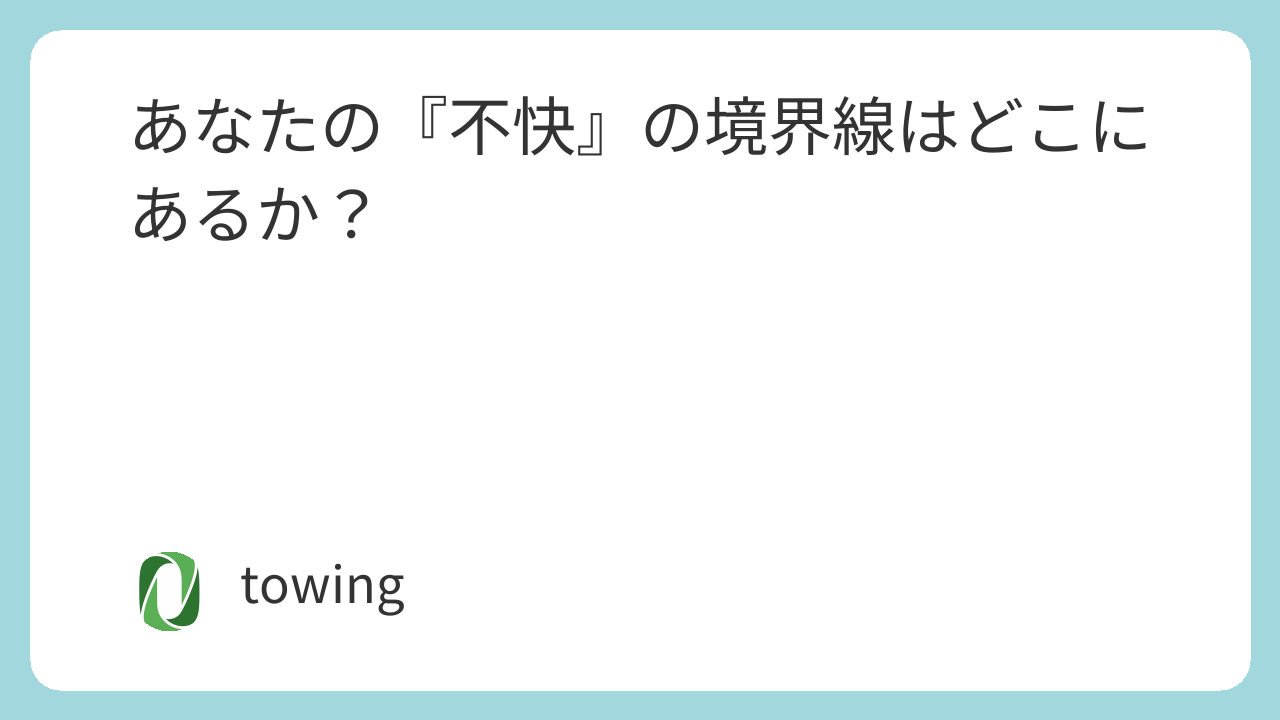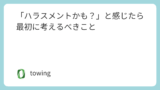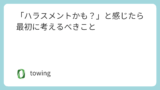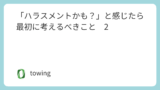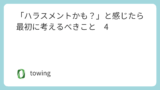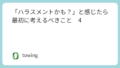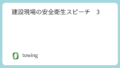以上の記事で、ここまで11のケースを見てきましたが、いかがでしたか?
「自分の経験とそっくりだ」
「これは自分なら平気だけど、これは絶対に許せない」
「どのケースも、判断が難しいと感じた」
様々な感想を抱いたことと思います。それでいいのです。
大切なのは、あなたが他人のケースを通して、あなた自身の「心のものさし」に意識を向けることができたという事実です。
次に、その「心のものさし」の目盛りをより明確にするための簡単なワークを行ってみましょう。
これは誰かに見せるためのものではありません。
あなた自身が、あなたの『不快』の境界線を知るための、プライベートな作業です。
ノートとペンを用意して、リラックスして取り組んでみてください。
書き込み式:どんな言動に「不快」を感じるか?
以下の文章の[____]の部分に、あなたが職場で「不快だ」「嫌だ」と感じる具体的な言動を、思いつくままに書き出してみてください。
一つや二つである必要はありません。些細なことだと感じても、遠慮なく書き出してみましょう。
– 私は、容姿や服装について[__________]と言われると、不快に感じる。
– 私は、プライベートなこと(恋愛、家族、休日など)について[__________]と聞かれると、嫌だと感じる。
– 私は、仕事のやり方について[__________]という態度を取られると、辛く感じる。
– 私は、飲み会などの場で[__________]されると、苦痛に感じる。
– 私は[__________]という言葉遣いをされると、心が傷つく。
– 私は、オンラインのやり取りで[__________]されると、監視されているようで息苦しく感じる。
– その他、私が「不快だ」と感じる言動は[__________]である。
いかがでしょうか。
書き出してみることで、あなたの「不快」の輪郭が少しはっきりとしてきたのではないでしょうか。
それは、あなたがあなた自身の「尊厳」を守るための大切な境界線なのです。
主観と客観を分けるための第一歩
このワークで、あなたが書き出したものは、あなたの「主観」です。
それは誰にも否定できない、あなただけの真実です。
そして、ハラスメントの問題を解決していく上で、次のステップは、そのあなたの「主観」が、社会のルールという「客観」の視点から見ると、どのように位置づけられるのかを知ることです。
なぜなら、会社や相談機関、あるいは法的な場であなたの苦しみを理解してもらうためには、あなたの「辛い」という感情を客観的な言葉で説明する必要が出てくるからです。
この本は、まさにその「主観」と「客観」をつなぐための橋渡しの役割を担います。
あなたが書き出した「不快感」が「法律の定義」や「判断軸」という客観的なものさしに照らすと、どう見えるのか。
それを、これから一緒に解き明かしていくのです。
世代・文化・価値観の違いを理解する
そして、主観と客観を分ける上で、もう一つとても大切な視点があります。
それは、「なぜ、相手はあなたが不快に感じる言動を、平気で行うのだろうか?」という問いです。
もちろん、中には明確な悪意を持ってあなたを傷つけようとしている人もいるでしょう。
しかし、多くのケースでは、相手はそれが「悪いことだ」と全く認識していない可能性があります。
なぜなら、その人の中にある「常識」や「価値観」が、あなたのものとは大きく異なっているからです。
その背景には、育ってきた「世代」の違いや「文化」の違いがあるかもしれません。
例えば、50代以上の管理職の中には、「頭を撫でる」ことを純粋に愛情表現だと考えている人がいます。
彼らが若い頃は、そうしたスキンシップが当たり前だった時代があったのです。
また、外国出身の同僚が距離感を詰めすぎるのは、その国の文化では親しみの表現として一般的だからかもしれません。
この「違い」を理解することは、相手を許すためではありません。
そうではなく、あなたが問題をより冷静に、そして戦略的に解決するための重要なヒントを与えてくれるのです。
相手の価値観を理解することで、あなたは無駄な感情的な対立を避け、「あなたの言動は、私の価値観では、こう受け取られてしまうのです」とより効果的にあなたの思いを伝えることができるようになるかもしれません。
私自身、長年の相談業務の中で学んだことがあります。
それは、「悪意のない加害者」と「悪意のある加害者」では、対処法が全く異なるということです。
前者には教育と対話が有効ですが、後者には毅然とした対応が必要になります。
この視点については、別途機会を見て詳しく掘り下げていきます。
まとめ:あなたの感情を大切にしながら、次のステップへ
今まで、具体的なケーススタディと簡単なワークを通して、あなたの「不快感」の輪郭を探ることを始めてみました。
11のケースを読み進める中で、あなたは次のようなことを感じたかもしれません:
– 「これは明らかにおかしい」と思うケース
– 「判断が難しい」と感じるケース
– 「自分だったら我慢してしまいそう」と思うケース
どの感想も、すべて正しいものです。
なぜなら、それはあなたの心が発する、正直なサインだからです。
重要なのは、その感情を「正しい」「間違っている」で判断しないことです。
まずは、「私はこう感じるのだ」という事実を、そのまま受け入れてください。
そして、次回からは、その感情を客観的な知識にあてはめていきます。
あなたの「これはおかしい」という直感が、法律的にはどう位置づけられるのか。
社会的にはどのような扱いを受けるのか。
それらを知ることで、あなたは自分の状況をより冷静に判断し、適切な行動を選択できるようになるでしょう。
もし、ここまで読んで「私の感じていることは、決して間違いではないのだ」と思えたなら、それは大きな前進です。
逆に、「やっぱり私の考えすぎなのかもしれない」と感じたとしても、それも重要な気づきです。
どちらの場合も、あなたは自分の感情と正面から向き合った勇気ある人です。
その勇気を持って、次に進んでいきましょう。
次回からは、いよいよハラスメントをめぐる法律という、あなたを守るための強力な「武器」であり「お守り」となる知識について、詳しく見ていくことにしましょう。