 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン
建設現場での「墜落・転落災害」をなくすために──今、現場に必要な5つのアプローチ
 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  開業準備
開業準備  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  ハラスメント
ハラスメント  開業準備
開業準備  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  開業準備
開業準備  開業準備
開業準備  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン  アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 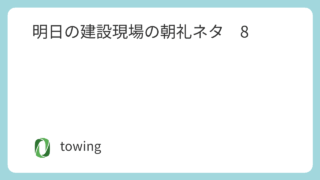 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 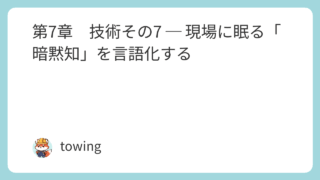 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 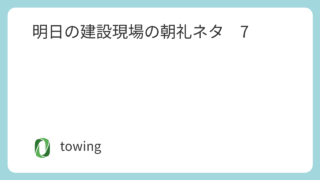 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 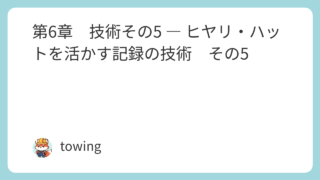 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 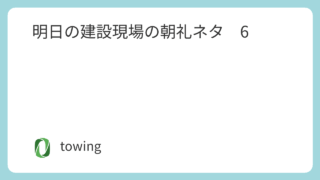 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 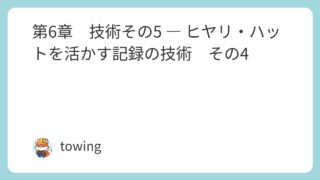 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 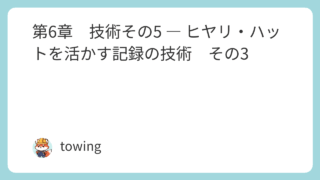 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 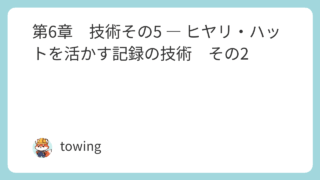 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 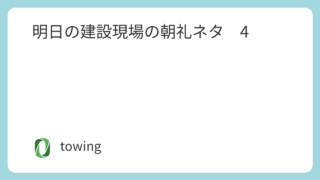 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン 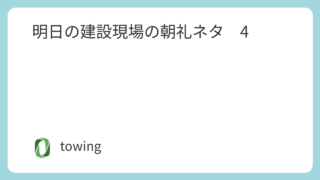 アンゼンアンシン
アンゼンアンシン