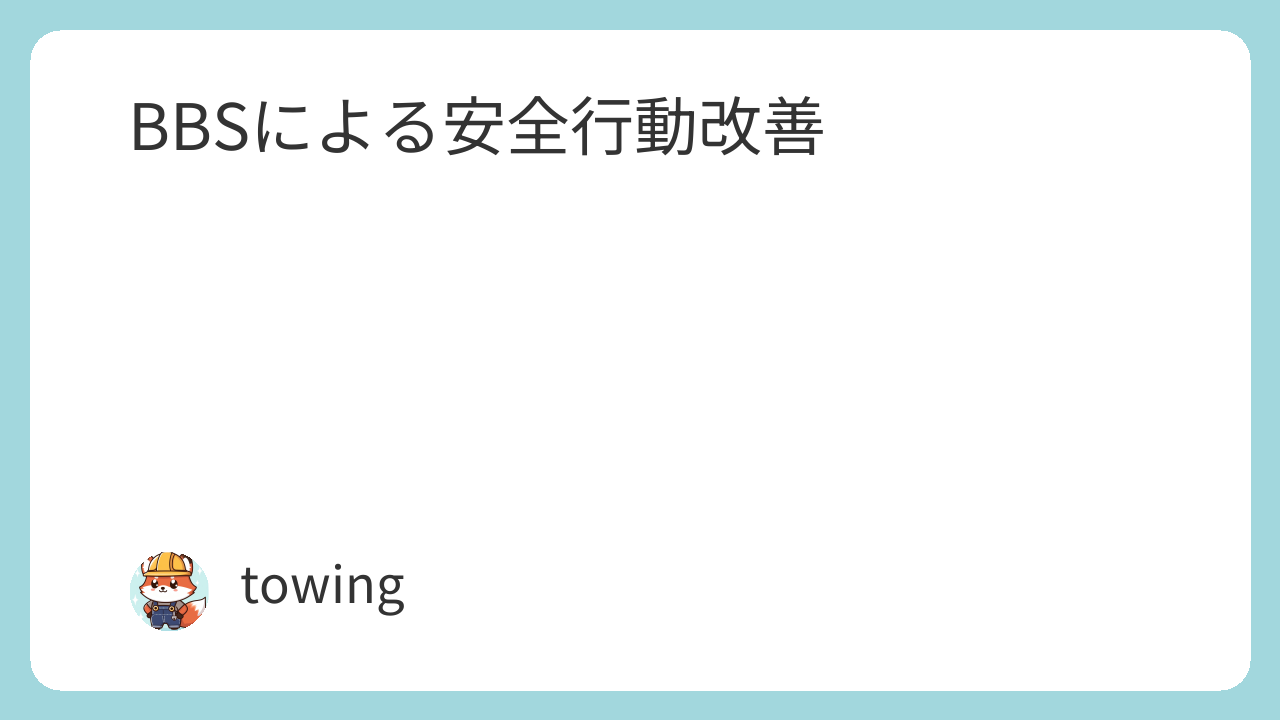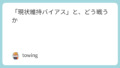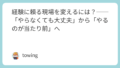■ 現状の問題点をBBSの視点で整理
BBSでは、事故や災害の原因を「人間の行動」に注目して改善していきます。そのためには以下の構造で考えるのが基本です:
① 行動(Behavior)
安全帯を使わない、昇降設備を整えない
② 直面する強化要因(Consequence)
- 【即時の強化】:作業が早く終わる、楽になる
- 【安全対策の結果】:手間がかかる、面倒、暑い
③ 結果として定着する行動
→「やらなくても大丈夫だった」経験が蓄積し、不安全行動が習慣化。
■ BBSによる改善アプローチ
以下に、経験過信や面倒くささによる不安全行動をBBSの考え方で是正する流れを示します。
1. 「望ましい行動」の明確化と見える化
- 「何が安全行動なのか?」を、現場ごとに具体的に定義する。
- 例:作業開始前に昇降設備を必ず確認、2m以上は安全帯着用など。
- ポスターやチェックリスト、現場ルールとして見える形にする。
2. 行動観察とフィードバック
- 指導者や安全担当者が、日常的に「行動観察」を行い、声かけと即時フィードバック。
- 「今、安全帯かけてるの良かったですね!」
- 「今日は暑いけど、しっかりフルハーネスですね」などポジティブ強化。
3. ポジティブな強化(強化因子の再設計)
- 手間がかかる安全行動に、メリットを実感させる工夫が必要。
- 表彰制度、称賛カード、ヒヤリハット賞の導入
- 「あなたの行動が仲間を守る」など意義づけ
4. 不安全行動の「仕組みからの抑止」
- 物理的・構造的な仕組みで不安全行動を起こしにくくする。
- 安全帯がないと動かない機械
- 昇降設備の設置をしないと作業できない工程設計
- これはBBSと併用すべき**制度的安全(System-based Safety)**の要素。
5. 安全文化の醸成(仲間の目)
- 「あの人がやってるなら自分もやろう」と思わせる同調圧力のポジティブ活用。
- ベテランが率先して行う
- 安全行動を称える掲示板やランキング
■ まとめ:経験への過信を“安全習慣”に変えるには?
| 状態 | 対応策(BBS的アプローチ) |
|---|---|
| 経験による過信 | 過去の無事より「今のリスク」に意識を向ける教育 |
| 面倒・手間 | 安全行動が「評価される」しくみづくり |
| 習慣化していない | 観察・フィードバックの継続と見える化 |
| 現場の空気 | ベテランによる模範、安全文化の浸透 |
行動は環境に影響される(レヴィンの法則)
「行動=f(人 × 環境)」という心理学的法則に沿えば、「安全に行動したくなる環境をつくる」ことが最大のポイントです。