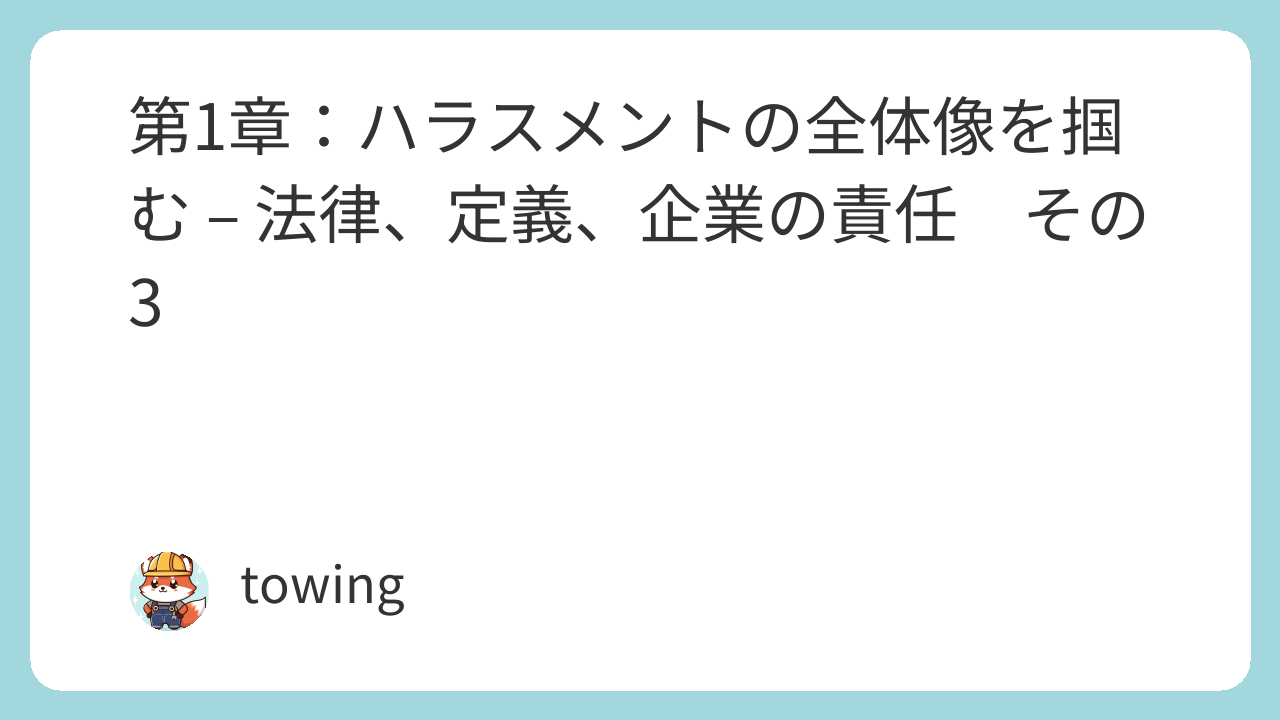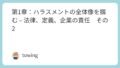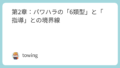3. 措置義務を怠った場合の「企業リスク」—— 3つの側面から見る深刻な結末
「法律で義務付けられているから対応しましょう」—— このような説明では、経営者の心は動きません。なぜなら、多くの経営者にとって、ハラスメント対策は「コストのかかる面倒な雑用」としか映らないからです。
しかし、私たちがクライアントに伝えるべきは、「対策を怠った場合のリスクがいかに深刻か」という現実です。これらのリスクを、法的・経済的・社会的という3つの側面から、具体的に理解していただくことが重要です。
(1) 法的リスク —— 直接的で避けられない制裁
最も分かりやすく、かつ避けることのできないリスクが、この法的制裁です。
民事上の損害賠償責任
ハラスメントの被害者は、行為者個人に対してはもちろん、企業に対しても損害賠償を請求することができます。これは以下の法的根拠に基づきます:
- 安全配慮義務違反(労働契約法第5条):使用者は労働者の生命・身体の安全を確保する義務を負う
- 使用者責任(民法第715条):従業員が第三者に損害を与えた場合、使用者も責任を負う
- 職場環境配慮義務違反:快適な職場環境を保持する義務
実際の判例を見ると、損害賠償額は決して軽微ではありません:
- パワハラによる精神疾患発症:300万円〜1,000万円
- セクハラによる退職強要:500万円〜1,500万円
- 重篤なメンタルヘルス障害:1,000万円〜3,000万円
重要なのは、「措置義務を果たしていなかった」という事実そのものが、裁判において「会社は安全配慮義務を怠った」と判断される決定的な材料になるという点です。つまり、法的義務の履行状況が、そのまま損害賠償責任の判断基準となるのです。
行政からの指導・勧告・企業名公表
各ハラスメント防止法に基づき、措置義務を講じていない企業に対しては、厚生労働大臣(実際は都道府県労働局長)による以下の行政措置が段階的に実施されます7:
- 助言:改善に向けた具体的な助言
- 指導:より強い行政指導
- 勧告:法的拘束力を持つ改善勧告
- 企業名公表:勧告に従わなかった場合の最終手段
特に「企業名公表」は、国が公式に「この企業はハラスメント対策を怠るブラック企業である」と認定することに等しく、企業にとって致命的なダメージとなります。
近年、労働局による企業名公表は確実に増加傾向にあり、「まさか自分の会社が」という油断は禁物です。一度公表されれば、その記録はインターネット上に永続的に残り続けることになります。
(2) 経済的リスク —— 静かに進行する「経営基盤の蝕み」
法的制裁のような派手さはありませんが、実は最も深刻なのがこの経済的ダメージです。なぜなら、これらは「見えにくい損失」として、長期間にわたって企業の体力を奪い続けるからです。
生産性の劇的な低下
ハラスメントが蔓延する職場で、従業員が100%のパフォーマンスを発揮することは絶対に不可能です。私が実際に見てきた企業の事例では、以下のような現象が必ず発生します:
- 創造性の枯渇:萎縮や恐怖心により、自発的な提案や改善活動が激減する
- チームワークの破綻:相互不信により、連携が取れなくなる
- 意欲の著しい低下:「どうせ頑張っても理不尽な目に遭う」という諦めが蔓延する
- ミスや事故の増加:精神的ストレスにより集中力が散漫になる
これらの影響は、被害者本人だけに止まりません。ハラスメントを目撃した周囲の従業員も「明日は我が身」という不安を抱き、職場全体の士気が著しく低下するのです。
休職・離職による人的損失
ハラスメントは、従業員のメンタルヘルスに深刻かつ長期的な影響を与えます。その結果として発生するのが:
- 休職者の増加:うつ病、適応障害等による長期休職
- 優秀な人材の離職:「こんな会社では働けない」という見切り
- 後遺症による能力低下:復職しても以前のパフォーマンスが発揮できない
特に、優秀な人材ほど「他に選択肢がある」ため、問題のある職場からは早期に退職してしまいます。結果として、企業には「問題を起こす人材」と「逃げ場のない人材」だけが残るという、最悪のスパイラルに陥ることになります。
採用・育成コストの膨大化
離職者が発生すれば、当然ながら新たな人材を採用し、一人前に育成する必要があります。一般的に、一人の従業員を採用・育成するコストは、年収の2〜3倍と言われています。
しかし、より深刻なのは「採用の困難化」です。現代は、企業の評判がSNSや転職口コミサイトを通じて瞬時に拡散される時代です。「あの会社はパワハラがひどい」「セクハラ上司がいる」といった情報は、優秀な求職者を確実に遠ざけます。
結果として、企業は「質の高い人材を採用できない」→「業績が悪化する」→「さらに職場環境が悪化する」という、負のスパイラルから抜け出せなくなるのです。
取引先・顧客からの信用失墜
BtoB取引においても、取引先企業のコンプライアンス体制は重要な評価要素となっています。特に大手企業では、取引先選定の際にハラスメント対策の実施状況を確認することが一般的になりつつあります。
措置義務を怠っている企業は、こうした「優良な取引先」から敬遠され、結果として事業機会の損失につながる可能性があります。
(3) 社会的リスク —— 一度失えば回復困難な「信用とブランド」
これは、企業の存続基盤そのものに関わる、最も回復困難なリスクです。
企業ブランド・イメージの致命的毀損
一度「ハラスメントを放置する企業」というレッテルが貼られてしまえば、それを払拭するのは容易ではありません。特に以下の影響は深刻です:
- 消費者離れ:BtoC企業では、不買運動や顧客離れに直結
- 求職者からの忌避:優秀な人材から選ばれない企業になる
- メディアでの取り上げ:ハラスメント問題は格好の「ニュースネタ」
現代の消費者や求職者は、商品・サービスの品質だけでなく、企業の姿勢や価値観も厳しく評価します。「人権を軽視する企業」と認識されれば、どんなに優れた商品やサービスを提供していても、支持を失うことになりかねません。
ESG投資からの排除
近年、投資の世界では「ESG投資」(Environment:環境、Social:社会、Governance:企業統治を重視する投資)が主流となっています。この「Social」の評価項目には、「従業員の人権尊重」「働きやすい職場環境の整備」が含まれており、ハラスメント対策の実施状況は重要な判断材料となります。
ハラスメント問題を抱える企業は、こうした投資マネーから排除され、資金調達や事業拡大の機会を失う可能性があります。これは、将来の成長機会の喪失を意味する、極めて深刻な問題です。
社会的信用の完全失墜
企業名公表や大きなハラスメント事件が発生した場合、その企業の社会的信用は地に落ちることになります。信用回復には、少なくとも数年から十数年の歳月と、膨大なコストが必要となります。
しかも、インターネット時代の現代では、一度ネット上に記録された「負の情報」は、半永久的に残存し続けます。将来の経営陣が変わったとしても、過去の「汚点」は消えることがないのです。
まとめ:ハラスメント対策は「義務」であり「投資」である
本章で見てきたように、ハラスメント対策は、もはや「余裕があるときに取り組む課題」ではありません。それは、企業が社会の一員として存続していくための「最低限の義務」であり、同時に、最も重要な経営資源である「人材」を守り、育てるための「賢明な投資」なのです。
私たち社会保険労務士が、この重要性を顧問先に理解してもらうためには、単に「法律で決まっているから」という表面的な説明ではなく、「対策を怠った場合のリスクがいかに深刻か」という現実を、具体的かつ説得力を持って伝える必要があります。
そして何より重要なのは、私たち自身が、この分野における「真のプロフェッショナル」として、確実な知識と実践力を身につけることです。
次章では、この基礎知識を土台として、最も相談件数が多く、かつ判断が困難とされる「パワーハラスメント」について、その具体的な類型と、「正当な指導」との境界線を見極めるための、より実践的な判断基準を詳しく学んでいきます。
顧問先から「これってパワハラになりますか?」と相談されたとき、あなたは明確で的確な回答ができるでしょうか。その自信がまだ十分でないとすれば、次章での学びが、あなたの実務能力を飛躍的に向上させることになるはずです。