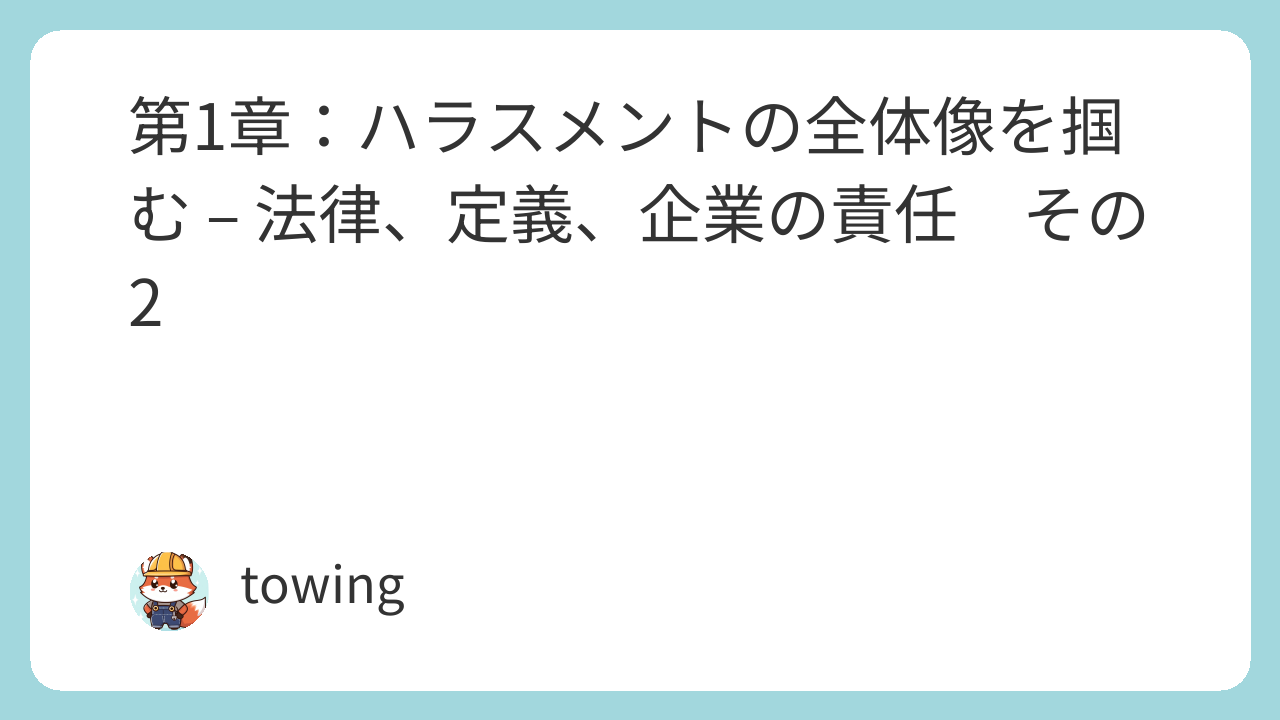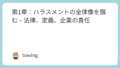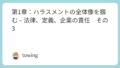2. 法律が企業に求める「措置義務」—— 4つの柱で構築する防災システム
3つのハラスメントの定義を理解したところで、次に重要なのは、法律が企業(事業主)に対して具体的に何を求めているかです。
これが「措置義務」と呼ばれるものです。私はこれを「ハラスメントという災害から従業員と会社を守るための防災システム」と説明しています。地震や火災に備えて避難経路を確保し、消火器を設置し、定期的に訓練を行うように、ハラスメントという「人災」に対しても、体系的な予防・対応システムが必要なのです。
この防災システムは、以下の4つの柱で構成されており、3つのハラスメントすべてに共通して求められます。
(1) 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 —— 「不退転の決意」の表明
第1の柱は、「我が社はハラスメントを絶対に許さない」という会社の断固たる姿勢を、内外に示すことです。これは単なる「お飾り」ではありません。法的な措置の根拠となる、極めて重要な基盤です。
具体的に求められる取組み:
- 方針の明確化
- 職場におけるハラスメントの内容とあってはならない旨の方針を明確化する
- ハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針と対処内容を就業規則等の文書に規定する
- 方針の周知・啓発
- 規定した方針を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等により全従業員に周知・啓発する
- ハラスメント防止の重要性について、従業員の理解を深めるための研修・講習等を実施する
ここで最も重要なのは、就業規則への明記です。就業規則に「服務規律」としてハラスメント禁止を明確に記載し、それに対する懲戒処分の内容を「懲戒事由」として規定することで、初めて法的な実効性を持つのです。
多くの企業で見落とされがちなのは、この「文書化」の重要性です。口約束や社内の暗黙の了解では、いざトラブルが発生した際に、毅然とした対応を取ることができません。
「うちは従業員20人の小さな会社だから、そこまでする必要はないでしょう」—— このような声をよく聞きます。しかし、規模の大小に関係なく、措置義務は全ての事業主に課されているのです。
(2) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 —— 機能する「駆け込み寺」の創設
第2の柱は、ハラスメントが起きた、あるいは起きそうになった時に、従業員が躊躇なく声を上げられる「安全な場所」を用意することです。
具体的に求められる取組み:
- 相談窓口の設置
- 相談窓口をあらかじめ定め、従業員に周知する
- 相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする
- 適切な対応範囲
- ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、発生のおそれがある場合や、ハラスメントに該当するか微妙なケースでも、広く相談に対応する
この相談窓口で最も重要なのは、「実効性」です。形式的に窓口を設置するだけでは意味がありません。
私の経験上、機能しない相談窓口には共通点があります:
- 相談窓口が上司や人事部だけで、相談しにくい構造になっている
- 相談内容が必ず漏れる仕組みになっている
- 相談しても何も変わらないという不信感が蔓延している
- 相談者が不利益を受けるリスクが高い
逆に、機能する相談窓口の特徴は:
- 複数の相談ルートが用意されている(社内・社外、男性・女性など)
- 秘密保持が徹底されている
- 迅速で適切な対応が期待できる
- 相談者の安全が確実に守られる
特に中小企業では、社会保険労務士が外部相談窓口を担うことで、従業員にとって相談しやすい環境を作ることができます。これは私たちにとって、重要な付加価値サービスの一つと言えるでしょう。
(3) 事後の迅速かつ適切な対応 —— 「初期消火」体制の確立
第3の柱は、相談が寄せられた際の対応プロセスです。火災で言えば「初期消火」に相当する、極めて重要な段階です。
具体的に求められる取組み:
- 事実関係の迅速かつ正確な確認
- 相談者、行為者の双方から事実関係を聴取する
- 双方の主張が食い違う場合は、第三者からも事実確認を行う
- 被害者に対する適正な措置
- 事実確認ができた場合、速やかに被害者に対する配慮措置を講じる(配置転換、労働条件の変更など)
- 行為者に対する適正な措置
- 事実確認ができた場合、速やかに行為者に対する措置を講じる(懲戒処分、謝罪、研修など)
- 再発防止措置
- 職場におけるハラスメント防止の方針を改めて周知・啓発する
- 再発防止のための措置を講じる
この段階でのキーワードは「迅速性」です。対応が遅れれば遅れるほど、以下の問題が発生します:
- 被害者の心理的ダメージが深刻化する
- 職場の他の従業員にも不安が広がる
- 事実確認が困難になる(記憶の曖昧化、証拠の散逸など)
- 問題の収拾がより困難になる
一方で、「正確性」も同程度に重要です。事実確認を怠ったまま拙速に処分を行えば、今度は行為者とされた従業員から不当処分として争われる可能性があります。
この「迅速性」と「正確性」のバランスを取ることが、実務上最も難しい部分の一つです。
(4) その他、併せて講ずべき措置 —— システムを支える「安全装置」
第4の柱は、上記3つの措置を効果的に機能させるための「安全装置」です。
具体的に求められる取組み:
- プライバシー保護
- 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を従業員に周知する
- 特に、性的指向・性自認、病歴、不妊治療等の機微な個人情報の取扱いには細心の注意を払う
- 不利益取扱いの禁止
- ハラスメントの相談をしたこと、事実確認等に協力したこと、都道府県労働局に相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、従業員に周知・啓発する
この2つの措置は、相談窓口を機能させるための「生命線」です。
プライバシーが守られないとわかれば、誰も相談しなくなります。相談したことで不利益を被るリスクがあれば、泣き寝入りを選ぶ従業員がほとんどでしょう。
特に「不利益取扱いの禁止」は、法的にも極めて重要な意味を持ちます。この禁止に違反した場合、事業主は行政からの指導・勧告の対象となり、さらには企業名公表のリスクも負うことになります。