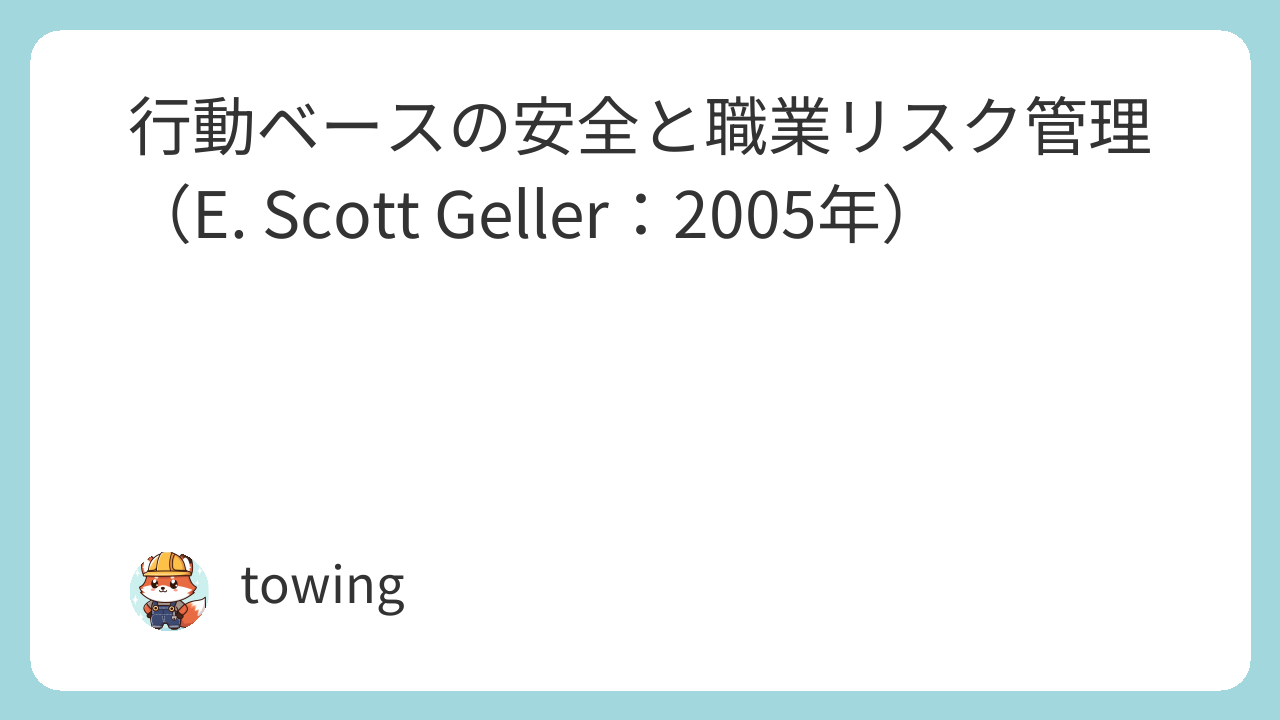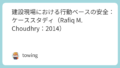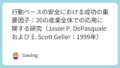職場安全の革命:行動ベースの安全(BBS)が切り拓く新たな可能性
皆さんの職場では、安全管理にどのような課題を感じていますか。「ルールを作っても守られない」「事故は減らない」そんな悩みを抱えていませんか。実は、従来の安全管理アプローチには、根本的な限界があるのです。
私がこれまで数多くの企業を指導してきた経験から申し上げると、職場の安全は単にルールや規制を守るだけでは解決できない、より深い課題を抱えています。
現実と向き合う:労働災害の深刻な実態
まず、現実を見つめてみましょう。米国のデータを例に取ると、44歳以下の住民の死因第一位が「意図しない傷害」です。毎年推定7,000人から11,000人もの従業員が職場で命を落とし、250万人から1,130万人が重傷を負っています。
これらの労働災害は、2005年には1,160億ドルもの経済的損失をもたらすと推定されており、その費用は年々増加の一途を辿っています。
このような悲劇と莫大なコストを防ぐために、私たちは何ができるのでしょうか。その答えの一つが、今回ご紹介する行動ベースの安全(Behavior-Based Safety, BBS)アプローチです。
行動ベースの安全(BBS)とは:パラダイムシフトの本質
行動ベースの安全(BBS)は、職場のリスクを管理し、傷害を防止するための行動科学に基づいたアプローチです。
従来のトップダウン型の安全管理が「指示と統制」に重きを置いていたのに対し、BBSは従業員が自ら職場のリスクをコントロールするためのツールと手順を提供し、ボトムアップで安全を向上させることを目指します。
BBSは、B.F.スキナーの行動科学に基づき、「人々が何をするか(行動)」に焦点を当てます。そして、「なぜその行動をするのか」を分析し、研究に裏付けられた介入技術を適用して行動プロセスを改善していくのです。
これは、従業員が「考えて安全」という受け身の姿勢から、積極的に安全行動に取り組む「行動で安全」というパラダイムシフトを促すものだと、私は確信しています。
なぜBBSが職場の安全に不可欠なのか
職場で発生する傷害や事故の多くは、人の行動に起因するとされています。BBSは、この人間行動の側面を体系的に管理することを目指す、極めて合理的なアプローチです。
その理由は2つあります。
1. 外的要因への着目による根本解決
BBSは、客観的に定義しにくい「内的な状態や特性」よりも、行動に影響を与える「環境要因」を特定し、それを変更することに焦点を当てます。
これには、不適切な管理システムや、危険な作業慣行を意図せず助長するマネージャーの行動なども含まれることを忘れてはなりません。
2. 罰則ではなく、ポジティブな結果の重視
従来の安全管理では、事故記録率などの「失敗や損失」を評価指標としがちでした。しかしBBSでは、望ましい行動を促すためにポジティブな結果や強化を重視します。
罰則は、人々の自由感を低下させたり、報復行動を誘発したりする可能性があります。BBSは、人々が職業リスクを低減し、傷害を防止するための目標を設定する、より積極的なアプローチを提供します。
BBSの実践フレームワーク:7つの主要原則
BBSの成功は、以下の7つの主要原則に沿って適用されることで達成されます。これは、まさに「しくみ」として機能するものです。
1. 介入を観察可能な行動に集中させる
BBSは、特定の行動を建設的な変化のターゲットとします。これは、危険な行動の頻度を減らすか、安全な行動の頻度を増やすことを意味します。
2. 行動を理解し改善するために外的要因を探す
行動に影響を与える環境要因(例:不適切な管理システム)を特定し、必要に応じて変更します。
3. アクティベーターで指示し、結果で動機づける
これはABCモデル(Activator-Behavior-Consequence:先行事象-行動-結果)として知られ、行動が発生する理由を理解し、行動に利益をもたらす介入設計に役立ちます。
アクティベーター(指示や合図)は、それによって得られる結果の強さに依存します。
4. 行動を動機づけるためにポジティブな結果に焦点を当てる
罰則(ネガティブな結果)を使用するのではなく、ポジティブな強化を通じて行動を促進します。
5. 介入を改善するために科学的手法を適用する(DO ITプロセス)
介入プロセス前後で行動を客観的に観察・測定し、改善のためのフィードバックを提供します。
このプロセスは4つのステップで構成されます:
D (Define – 定義): ターゲットとなる行動(危険行動か安全行動か)を明確に定義します。例えば、個人保護具(PPE)の使用や、物の持ち上げ方などが含まれます。行動チェックリストを作成することで、従業員のオーナーシップを育みます。
O (Observe – 観察): 訓練されたオブザーバーが、特定の安全行動や危険行動を観察します。これは「欠点探し」ではなく、変更または継続が必要な行動や条件を発見するための「事実発見の学習プロセス」です。観察された行動の結果は、「安全であった割合」として集計されることが推奨されます。
I (Intervene – 介入): 安全行動を増やすか、危険行動を減らすための介入策を設計・実施します。行動観察の結果を作業者個人やグループにフィードバックすることは、パフォーマンス改善に非常に効果的です。その他、安全スローガン、ヒヤリハット報告、目標設定、感謝カード、コーチング、インセンティブ・報酬プログラムなども有効です。
T (Test – テスト): 観察結果に基づいて介入アプローチを洗練または変更します。目標とする頻度に達しない場合は分析し、介入を見直します。このプロセスを通じて、従業員は事実上「行動科学者」となり、継続的な改善を推進します。
6. 情報を統合するために理論を使用し、可能性を制限しない
理論は、系統的な観察から得られた情報を統合するために使用されるべきであり、研究や介入の可能性を制限するために使用されるべきではありません。
7. 内的な感情や態度を考慮して介入を設計する
介入は感情状態に間接的に影響を与えるため、肯定的な強化は罰則よりも望ましい感情状態を引き起こします。介入がエンパワーメント、信頼、チームワークを築くように設計することが重要です。
行動変容の「流れ」:段階的アプローチの実践
BBSは、行動が「他者主導」から「自己主導」を経て「習慣化」するまでの流れを捉え、それぞれに適切な介入アプローチを適用します。これは、まさに「仕込み」の段階です。
行動の3つのタイプ
他者主導行動 (Other-directed): 従業員がポリシーや訓練など、他者の指示に従う段階です。
自己主導行動 (Self-directed): 従業員が関連する指示を記憶・内面化し、自ら行動を活性化する段階です。意図的に危険を冒す「計算されたリスク」も自己主導行動に分類されます。
習慣化された行動 (Automatic/Habitual): 行動が頻繁かつ一貫して行われ、習慣が形成された段階です。
介入の3つのアプローチ
指示的介入 (Instructional intervention): 新しい行動を開始させたり、行動を自動段階から自己主導段階に移行させたりするために、アクティベーターや先行事象を使用します。主に教育セッション、訓練、指示的フィードバックがこれにあたります。
支援的介入 (Supportive intervention): 正しい方法を学んだ人が、その行動を自然なルーティンの一部にするために、練習を続けることを支援します。ポジティブな結果(報酬、認知)の適用に焦点を当て、感謝されていると感じさせることで、その行動を再度行う可能性を高めます。
動機づけ的介入 (Motivational intervention): やり方を知っていても実行しない「計算されたリスク」を冒す人々に対して、外部からの働きかけを行います。インセンティブや報酬プログラムがこれに当たります。罰則やペナルティは効果が薄い場合が多いことを、私たちは経験から知っています。
自己管理 (Self-management): 従業員が「DO ITプロセス」を自身の行動に適用することです。
説明責任から責任へ:安全文化の醸成
大規模な安全衛生推進において重要なのは、「説明責任(Accountability)」と「責任(Responsibility)」の区別です。
説明責任は、特定の目標を達成することですが、責任はそれを超えて、期待以上の行動を自発的に行うことを意味します。多くの組織で安全パフォーマンスが停滞しているのは、従業員が説明責任を超えて、自らの安全に対する責任を拡張する必要があるためだと、私は見ています。
特に一人で作業する従業員が多い職場では、上司や同僚が常に安全作業を監視できるわけではありません。そのため、企業リーダーや安全衛生の専門家にとっての課題は、安全に対する責任感や自己責任を育むような労働文化を醸成することなのです。
結論:新たな安全文化の創造
行動ベースの安全(BBS)は、職場の傷害を防止するための強力で実績のあるアプローチです。従来の「指揮・統制」や「強制」に依存するアプローチが限界を迎える中で、BBSは従業員が自らの安全パフォーマンスをコントロールするためのツールと手順を提供し、ボトムアップでのエンパワーメントを可能にします。
BBSは、単なる安全規則の順守や、記録可能な傷害率の削減といった結果指標に焦点を当てるのではなく、傷害予防プログラムへの質の高い参加を促します。これは、「安全は態度だ」といった漠然としたスローガンを、「今やっていることを続ければ、今得ているものを得続ける」という、行動と結果の明確な関連性を示す考え方に置き換えるものです。
BBSは、職場におけるリスクを低減し、意図しない傷害を防止するために、行動分析の応用を改善し、拡大するためのさらなる研究を促すものです。皆さんの組織でも、この効果的なアプローチを導入することで、より安全で生産性の高い職場環境を築くことができるでしょう。
論文情報:
- 論文のタイトル(日本語訳): 行動ベースの安全と職業リスク管理
- 著者: E. Scott Geller
- 発行年: 2005年