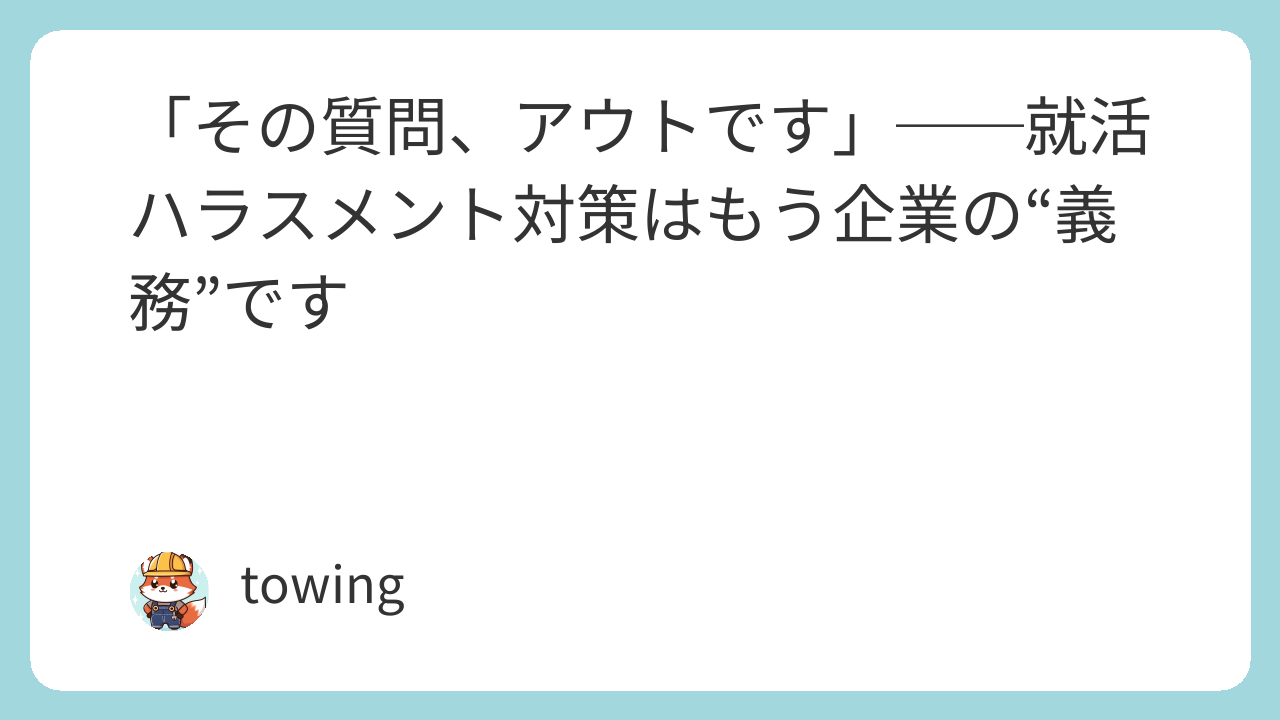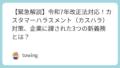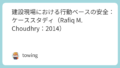はじめに
「恋人はいるの?」「ご両親はどんなお仕事を?」「OB訪問のあと、食事でもどう?」
こんな質問、まだ採用面接で口にしていませんか?
もし少しでも心当たりがあるなら、すぐに見直しを。
2025年(令和7年)の法改正により、企業は就活生やインターン生に対するハラスメント、いわゆる「就活ハラスメント」を防止する措置を講じることが義務づけられました。
「まだうちの社員じゃないし」「昔は当たり前だった」──そんな言い訳はもう通用しません。
これからの採用活動では、学生の人権を守る姿勢が企業評価の分かれ目になります。
今回は、採用担当者が知っておくべき最新の法改正と、企業価値を高めるための具体策を解説します。
法改正で明確に。「就活生も保護の対象です」
今回の改正でポイントとなるのは、ハラスメント防止義務の対象が“求職者”にも広がったこと。
これまでの法制度は主に自社の従業員を対象にしていましたが、今後は、就職活動中の学生やインターン生も保護の対象になります。
つまり、採用面接という優位な立場を利用した不適切な言動は、企業としての法的責任を問われる重大な問題になったのです。
これって就活ハラスメント?代表的なNG行動リスト
「どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか分かりづらい」
そんな声に応えて、代表的なNG行動を整理しておきます。
セクシュアルハラスメントの例
- プライベートに踏み込んだ質問
└「恋人はいるの?」「結婚や出産の予定は?」など - 容姿や服装へのコメント
└「その服、似合ってるね」「もっと明るい色の方がいいよ」 - OB/OG訪問での不適切な誘い
└ 食事や飲酒にしつこく誘う
└ 「内定に影響するかもよ」といった圧力をかける
パワーハラスメントの例
- 圧迫的な面接
└ 「君、そんな受け答えでやっていけるの?」
└ 回答に詰まった学生をあえて責め立てる - 不当な要求
└ 他社の選考を辞退するよう強要(いわゆる「オワハラ」)
└ 「内定を出す代わりに◯◯して」などの取引条件
これらは学生に精神的苦痛を与えるだけでなく、SNSや口コミを通じて企業の評判を一気に落とすリスクを伴います。
採用担当者が今すぐ取り組むべき3つのステップ
法改正に対応するには、以下の3つの対策が必須です。
1. ハラスメント禁止方針の明文化と周知
まずは、就活ハラスメントを一切容認しないという方針を明確にし、社内外にしっかり伝えましょう。
- 面接官・リクルーターへの研修
└ どんな質問がNGなのか、明確なガイドラインを用意する - 学生への意思表示
└ 採用ページに「ハラスメント行為禁止」「公正な選考の実施」を明記する
2. 学生向け相談窓口の設置
万が一ハラスメントを受けたと感じた場合に備え、学生専用の相談窓口を設けましょう。
- 専用窓口の設置と案内
└ 採用サイトや選考メールで窓口を明示
└ 「相談しても選考に影響しない」ことを明記して、安心感を提供する
3. 問題発生時の迅速な対応体制
相談があった際には、速やかにかつ誠実に対応する仕組みが求められます。
- プライバシーに配慮した調査
- 被害学生への謝罪・ケア
- 加害行為を行った社員への適切な処分
対策は“企業価値”にも直結。「プラチナえるぼし」新基準へ
今回の法改正に関連して注目されているのが、「プラチナえるぼし認定」の基準変更です。
この認定制度は、女性活躍推進に積極的な企業に与えられるものですが、今後は「就活ハラスメント防止の取り組み」が新たな評価項目に加わります。
つまり、ハラスメント対策に真剣に取り組むことは、優秀な人材から「選ばれる企業」になるための強力な武器でもあるのです。
まとめ──企業の顔として、誠実に学生と向き合おう
学生の人権を尊重し、公正な採用活動を行うことは、企業としての“責任”であり、同時に“未来への投資”でもあります。
採用担当者や面接官一人ひとりが、自らの言動に責任を持ち、誠実に学生と向き合うこと。
その姿勢こそが、企業ブランドを高め、未来を担う人材を惹きつける最も確かな方法です。
「この会社で働きたい」──そう思われる採用の現場を、私たち一人ひとりの行動からつくっていきましょう。