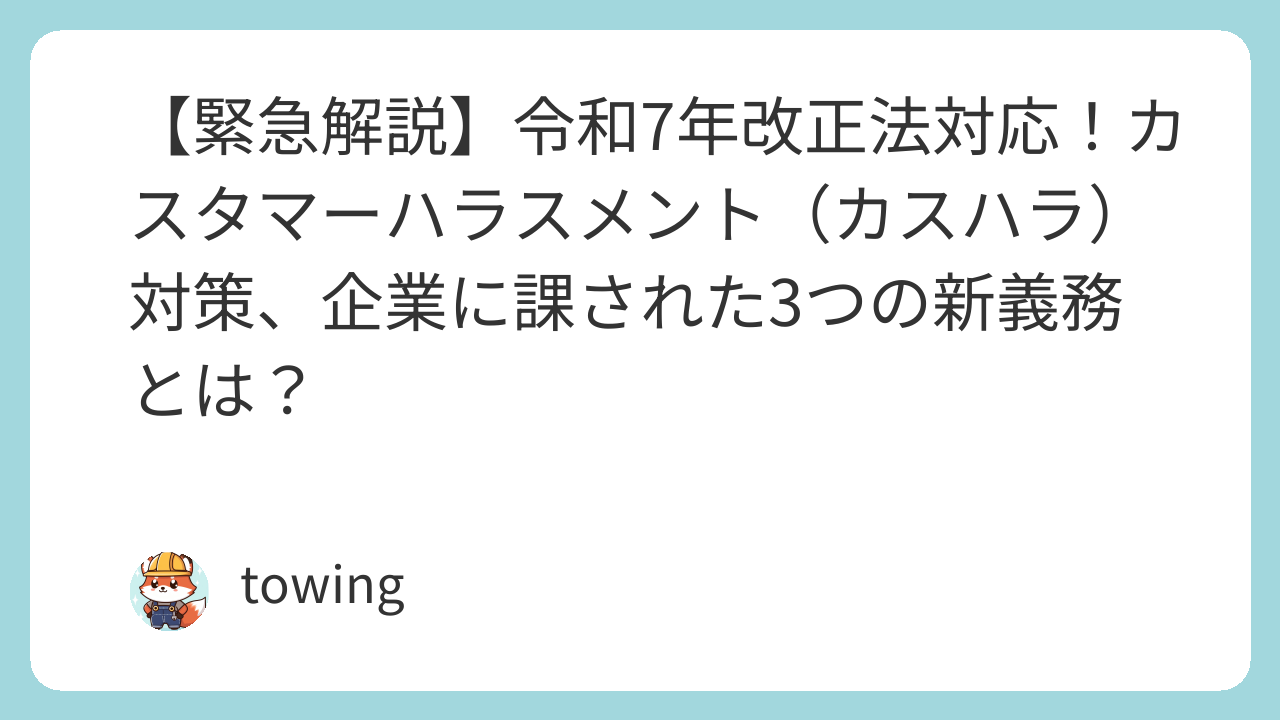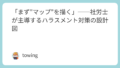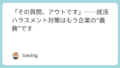はじめに
「お客様は神様です」
そう信じて疑わなかった時代は、もう終わりを迎えようとしています。
2025年(令和7年)施行の改正法によって、企業にはカスタマーハラスメント(いわゆる“カスハラ”)への対策を講じることが法的義務として課されることになりました。これまで努力義務にとどまっていた対応が、ついに「義務化」されるのです。
飲食、販売、サービス、医療、介護、行政窓口など、あらゆる業種で「顧客対応の限界」を感じていた企業にとって、これは現場を守る大きな追い風となるでしょう。
本記事では、法改正のポイントと、企業が講じるべき「3つの具体策」について、実務目線でわかりやすく解説します。
カスハラは「もはや他人事ではない」──企業に課された法的責任
今回の改正で最も重要なのは、顧客からの迷惑行為への対応が“法的に必須”になるという点です。
これまで、パワハラ・セクハラについては防止措置が義務化されていましたが、カスハラについては「できる限り対応してください」という努力義務にとどまっていました。
しかし、令和7年以降は違います。事業主には、カスハラを防ぐための雇用管理上の措置を取ることが義務づけられ、違反すれば行政指導や社会的批判の対象になる可能性も出てきます。
あなたの会社は大丈夫? カスタマーハラスメントの定義とは
法令上、カスハラとは、以下の3要件をすべて満たす行為を指します。
- 顧客、取引先、施設利用者などの第三者による行為であること
- 社会通念上、許容される範囲を超えた言動であること
- 労働者の就業環境を害していること
つまり、「お客様」の立場からの行為であっても、一線を越えればハラスメントになるということです。
代表的なカスハラの例
- 暴力・暴言:怒鳴りつける、机を叩く、人格を否定する言葉
- 過剰な謝罪要求:「土下座しろ」「その場で責任者を呼べ」などの強要
- 不当な要求:法外な値引き、金銭補償、自社に無関係な私的要求
- 長時間の拘束:数時間にわたるクレーム電話、店舗内での居座り
- 個人攻撃:従業員の名前や顔写真をSNSで晒す、誹謗中傷の書き込み
カスハラと正当な苦情の違いは、「社会通念上、許容される範囲かどうか」です。判断に迷うケースもあるため、社内での線引きを明確にしておくことが重要です。
企業が取るべき「3つの具体的措置」
では、カスハラ防止のために企業が取るべき措置とは何か。ここでは、政府方針に基づく3つの対策を整理します。
1. 方針の明確化と周知・啓発
まず必要なのは、会社としての明確なスタンスです。
「カスハラは許しません」というメッセージを、社内外にしっかり示すことが第一歩になります。
- 社内への明示
└ 就業規則に明文化し、従業員への研修を徹底
└ カスハラとは何か、どのように対応するかを具体的に共有 - 社外への発信
└ 店舗やHPに「迷惑行為に対する対応方針」を明記(例:「当社では従業員へのハラスメントをお断りしています」)
└ 顧客への注意喚起を行い、適正な対応を促す
2. 相談体制の整備
従業員が安心して声を上げられる相談窓口の設置は、企業の信頼性を左右する重要な要素です。
- 人事・労務部門に専用窓口を設置
└ プライバシー配慮を徹底し、相談したことによる不利益を防止 - 相談対応者への研修
└ 被害者対応の基本姿勢、心理的サポート、外部連携の方法などを教育
3. 発生後の迅速・適切な対応
カスハラが実際に発生した場合、迅速かつ組織的に対応する体制づくりが求められます。
- 対応マニュアルの整備
└ 現場スタッフが一人で抱え込まないよう、手順を明文化 - 組織的対応の構築
└ 部署を超えた連携体制を整備し、対応の属人化を防ぐ - 外部機関との連携
└ 悪質なケースには、弁護士・警察・産業医などと連携する備えも必要
注意すべき2つの視点──過剰防衛にならないために
カスハラ対策を進めるうえで、顧客対応を萎縮させない工夫も重要です。
- 正当なクレームは受け止める
「不快だ」と言われたからといって全てをシャットアウトしては逆効果です。
あくまで問題は“社会通念を超えた”迷惑行為。冷静な線引きが大切です。 - 障害者への合理的配慮は引き続き必須
障害のある方に対する合理的配慮は、カスハラとは別の法的義務(障害者差別解消法)として、引き続き企業に求められています。
まとめ:従業員を守ることが、企業の信頼と成長につながる
カスハラ対策は、単なる「守りの体制」ではありません。
従業員が安心して働ける職場は、離職率の低下・顧客満足度の向上・組織の安定という形で、確実に企業の成長へとつながります。
2025年、法改正のタイミングを機に、自社の体制を見直してみませんか?
「一人ひとりを大切にする企業」こそが、これからの時代、社会からも顧客からも選ばれていくのです。