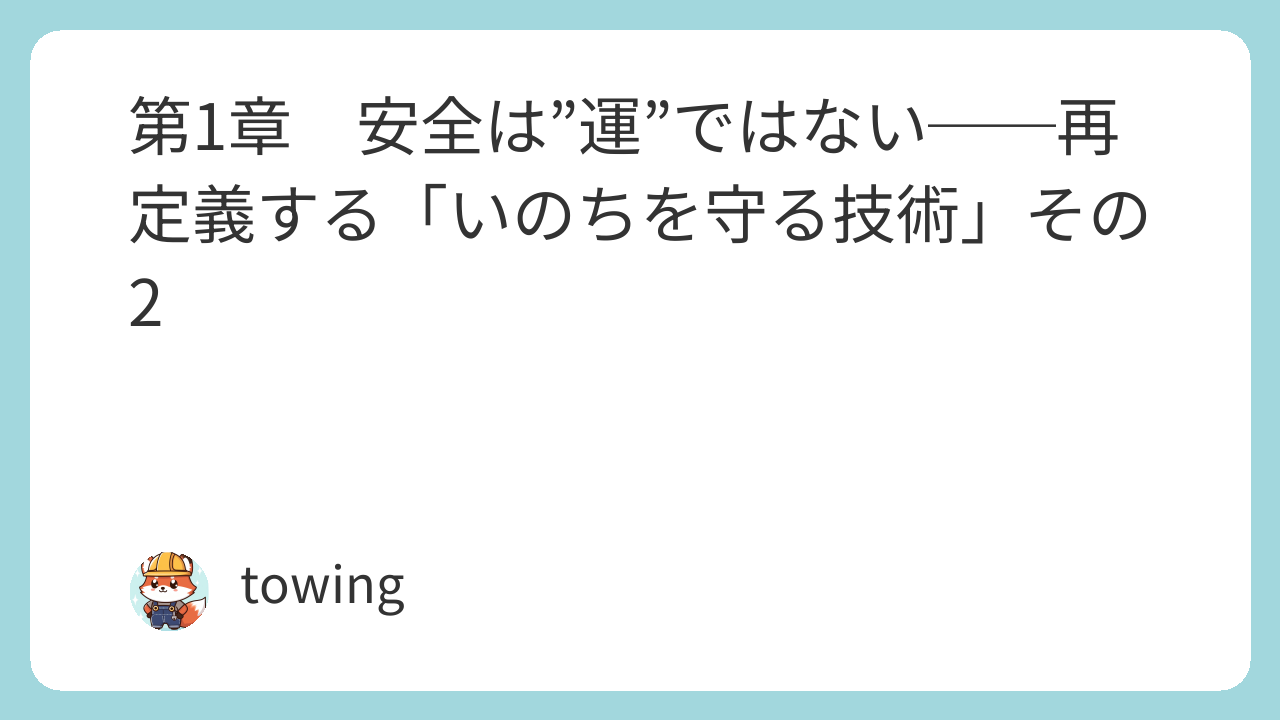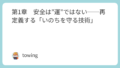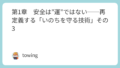行動は『しくみ』で変わる──レヴィンの法則
では、「”気をつける”ことに頼らない」とは、どういうことでしょうか。そのヒントになるのが、社会心理学の父と呼ばれるクルト・レヴィンが提唱した「レヴィンの法則」です。
彼は、人間の行動を非常にシンプルで本質を示した式で表現しました。
B = f(P, E)
- B (Behavior):
人間の行動 - P (Personality):
その人の個性(性格、知識、経験、意欲、体調など) - E (Environment):
その人を取り巻く環境(場所、道具、ルール、人間関係、職場の文化など)
この法則が教えてくれるのは、「人の行動は、本人のやる気や性格(P)だけで決まるのではなく、その人が置かれている状況(E)と相互に影響し合って決まる」という、極めて重要な事実です。
これまでの安全管理は、事故の原因を作業員個人の問題(P)に求めすぎていました。「経験が不足だから」「真面目じゃないから」「安全意識が低いから」。だから対策も教育や訓練、精神論で「P」に働きかけることばかりでした。
もちろん、知識やスキルは安全の大事な基盤です。でも、人の性格や価値観を外から変えるのは本当に難しく、時間もかかります。つまり、「P」だけのアプローチでは効果は限定的で、すぐに結果も出にくいのです。
そこでレヴィンの法則が教えてくれるもう一つのアプローチが、「E(環境)」を変えることの重要性です。
例えば、「ついお菓子を食べてしまうという行動(B)」に悩む人がいるとします。「我慢しろ」「意志を強く持て」というのがPへのアプローチ。でも、たいていの場合、これは失敗に終わります。
一方、Eへのアプローチはこう考えます。「そもそも、なぜお菓子を食べてしまうのか?」と。原因が「机の引き出しにお菓子が入っているから」という環境にあるなら、対策は驚くほど簡単です。お菓子を処分し、買わないようにする。つまり、「望ましくない行動を取りにくい環境を作る」ということです。
現場の安全も、まったく同じ考え方ができます。
「高所作業で安全帯を使わない(B)」作業員がいるとします。「ルールを守れ!」と叱る(Pへのアプローチ)だけでは、見ている人がいなければ、また同じことを繰り返すかもしれません。
Eへのアプローチでは、こう問います。「なぜ、彼は安全帯を使わないんだろう?」と。
- 安全帯を掛けるべき場所が、作業の邪魔になる不便なところにあるからじゃないか?
- 使い方が手順書にちゃんと書かれてなくて、自己流になっているからじゃないか?
- 現場のベテランが「邪魔なだけだ」「格好悪い」といっているからじゃないか?
こういう「環境」こそが、不安全行動を引き起こす本当の原因なのです。だとすれば、私たちが取り組むべきは、作業員が特別な意志力や高い意識を持たなくても、自然に安全な行動ができるような『しくみ』、つまり「E(環境)」の改善なのです。
「P」を変えようとする視点は、「なぜできないんだ!」という叱責につながりがち。でも、「E」を変えようとする視点は、「どうすれば、みんなができるようになるだろう?」という、前向きで建設的な問いを生み出します。この視点の転換こそが、本当に効果的で長続きする安全管理への第一歩なのです。