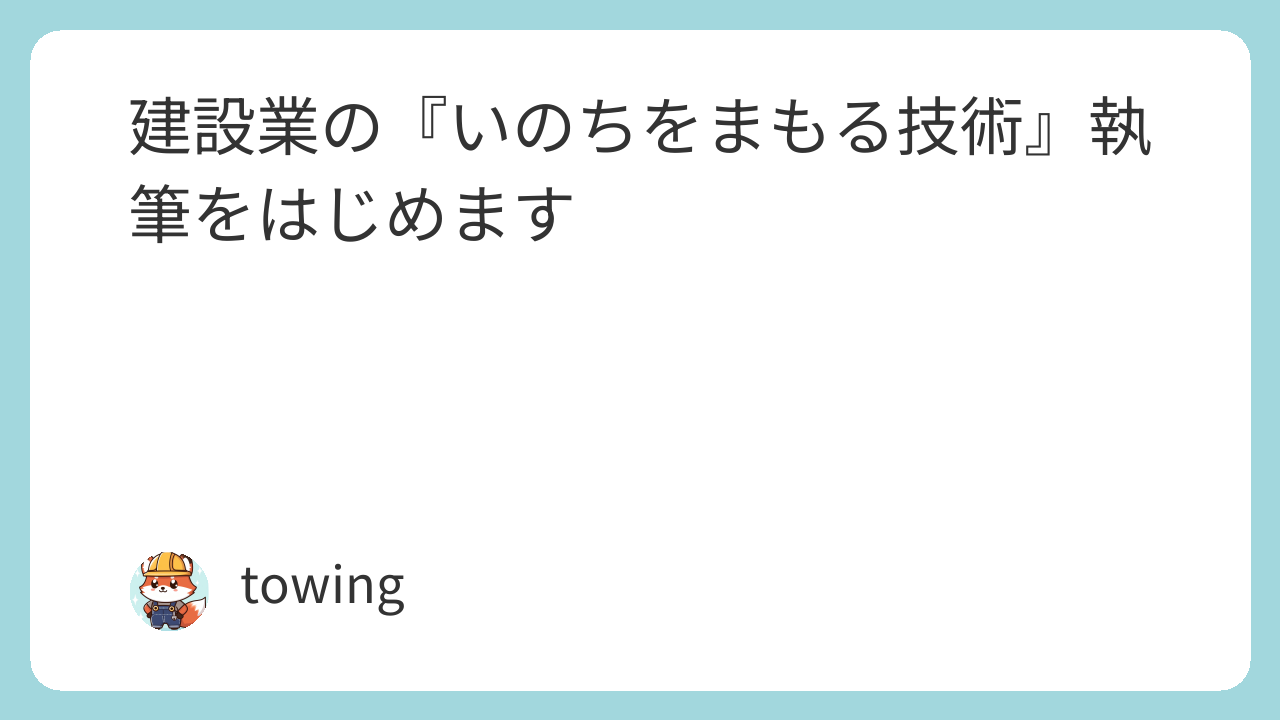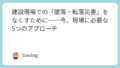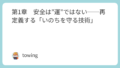執筆の目的──いのちを守る「技術」を見える形に
『いのちを守る技術』というタイトルの本を執筆しようと思っています。次からのブログ記事はそのドラフトです。定期的に見直してリライトすると思います。また、本にするつもりなので記事中で”本書”という言葉を使うと思います。
私たちが「安全」と聞いたとき、まず思い浮かべるのは「注意力」「意識」「責任感」など、”気持ち”の面ではないでしょうか。確かにそれも大切です。しかし、「気をつけていれば守れるいのち」には限界があります。大事なのは、「誰でも、どの現場でも、一定の水準で実行できる”しくみ”を持つこと」です。それこそが、いのちを守る”技術”と定義します。
ここで言う「技術」とは、特殊な技能や高い専門性のことではありません。むしろ、「現場で誰でも使える工夫」「再現性のある知恵」「仕組み化された行動」こそが、いのちを守る本当の”技術”なのです。
ベテランの背中にしかなかったノウハウ。うまくいった現場だけで閉じていた知見。そうした”実践知”を掘り起こし、整理し、言語化して、誰もが使える形にすることが狙いです。
「いのちを守る技術」を12のテーマを4部構成で紹介していきます。
【第1部:基礎となる考え方(第1章〜第4章)】
まず、安全を「技術」として捉え直し、個人の行動を変える「しくみ」と「環境」の重要性を解説します。習慣化や行動デザインの考え方など、本書全体の土台となる知識です。
【第2部:コミュニケーションと記録の技術(第1章〜第3章)】
現場に潜む危険の芽をいかにして早期に発見し、共有するか。「言える化」「記録」「暗黙知の言語化」といった、人と情報の流れをデザインする技術を扱います。
【第3部:人間の”クセ”と戦う技術(第1章〜第2章)】
「自分だけは大丈夫」と思ってしまう確証バイアスや、「去年と同じでいい」という現状維持バイアスなど、事故の引き金となる人間の心理的な”クセ”を理解し、それに対処するマネジメント手法を紹介します。
【第4部:現場を変える実践の技術(第1章〜第4章)】
「見える化」による危険の察知、安全レベルを個人に依存させない「平準化」、チームで支え合う文化づくり、そして、安全の価値を数字で示し、経営層をも動かすための技術まで、より実践的・組織的なアプローチを展開します。
各章は、基本的にどこから読んでいただいても構わないようにします。ご自身の課題意識に最も近い章から手に取っていただくことも可能です。それぞれの章では、「なぜそうなるのか」という理論的背景と、「では、どうすればいいのか」という具体的な実践例を、セットで解説することを心がけました。
また、「現場監督・代理人・安全管理者」だけでなく、「若手職員」「技能実習生の指導者」「経営層」など、さまざまな立場の方が使える内容にできればと思っています。
誰が読んでも、現場での行動を一つでも変えられる。その願いを込めて構成しました。
あなたが守っている
「安全管理は、報われにくい仕事だ」と、あるベテランが言いました。どれだけ安全を維持しても、誰も気づかない。事故が起きなければ、”何も起きなかった”ように見える。
けれども、現場で誰も死ななかった一日には、確かに価値があります。守ったいのちは、気づかれなくても、そこにあります。
そんなあなたのような人に向けて執筆します。一つでも多くの現場で、一人でも多くのいのちが守られるように──”安全”を、実践可能な”技術”として手に取れるようにするために。