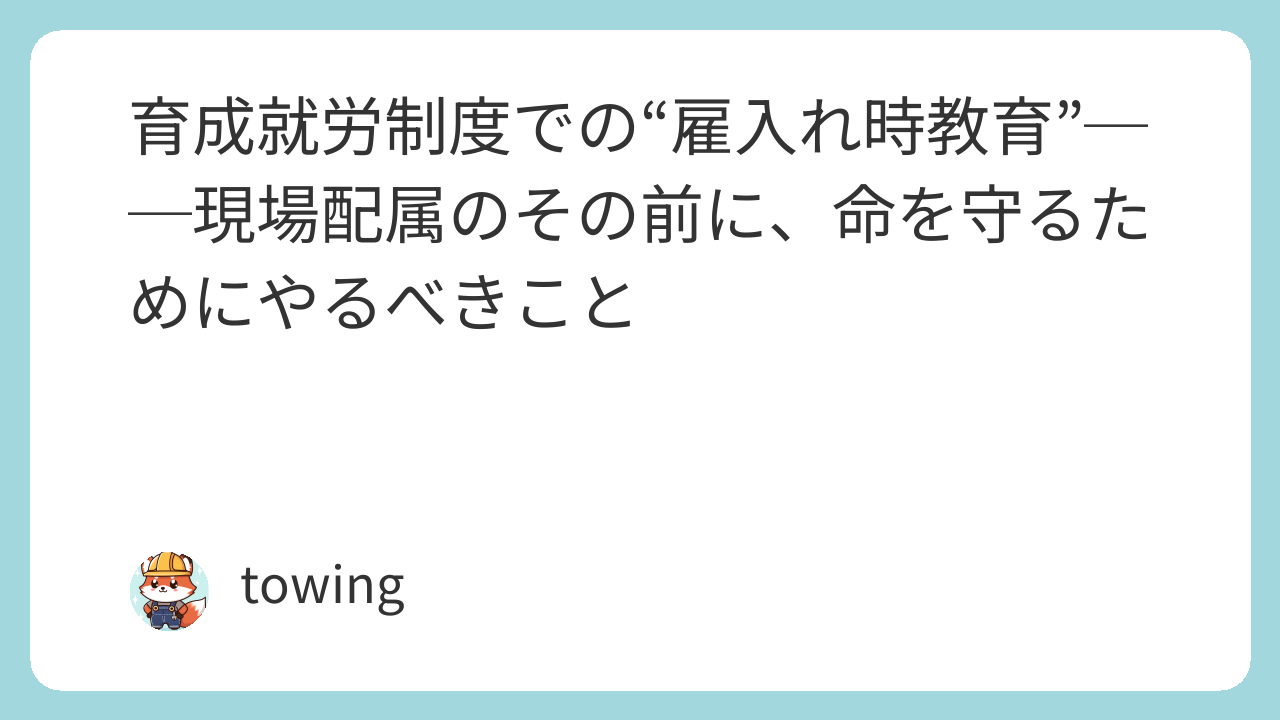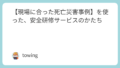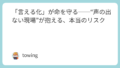はじめに
育成就労制度(2027年施行予定)や現行の技能実習制度では、日本で働く外国人材に対して、**労働安全衛生法に基づく「雇入れ時教育」**の実施が義務づけられています。
特に、言語や文化の違いがある外国人の場合、「教えたつもり」「わかったはず」が命取りになります。
作業を始めるその前に、安全について丁寧に伝える――それが“雇入れ時教育”です。
■ 教育のタイミング──作業を始める前に、必ず実施
雇入れ時教育は、法律上、「雇い入れたとき」=実際に業務を開始する前に行う必要があります。
技能実習生や育成就労者も例外ではありません。
特に災害が多いのは、「入国直後・配属直後の慣れていない時期」。
導入講習が終わり、現場に入る前の段階で、十分な時間を確保して実施することが重要です。
■ 雇入れ時教育の内容──8つの柱でリスクを見える化する
労働安全衛生規則第35条では、雇入れ時教育で扱うべき内容が明確に示されています。
以下に、現場でよくある例を交えて紹介します。
(※内容の説明は前項参照。以下、カリキュラム案にまとめます。)
■ 時間配分6時間の効果的カリキュラム例(モデル)
| 時間帯 | 内容 | 教育形式 |
|---|---|---|
| 9:00〜9:15 | ◆オリエンテーション(教育の目的、流れ) | 講義+対話形式 |
| 9:15〜10:00 | ①作業の危険・有害性の理解 | 写真・動画・実物提示 |
| 10:00〜10:45 | ②保護具・安全装置の使い方 | 実物演習(装着体験) |
| 10:45〜11:30 | ③作業手順と④作業前点検 | 現場シミュレーション |
| 11:30〜12:00 | ◆理解確認①(○×クイズ・振り返り) | 小テスト・グループ対話 |
昼休憩(12:00〜13:00)
| 時間帯 | 内容 | 教育形式 |
|---|---|---|
| 13:00〜13:40 | ⑤職業病の予防(腰痛、眼精疲労、化学物質) | 講義+ストレッチ体験 |
| 13:40〜14:10 | ⑥整理整頓・清掃ルール | 写真+模擬配置演習 |
| 14:10〜14:40 | ⑦応急措置と避難(火災・ケガ・地震) | 実地訓練+避難経路確認 |
| 14:40〜15:10 | ⑧その他の注意点(作業ごとの特記事項など) | 業種別教材+補足説明 |
| 15:10〜15:40 | ◆理解確認②(ロールプレイ・質疑応答) | 実演+対話型テスト |
| 15:40〜16:00 | ◆まとめ/教育記録記入/アンケート | 全体振り返り+記録作成 |
■ 外国人材への教育で気をつけたいこと
言語が違えば、感じ方も違います。
外国人に安全を伝えるときには、次のポイントを押さえることが大切です。
● わかる言葉で、ていねいに
- 平易な日本語を使う
- 専門用語や略語を避け、具体的に説明
- イラスト・動画・実物を使って視覚で伝える
- 通訳や母国語資料も積極的に活用
● 習慣の違いを理解した伝え方
- 「なぜ日本ではこれをやるのか」もセットで説明
- 曖昧な表現は避け、明確・具体的に指示
- 質問しやすい雰囲気をつくる
● 実践を通じた教育を
- 座学だけで終わらせず、実機に触れる実演型の教育
- 危険な作業は、シミュレーション訓練で身につける
■ 教育記録と、特別教育の必要性にも注意
- 雇入れ時教育を行ったら、内容・日時・受講者名を記録し、3年間保存することが義務づけられています。
- フォークリフトや高所作業など、特定の危険作業には別途「特別教育」が必要です。
- 作業内容が変わった場合も、再教育が求められます。
■ 安全教育は、“命の準備運動”
安全教育は「作業前の形式的な手続き」ではありません。
それは、命を守る準備運動であり、現場で働くすべての人にとっての“初めての防具”です。
とくに、育成就労や技能実習といった「これから育っていく人たち」にこそ、最初の一歩であるこの教育を、手を抜かず、心を込めて届けたい。
OFFICE SAFE WORKでは、こうした雇入れ時教育の支援も考えています。
教材づくりから記録の管理、講師の派遣まで、「やった」で終わらせず「伝わった」までご一緒に考えます。