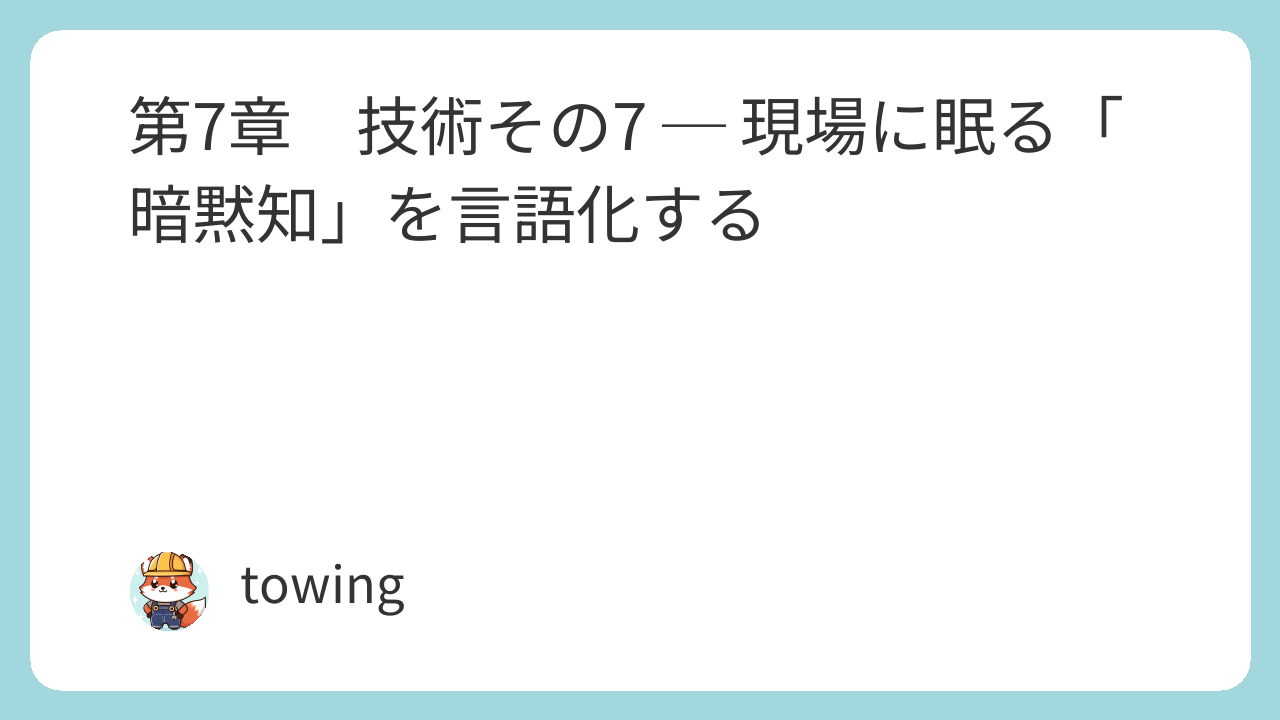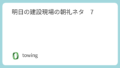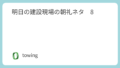ベテランの”無意識の判断”をどう伝えるか
「まあ、長年の勘だな」
「なんとなく、嫌な予感がしたんだよ」
「いつもと音が違う気がしてね」
あなたの現場にも、こんな言葉を口にするベテラン職人がいらっしゃるのではないでしょうか。クレーンの操作、足場の組み立て、地山の掘削─彼らの卓越した技術や危険を察知する能力は、マニュアルに書かれた手順をなぞるだけでは決してたどり着けない領域にあります。一つひとつの作業を驚くほどスムーズに、そして何よりも安全にこなしていく姿には、言葉では簡単には説明できない経験則や身体感覚、つまり「暗黙知」が息づいています。
この暗黙知こそが、現場の安全を最後の最後で支える、いわば「生きたマニュアル」です。しかし、それは同時に、これほど脆く、失われやすい知識もありません。ベテラン自身でさえ、なぜその判断を下したのか、なぜその手順を選んだのかを論理的に説明できないことがほとんどです。なぜならばそれは、思考を経由しない「無意識の判断」であり、身体に染みついた感覚だからです。
ここに、技術継承への大きな壁が立ちはだかっています。若手や経験の浅い作業員は、具体的な指示や根拠がなければ思うように動くことができません。「いつもと違う感じ」と言われても、何がどう違うのか分からなければ真似のしようがないのです。結果として 「見て覚えろ」 「体で覚えろ」 という旧来の指導法に頼らざるを得なくなり、若手は危険の本質を理解できないまま、表面的な作業を真似するだけになってしまいます。そして、ベテランが現場を去ると同時に、その貴重な安全技術もまた、永遠に失われてしまうのです。
この属人化された「職人の勘」を組織全体の共有財産である「技術」へと昇華させること。それが本章のテーマである「暗黙知の言語化(形式知化)」です。これは単なる技術継承の問題ではありません。現場にいる誰もが、ベテランと同じ「危険を見抜く目」を持つための、極めて重要な安全活動です。
では、どうすれば言葉にならない無意識の判断を誰もが理解できる形に変換できるのでしょうか。その第一歩は、丁寧な「対話」と「観察」から始まります。
重要なのは、結果ではなくプロセスを問うことです。「なぜ、そうしたのですか?」という漠然とした問いでは、「なんとなく」という答えしか返ってこないでしょう。そうではなく、彼らが判断を下した瞬間に五感で何を感じ取っていたのかを具体的に掘り下げていきます。
- 視覚について:
「その時、何が見えていましたか?」 「どこに一番注意を払っていましたか?」 「いつもと比べて、物の色や形、配置に違いはありましたか?」 - 聴覚について:
「どんな音が聞こえましたか?」 「機械の音はいつもと同じでしたか?」 「異音はしませんでしたか?」 - 触覚・嗅覚について:
「地面の揺れや機械の振動はどうでしたか?」 「何か変わった匂いはしませんでしたか?」
こうした具体的な質問を投げかけることで、ベテランの頭の中で無意識に行われていた情報処理のプロセスを一つひとつ解き明かしていくことができます。「クレーンのモーター音が、いつもより少し甲高い気がしました。これは過負荷の兆候かもしれないので、一度荷を降ろして確認したんです」といった具体的なエピソードを引き出せれば、それはもう「勘」ではなく、立派な「判断基準」となります。
また、ベテランの作業に同行し、その行動を逐一観察する「シャドーイング」も極めて有効です。作業前、彼はどこを見ているでしょうか。どんな準備をしているでしょうか。手順を少し変えたとしたら、それはなぜでしょうか。その一つひとつの所作に、安全を確保するためのヒントが隠されています。観察によって得られた気づきを元に、改めてインタビューを行うことで、本人すら意識していなかった暗黙知が浮かび上がってきます。