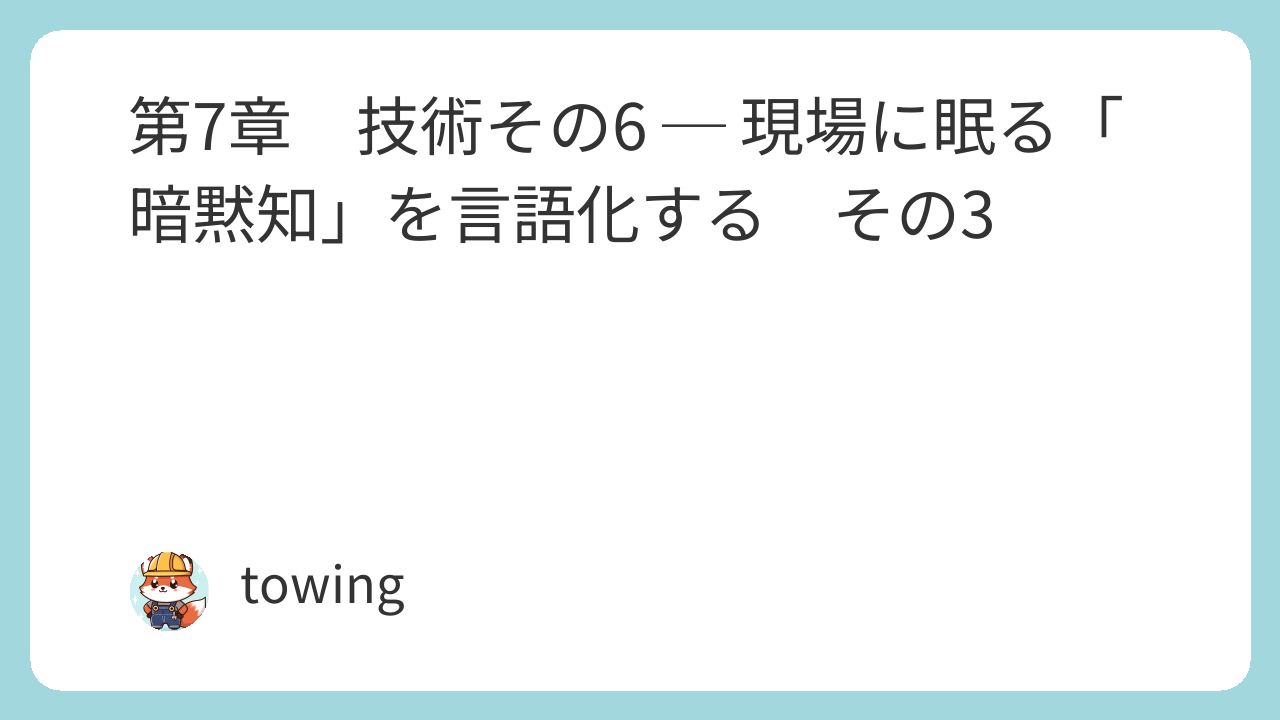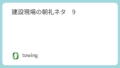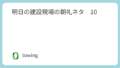動画、図解、写真──見える化の実践例
対話と観察によって、ベテランの暗黙知をある程度「言葉」にすることができました。しかし、現場の技術には、言葉だけではどうしても伝えきれないニュアンスや身体感覚が伴うものがあります。
例えば 「工具はこれくらいの角度で」 「腰をこう使って」「これくらいの力加減で」といった感覚は、いくら言葉を尽くしても正確に伝えることは困難です。こうした言語化の限界を超える強力な武器が「見える化」の技術です。動画、図解、写真を駆使することで、暗黙知を直感的かつ具体的に共有することが可能になります。
1. 動画の活用:「動き」と「視点」を伝える
動画は、作業の一連の流れや身体の使い方を伝えるのに最適なツールです。
- お手本動画とNG動画の比較:
安全な作業手順を撮影した「お手本動画」はもちろん有効ですが、それだけでは不十分です。ありがちな失敗例や危険な手順を再現した「NG動画」とセットで見せることで、なぜその手順が推奨されるのか、どこに危険が潜んでいるのかを学習者は深く理解ができます。「正しい足場の組み方」の動画と「手すりを一部省略した不安全な足場」の動画を比較すれば、その重要性は一目瞭然です。 - 視線カメラ(ウェアラブルカメラ)の活用:
ベテランのヘルメットに小型カメラを取り付け、作業中の「視点」を録画する手法は、暗黙知を掘り起こす上で絶大な効果を発揮します。玉掛け作業中、ベテランは荷物だけでなく、ワイヤーの状態、クレーンの動き、周囲の人員配置など、常に視線を動かして広範囲の情報を収集しています。この「視線の動き」こそ、安全を確保するための無意識の判断そのものです。若手はこの動画を見ることで、自分がどこを見るべきだったのか、何を見落としていたのかを客観的に知ることができます。動画に「ここでフックの状態を確認」「ここで退避経路を最終確認」といった解説テロップを加えれば、極めて質の高い教材となります。 - スロー再生と解説:
一瞬の判断や微妙な身体の動きを捉えるには、スロー再生が有効です。例えば重量物を持ち上げる際の膝の使い方や、溶接トーチの微妙な角度の変化など、通常速度では見過ごしてしまうような重要なポイントをスローで再生し、なぜその動きが必要なのかを解説付きで見せることで、学習効果は飛躍的に高まります。
2. 図解の活用:「勘所」をピンポイントで示す
複雑な構造や作業の「勘所」をシンプルに伝えるには、図解が効果的です。
- 力の向きや角度の図示:
「このボルトは、まっすぐではなく少し斜め上に力を加えながら締めると、うまくはまります」といったコツは、言葉で説明するよりも、矢印などを使った簡単なイラストで示す方がはるかに分かりやすいものです。工具の正しい持ち方、身体の軸の保ち方など、写真では分かりにくいポイントを図で補足することで、理解を助けます。 - 危険予知トレーニング(KYT)シートへの応用:
現場の状況をイラストに描き、「この中に潜む危険を指摘してください」と問いかけるKYTは、まさに暗黙知を共有する格好の場です。ベテランは、若手が気づかないような思わぬ危険(例:資材の仮置きの仕方、天候の変化による影響)を指摘するでしょう。なぜそこが危険だと判断したのか、その根拠を全員で議論することで、多様な視点からの危険感受性を養うことができます。
3. 写真の活用:「OK」と「NG」を瞬時に伝える
写真は、特定の状態が安全か不安全かを一目で判断させる力を持っています。
- OK/NG事例の比較展示:
同じ場所の「正しい単管バリケードの設置方法(OK写真)」と「ウエイトが乗っていない、間隔が広すぎるなどの不安全な設置方法(NG写真)」を並べて掲示します。あるいは、違う場所の「整理整頓された資材置き場(OK写真)」と「乱雑に置かれた資材置き場(NG写真)」を比較します。このように良し悪しの状態をビジュアルで対比させることで、誰もが正しい状態を瞬時に理解し、自分の現場と比較することができます。休憩所や朝礼のスペースに掲示しておくだけで、日々の意識付けにつながります。 - ヒヤリ・ハットの再現写真:
実際に起きたヒヤリ・ハットの状況を可能な範囲で写真に撮って記録・共有します。文章だけの報告書よりも写真がある方が、状況の深刻さや危険性がリアルに伝わります。「なぜこうなったのか」 「どうすれば防げたのか」 を議論する際の、具体的で説得力のある材料となります。
これらの「見える化」ツールは、単独で使うのではなく、組み合わせて活用することでさらに効果が高まります。動画で全体の流れを掴み、図解でポイントを理解し、写真でOK/NGの状態を記憶する。このように多角的なアプローチで暗黙知を形式知へと変換していくのです。