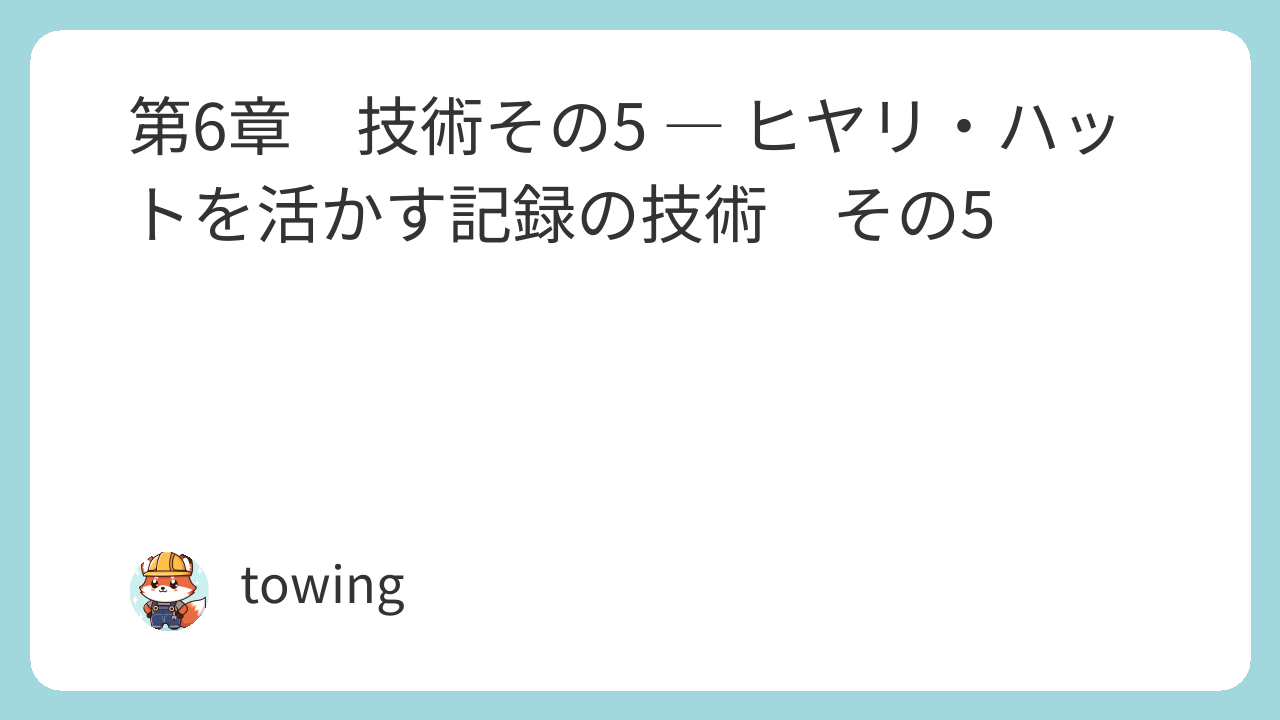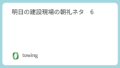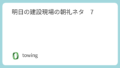パターン化と共有の技術
さて、現場から書きたくなる『しくみ』によって、質の高いヒヤリ・ハット情報が集まり始めました。しかし、ここで満足してはいけません。集められた情報は、ただファイリングしておくだけでは「宝の持ち腐れ」です。それを分析し、現場の誰もが理解できる形に加工して共有する「技術」があって、初めて価値が生まれます。
そのための具体的なステップが、「パターン化」と「共有」です。
1.パターン化で「災害の傾向」を見抜く
一つひとつのヒヤリ・ハットは、点にすぎません。しかし、それらを分析し、分類(パターン化)することで、点と点がつながり、現場に潜む「災害の傾向」や「弱点」という線や面が見えてきます。
- 情報をタグ付けする
集まった報告書をただ漫然と眺めるのではなく、いくつかの切り口で「タグ付け」していきます。 - 災害の型:
墜落・転落、飛来・落下、はさまれ・巻き込まれ、転倒、感電、切れ・こすれ… - 発生場所:
足場、開口部周辺、資材置き場、階段、バックホウ周辺… - 時間帯:
朝礼直後、昼休み明け、残業時間帯、雨天時、強風時… - 作業内容:
玉掛け作業、高所作業、溶接作業、型枠解体… - 作業経験
職種としての経験年数、現場入場日数…と - 原因の分類:
不安全な行動(保護具不使用、手順不遵守など)、不安全な状態(機械の不備、整理整頓不良、不十分な照明など)
最初は手作業でも構いません。エクセルなどで一覧表を作り、各事例にこれらのタグを付けていくだけで、驚くほど多くのことが見えてきます。
「どうも我々の現場は、雨上がりの午後に、足場での転倒系のヒヤリ・ハットが集中しているな…」
「若手作業員から、玉掛けワイヤーの点検に関するヒヤリ・ハットが多く上がってくる。もしかして、点検基準の教育が不足しているのではないか?」
このように、経験や勘だけに頼っていた危険の傾向が、データとして客観的に可視化されるのです。これが「パターン化」の力です。
- 「なぜなぜ分析」で深掘りする
特定のパターンが見えてきたら、次に「なぜ、そのヒヤリ・ハットが起きたのか?」を深掘りします。ここで有効なのが、ご存知「なぜなぜ分析」です。ただし、ここでも注意すべきは、原因を個人の資質(不注意、確認不足など)で止めないことです。 - 悪い例:
なぜ転びそうになった? → 足元をよく見ていなかったから(個人の問題で終了) - 良い例:
なぜ転びそうになった? → 通路に資材が置いてあったから。
なぜ資材が置いてあった? → 決められた置き場所がいっぱいだったから。
なぜ置き場所がいっぱいだった? → 次の工程の資材が前倒しで搬入されたから。
なぜ前倒しで搬入された? → 現場間の連絡調整が不十分だったから。
なぜ連絡調整が不十分だった? → 週間工程会議で、資材搬入計画まで共有されていなかったから。
ここまで深掘りすれば、対策は「足元に注意しろ!」という注意喚起ではなく、「週間工程会議で資材搬入計画を共有するルールを作る」という具体的な『しくみ』の改善に行き着きます。
2.共有で「集合知」を醸成する
パターン化によって見えてきた現場の弱点と、それに対する『しくみ』仕組みの改善策は、現場の全員に共有されて初めて意味を持ちます。この「共有」のプロセスにも、効果を高める技術があります。
- 朝礼での1分間共有:
毎日の朝礼で、一件だけヒヤリ・ハット事例を取り上げます。長々と説明する必要はありません。「昨日、A棟の3階で、床の濡れによる転倒のヒヤリがありました。雨の日は特に滑りやすいので、皆さん注意してください。対策として、巡回時にモップがけを追加します」といったように、事実と対策を簡潔に伝えます。これを続けることで、危険に対する感受性が現場全体で高まっていきます。 - 「ヒヤリ・ハットマップ」の作成:
現場の図面を大きく印刷し、ヒヤリ・ハットが発生した場所にシールを貼っていく方法です。どこで、どのような危険が潜んでいるかが一目瞭然になります。「このカーブは、見通しが悪くて車両との接触ヒヤリが多いな」「この開口部周りは、落下系のヒヤリが集中している」といったことが視覚的に理解でき、自然と危険な場所を意識するようになります。 - 写真とイラストの活用:
文字だけの報告書よりも、写真や簡単なイラストを使った方が、記憶に残りやすく、言葉の壁も超えやすくなります。特に、外国人技能実習生などが多い現場では極めて有効です。危険な状況を再現した写真に、良い例(○)と悪い例(×)を並べて掲示するだけでも、優れた教育資料になります。 - 「ファインプレー報告」も同時に集める:
ヒヤリ・ハット、つまり「危なかったこと」だけでなく、「危険を防いだ好プレー」も積極的に集めて共有します。「○○さんが、資材の不安定な積み方を発見し、すぐに直してくれました」「△△さんが、声をかけ合って安全な荷下ろしを実践していました」といったポジティブな情報が共有されることで、現場の雰囲気が明るくなり、安全行動が賞賛される文化が育ちます。
これらの技術は、特別な才能や高価なツールを必要としません。必要なのは、ヒヤリ・ハットという情報の価値を信じ、それを活かすための少しの工夫と手間を惜しまない姿勢です。
集め、分析し、共有する。このサイクルを回し続けることで、ヒヤリ・ハット活動は「やらされ仕事」から「自分たちの命を自分たちで守るための創造的な活動」へと進化していきます。それは、未来に起こるはずだったかもしれない重大な災害を静かに、しかし着実に、防ぎ続けることになります。
守った命は、誰にも気づかれることはありません。しかし、その目に見えない成果こそが、この技術を実践するあなたにとっての、最高の報酬となるはずです。