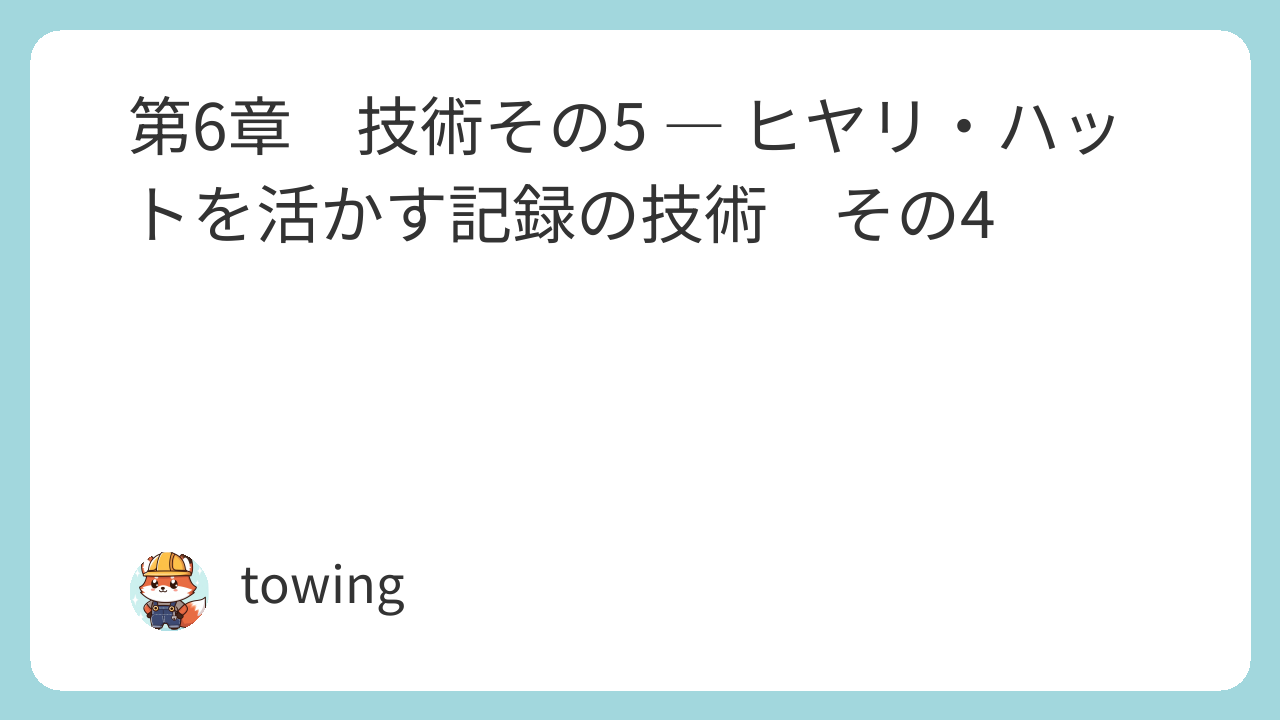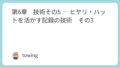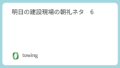記録を「指導」につなげない勇気
ヒヤリ・ハット報告が形骸化するもう一つの大きな原因は、報告が個人の「評価」や「指導」に直結してしまうことです。
「またお前か。注意力が足りないんじゃないか?」
「こんな基本的なこと、なぜ気づかなかったんだ」
もし報告書を提出した結果、このような言葉をかけられたとしたら、誰が正直に自分の失敗を打ち明けようと思うでしょうか。多くの人は口を閉ざし、次に同じような経験をしても “見なかったこと” “なかったこと” にしてしまうでしょう。
これこそが、危険の芽が育つ温床です。
ヒヤリ・ハットは、個人の不注意や能力不足を責めるための材料ではありません。それは、
「誰がその状況に置かれても、同じようなミスを犯す可能性があったのではないか?」
という視点から、現場に潜むシステム上の欠陥、つまり『しくみ』の問題点を発見するための貴重なデータなのです。
航空業界には、「ASRS(Aviation Safety Reporting System)」という優れたインシデント報告制度があります。これは、パイロットや管制官などが自発的にミスや危険な状況を報告するシステムですが、最大の特徴は「非懲罰的」であることです。故意の違反でない限り、報告したことで罰せられることはありません。その代わり、集められた膨大なデータは徹底的に分析され、航空業界全体の安全対策や訓練プログラムの改善に活かされています。
なぜ彼らはそうするのでしょうか。それは、
人間は誰でもエラーを犯す不完全な存在である
という事実を深く理解しているからです。だからこそ、個人の責任を追及するのではなく、エラーを誘発した状況や背景(=『しくみ』)を改善することに全力を注ぎます。
建設現場のリーダーにも、この「記録を指導につなげない勇気」が求められます。
報告書に書かれた作業員の名前を見て、「指導」の二文字が頭をよぎるのをぐっとこらえる勇気。報告された内容が、たとえ基本的な安全ルール違反であったとしても、「なぜ、彼はルールを守れなかった(守らなかった)のだろう?」と、その背景にある要因に目を向ける知性。
- もしかしたら、工期が迫っていて焦っていたのかもしれない
- もしかしたら、必要な機材が別の場所で使われていて、手元になかったのかもしれない
- もしかしたら、その日の体調が悪かったのかもしれない
- もしかしたら、そもそもそのルールの必要性が、彼は納得していなかったのかもしれない
このように、「誰が(Who)」ではなく「なぜ(Why)」を問い続けること。そして、その問いの先に個人の資質の問題ではなく、環境、手順、道具、コミュニケーション、教育といった『しくみ』の問題を見つけ出すこと。これが、ヒヤリ・ハットを本当に活かすための核となる考え方です。
もちろん、意図的なルール無視や危険行為を容認しろと言っているのではありません。しかし、その判断は慎重に行うべきです。ほとんどのヒヤリ・ハットは、真面目に仕事に取り組む中で、様々な要因が不運にも重なった結果として発生します。
リーダーが 「報告者を断固として守る」 「原因究明を個人攻撃の場にしない」 という姿勢を明確に示し、行動で示し続けること。その「勇気」こそが、現場に心理的安全性をもたらし、隠された危険をあぶり出すための土壌を作ることにつながります。