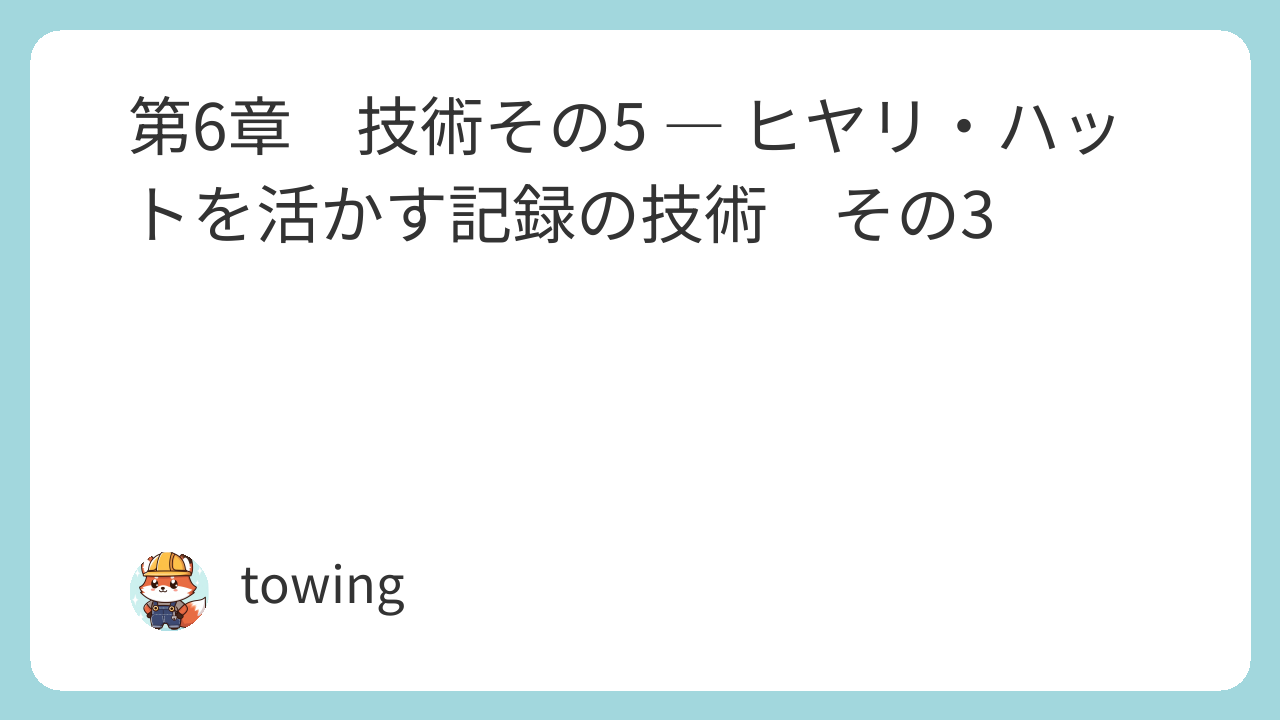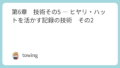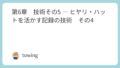“書いたら損をする”から“書いたら得をする”へ
まず、報告のハードルを徹底的に下げることが重要です。完璧な文章である必要など全くありません。むしろ、書式にこだわりすぎることが、報告の心理的障壁を高めてしまいます。
- フォーマットの簡素化:
紙一枚にびっしりと書かせるのではなく、スマホアプリや現場事務所のホワイトボードに「いつ・どこで・何が・どうなりそうだったか」を箇条書きにするだけでも十分です。写真や簡単なイラストを添える方式も有効です。重要なのは文章力ではなく、事実が伝わることです。 - 匿名性の担保:
特に導入初期は、誰が報告したかわからないようにする工夫も有効です。これは「責任逃れ」を推奨しているのではありません。「犯人探し」をしない、というリーダーからの明確なメッセージです。まずはどんな些細な情報でも出てくる環境をつくることが最優先です。 - 報告へのポジティブな反応:
これが最も重要かもしれません。ヒヤリ・ハットが報告されたら、リーダーはまず「ありがとう。貴重な情報を教えてくれて、本当に助かります」と感謝を伝えます。そして、その情報がどのように現場の改善に活かされたかを朝礼や掲示板で必ずフィードバックするのです。
「あの時、勇気を出して報告してくれたおかげで、あそこの段差にステップが設置されました」
「○○さんが気づいてくれたおかげで、あそこの照明が明るくなりました」
このように、自分の小さな行動が具体的な改善につながり、仲間からの感謝や尊敬という「報酬」を得られるとわかれば、「次も何か気づいたら報告しよう」という気持ちが自然に芽生えてきます。ヒヤリ・ハット報告を
罰ゲームではなく、ヒーローになるための機会
という認識に変えるのです。
“書かせる”文化は、管理者が楽をするための仕組みです。”書きたくなる”文化は、現場の全員で安全をつくるための『しくみ』です。手間はかかりますが、そのリターンは計り知れません。