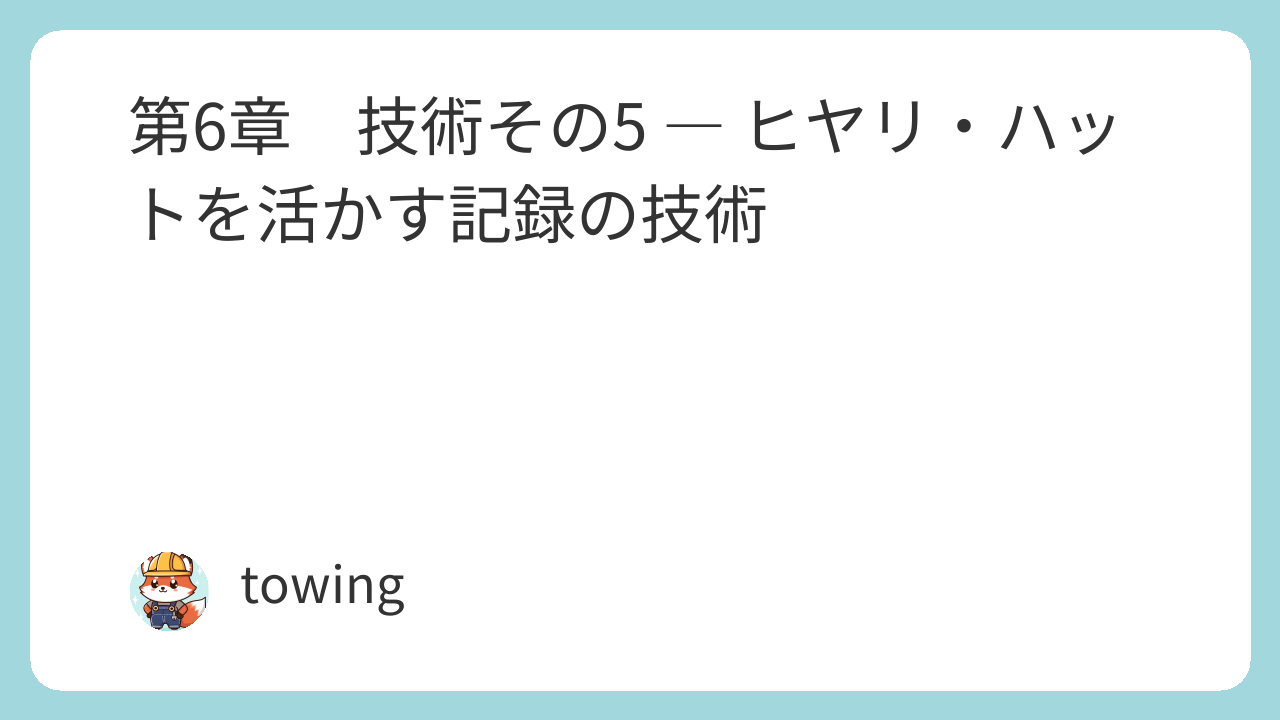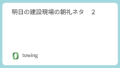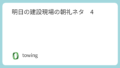形だけの報告をやめて、書きたくなる『しくみ』へ
「ヒヤリ・ハット報告、きちんと集まっていますか?」
もしあなたが現場の安全管理者やリーダーでしたら、この問いに「はい、もちろんです」と胸を張って答えられるかもしれません。しかし、その集まった報告書の内容はどうでしょうか。
「足場から物が落ちそうになりましたが、拾ったので問題ありませんでした」
「開口部でつまずきそうになりましたが、気をつけて歩きました」
「ヘルメットを被り忘れるところでしたが、思い出したので被りました」
報告を求めると提出される、当たり障りのない、まるで「反省文」のような報告書の山。提出ノルマとして課せられ、形骸化した活動になっているためではないでしょうか。本来、ヒヤリ・ハット活動は、重大災害という氷山の「海面下にある巨大な部分」を可視化し、未来の事故を未然に防ぐための、現場でできる最も効果的な安全活動のはずです。
しかし、多くの現場でその活動が十分に活かされていません。それは、担当者の熱意や作業員の意識が低いからではありません。ヒヤリ・ハットという貴重な情報を「活かす技術」と、そのための『しくみ』が不足しているからです。
本章では、形骸化した活動から脱却し、ヒヤリ・ハットを「未来の命を守るための生きた情報源」に変えるための具体的な技術と思想について解説いたします。カギとなるのは、「書かせる」から「書きたくなる」への転換、そして、報告された情報を「個人指導」ではなく“『しくみ』改善”に活かす勇気です。