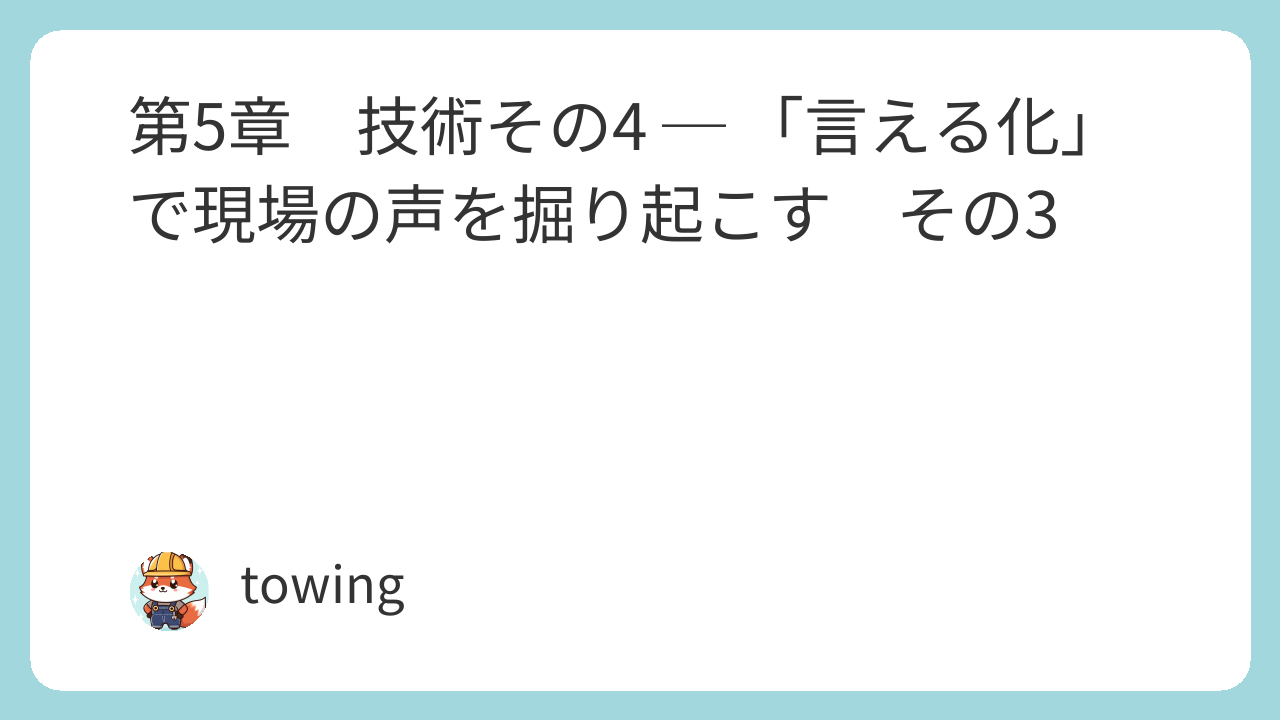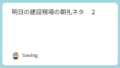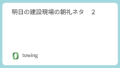『しくみ』で言える空気をつくる
「もっと積極的に意見を言え」
「気づいたことは何でも報告しろ」
リーダーがいくら言葉でこう叫んでも、現場の空気は変わりません。チーム全員の心理的な壁を取り払い、「言える化」を実現するためには、個人の意識改革に期待するのではなく、誰もが自然と声を上げられる客観的な『しくみ』をデザインする必要があります。
ここでは、明日からでも始められる具体的な『しくみ』のアイデアをいくつか紹介します。これらを組み合わせ、ご自身の現場に合わせてカスタマイズすることで、「言える」空気は着実に醸成されていきます。
1. 「聞き出す」ための場を意図的につくる
ただ 「何かあるか?」 と漠然と問いかけるだけでは、声は出てきません。聞き手側が、話しやすい「お膳立て」をする必要があります。
- 少人数でのリスクアセスメントミーティング:
朝礼後などに、5〜6人のチームに分かれ、その日の作業に潜む危険について5分だけでも話し合う場を設けます。「今日の作業で、自分が一番ヒヤリとしそうなことは何だろう?」といった具体的な問いかけから始めると、意見が出やすくなります。重要なのは、職長やリーダーが一方的に話すのではなく、若手や経験の浅い作業員から順番に発言を促すなど、全員が参加できるルールを設けることです。 - 「グッド&ニュー」や「グッジョブ報告」の導入:
いきなり危険の指摘から入ると、どうしても場の空気が重くなります。そこで、ミーティングの冒頭で「昨日から今日にかけてあった“良かったこと”(Good)や“新しい発見”(New)」を一人ずつ発表する時間を設けます。安全に関する内容でなくても構いません。「〇〇さんの挨拶が気持ちよかった」「新しい工具が使いやすかった」といったポジティブな発言でウォーミングアップすることで、その後の意見交換が活発になります。安全行動を褒め合う「グッジョブ報告」も、相互承認の文化を育み、心理的安全性を高める上で非常に有効です。
2. 「匿名性」というセーフティネットを用意する
どうしても対面では言いにくい、という声は必ず存在します。そうした声を拾い上げるために、匿名で意見を表明できる方法を設けることは、効果的なセーフティネットとなります。
- 物理的な意見箱(目安箱)の設置:
古典的な方法ですが、今なお有効です。作業員の休憩所など、人目を気にせず投函できる場所に設置します。用紙と筆記用具を常に備え付けておくことが大切です。 - デジタル意見箱の活用:
現場事務所に掲示したQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、匿名で意見や写真を送れるフォームを用意するのも良いでしょう。Googleフォームなどの無料ツールで簡単に作成できます。これなら、帰宅後のリラックスした状態で意見を送ることも可能です。
ここで最も重要なのは、投書された意見へのフィードバックを徹底することです。投書された意見は、掲示板や朝礼などで
「〇〇という意見をいただきました」
と必ず公開し、
「これに対して、〇〇という対策を実施します」
「〇〇という理由で、今回はすぐの対応が難しいですが、継続して検討します」
といった形で、対応状況を全員に「見える化」します。フィードバックのない意見箱は、すぐに誰からも信用されなくなり、単なる“箱”と化してしまいます。「自分の声が、きちんと届き、現場を変える力になる」という実感こそが、この『しくみ』を動かすエンジンとなります。
3. 「報告してくれて、ありがとう」を文化にする
ヒヤリ・ハットやインシデントの報告は、災害を未然に防いだ「ファインプレー」です。しかし、多くの現場では、報告者が「何かやらかした人」 という目で見られがちです。この認識を180度転換させる必要があります。
- 「非難しない文化」の宣言と実践:
まず、経営層や現場のトップが、「いかなる報告も、報告者を非難・処罰するためには使わない。すべての報告は、再発防止という未来のために活用する」という「非難しない原則」を明確な言葉で宣言し、あらゆる場面で繰り返し伝えることが重要です。そして、実際に報告が上がってきた際に、決して報告者を責めることなく、「よく報告してくれました。ありがとう」と感謝の意を表明し、その姿勢を見せ続けることが、何よりも強いメッセージとなります。 - 報告を「評価」する制度:
優れたヒヤリ・ハット報告や改善提案に対して、「月間ファインプレー賞」として表彰したり、少額の報奨金やインセンティブを与えたりする制度も有効です。報告が「評価されるべき良い行動」であると位置づけることで、報告への心理的ハードルは劇的に下がります。
4. 「聞き役」と「つなぎ役」を任命する
職長や上司といった“縦のライン”だけでは、拾いきれない声があります。同僚や後輩といった“横のライン”に、相談しやすい「聞き役」を配置することも有効なアプローチです。
- 安全サポーター制度:
各チームに、若手や中堅の中から「安全サポーター」や「安全キーパーソン」といった役割を任命します。彼らの役割は、何かを決定したり指示したりすることではありません。仲間からの「ちょっと気になるんだけど…」という小さな疑問や気づきに耳を傾け、それを職長や安全管理者に「つなぐ」ことです。職長には言いにくいことでも、年齢の近いサポーターになら話せる、というケースは少なくありません。
これらの『しくみ』は、単独で機能するものではなく、相互に関連し合って初めて大きな効果を発揮します。重要なのは、完璧な『しくみ』を最初から目指すのではなく、まずは一つでも試してみること。そして、現場の反応を見ながら、自分たちの職場に合った形に改善し続けていくことです。
「言える化」は、コミュニケーションの問題であると同時に、現場の安全を根底から支えるインフラ整備です。小さな声に耳を傾け、それを拾い上げる『しくみ』を構築すること。それこそが、未来の誰かの尊い命を救う、最も着実な一歩となるはずです。