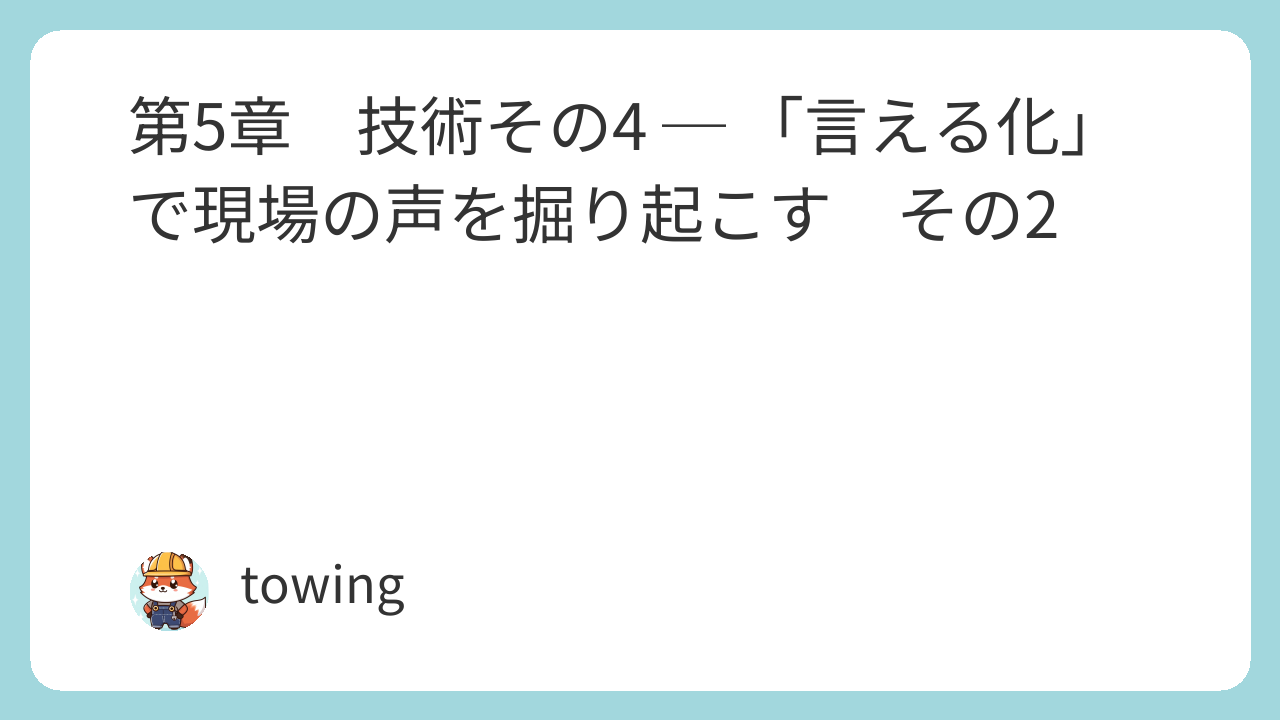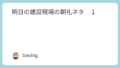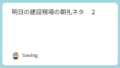声が出ない現場には、危険が育つ
声が出ない、あるいは、出させない現場は、災害という“病”にとって非常に進行しやすい環境です。なぜなら、
「早期発見・早期治療」
の機会が、そこには存在しないからです。
ドイツ出身の政治学者エリザベート・ノエレ・ノイマンによって提唱された「沈黙の螺旋(Spiral of Silence)」という理論があります。これは、自分の意見が周囲の大多数と異なると感じたとき、孤立を恐れるあまり、その意見を表明することにためらい、結果として異なる意見がますます表明されにくくなる、という現象を説明したものです。
これを安全管理に置き換えて考えてみましょう。
ある作業員が、慣習的に行われている作業手順に「危ないのではないか」という懸念を抱いたとします。しかし、周りの誰もが、その手順に疑問を持たず、当たり前のように作業をこなしています。上司も、長年そのやり方でやってきたベテランです。
「ここで口を挟んだら、和をみだすだけではないか」
「自分だけが知らない、何か理由があるのかもしれない」
そう考えた作業員は、口をつぐみます。彼の沈黙は、周囲に「このやり方で問題ない」という暗黙のメッセージとして伝わります。そして、同じような懸念を感じていたかもしれない別の作業員も、「誰も何も言わないのだから、大丈夫なのだろう」と考え、やはり沈黙を選びます。
このようにして、「危険かもしれない」という個々の小さな懸念は、集団の同調圧力によってかき消され、「この現場の作業のやり方は、これで問題ない」という、誤った“安全神話”が形成されていきます。この「沈黙の螺旋」が回り始めると、もはや誰も危険を指摘できなくなり、現場は組織ぐるみで危険な状態を容認・維持してしまうのです。
声が出ない現場には、いくつかの共通した特徴が見られます。
- 一方通行のコミュニケーション:
上司からの指示は絶対で、部下からの意見や質問が歓迎されない。朝礼やミーティングが、単なる指示伝達の場になっている。 - 懲罰的な文化:
ミスや失敗を犯した者に対して、原因究明や再発防止よりも、叱責やペナルティを優先する。「報告したら怒られる」という空気が、問題を隠蔽する土壌となる。 - 過度な効率至上主義:
「忙しい」「時間がない」が口癖で、作業員が立ち止まって考えたり、話し合ったりする時間的・精神的な余裕がない。少しでも作業を止めると、「何をやっているんだ」という無言の圧力がかかる。 - 固定化された人間関係と慣習:
「昔からこうやっている」 「あの人が言うことだから間違いない」 という思考停止が蔓延し、新しい視点や変化を拒絶する。
あなたの現場は、どうでしょうか。もし、これらの特徴に一つでも思い当たる節があれば、それは災害という“病”がひそかに進行しているサインかもしれません。声が出ない現場は、いわば菌の “培養室”です。危険という名の病原菌が、誰にも邪魔されることなく、着実に育つ環境を提供してしまっているのです。