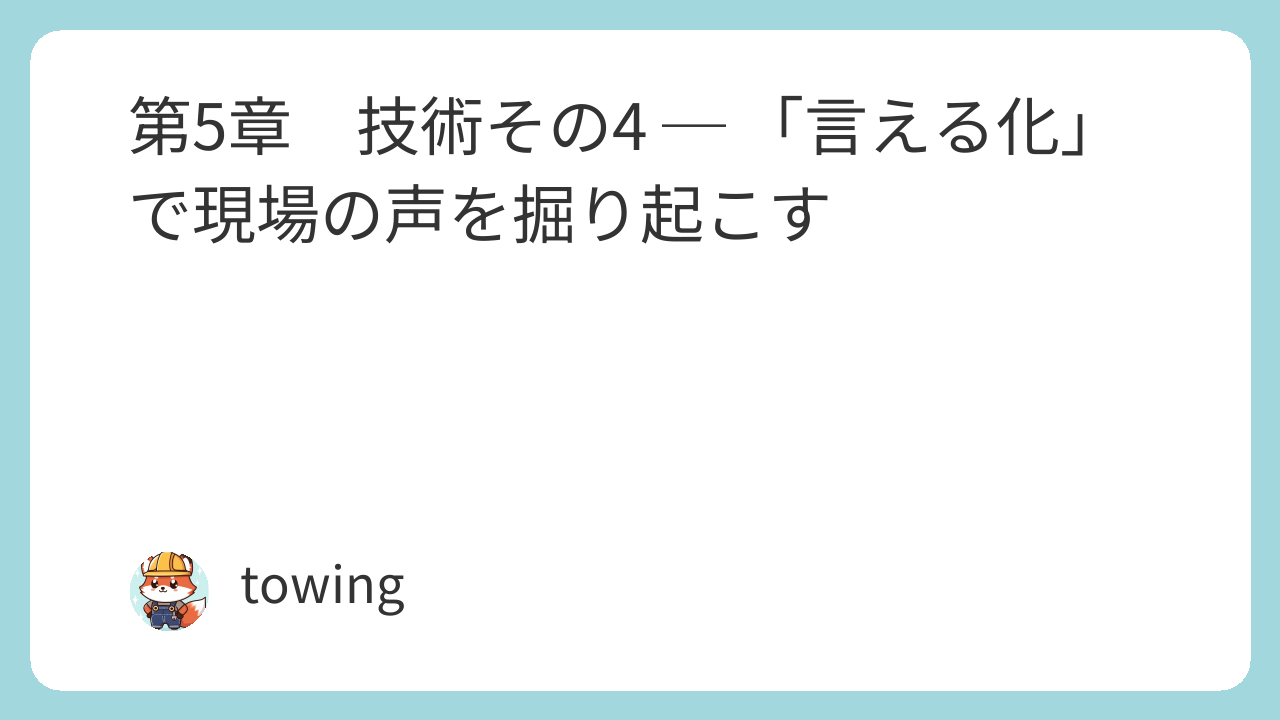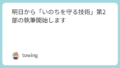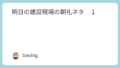危険は”違和感”のうちに止める
「何か、おかしいな……」
重大な労働災害の報告書を詳しく調べていくと、その事故が起きる数日前、あるいは数時間前に、現場の誰かが感じていた、この小さな「違和感」に辿り着くことが少なくありません。
「あの機械、いつもと違う音がする気がする」
「この足場、少し不安定じゃないか?」
「今日の〇〇さん、なんだか集中できていないように見える」
こうした「違和感」は、例えると、災害という“病”の初期症状かもしれません。ところが、多くの場合、この貴重なシグナルは誰にも伝えられることなく、現場の喧騒の中にかき消えてしまいます。なぜでしょうか。
「こんなことを言って、心配症だと思われたら恥ずかしい」
「ベテランの職人さんが気がついていないわけがない」
「みんな忙しいのに、流れを止めてまで言うほどのことではないのではないか」
「自分が指摘したせいで、人間関係がギクシャクするのは嫌だ」
このような、遠慮、気兼ね、自己保身といった心理的な壁が、声に出すことをためらわせてしまいます。そして、せっかく気がついた小さな違和感は放置され、やがて取り返しのつかない大事故という最悪の形で、その存在を証明してしまうのです。
「いのちを守る技術」において、この初期症状、つまり、
現場の作業員一人ひとりが感じる「違和感」や「気づき」
をいかにして掬い上げ、対策につなげるかは極めて重要なテーマです。
それを実現する技術が「言える化」です。
「言える化」とは、単なる「報告・連絡・相談の徹底」といったルールを作ることではありません。現場にいる誰もが、その人の立場や性格、役職、経験年数に関係なく、危険や懸念を感じた時に、安心して声に出すことができる『しくみ』と『文化』を意図的に作り上げる技術のことをいいます。
危険の芽は、小さな違和感のうちに摘み取らなければなりません。そのためには、現場に埋もれている無数の「声なき声」を掘り起こす言える化の『しくみ』が不可欠なのです。