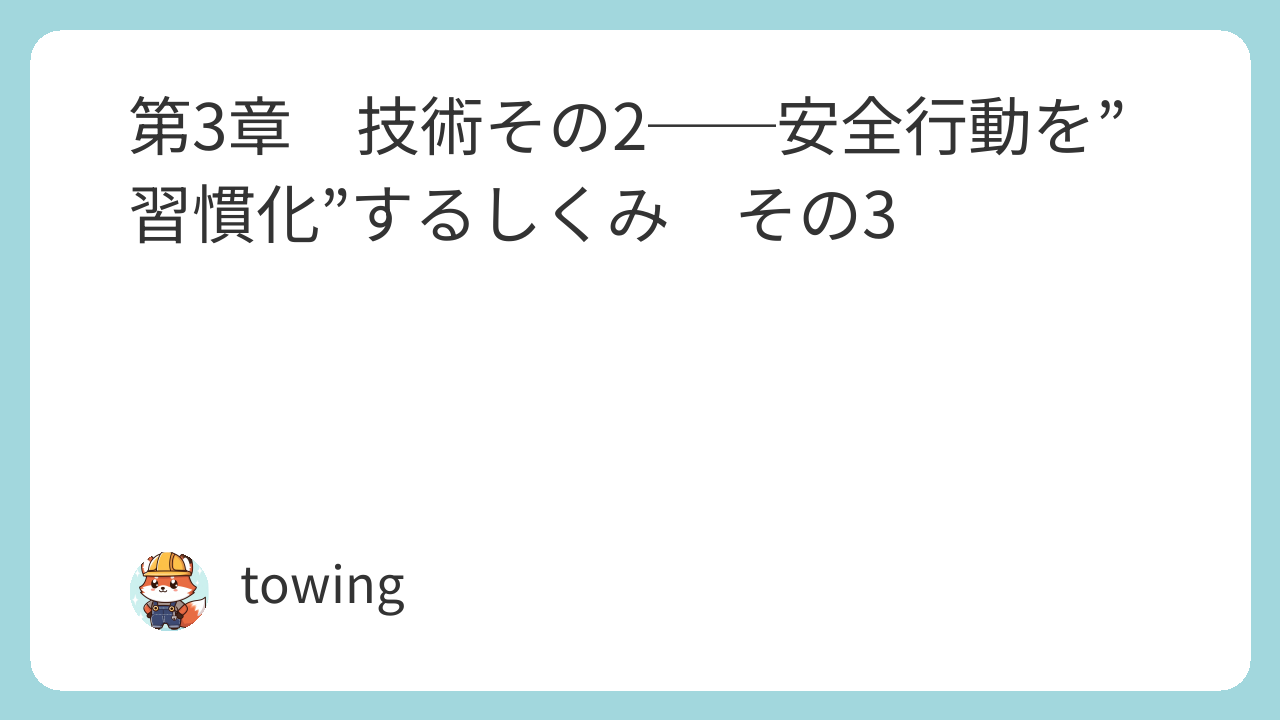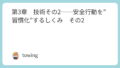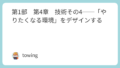朝礼・安全巡視を「習慣化装置」に変える技術
「習慣化のメカニズム」を理解したら、次はその理論を現場の日常業務に組み込みます。特に、毎日行われる「朝礼」と定期的な「安全巡視」は、習慣化の「きっかけ」と「報酬」を仕込む絶好の機会です。これらを単なる情報伝達や監視の場から、現場の安全文化を醸成する「習慣化装置」へと変えていきましょう。
朝礼への”仕込み”:きっかけと報酬の舞台
多くの現場の朝礼は、連絡事項の伝達と形骸化したKY活動に終始しがちです。これでは、安全意識の高揚はおろか、重要な情報すら頭に残りません。朝礼を安全行動の「きっかけ」を生み出す場として再設計しましょう。
- コツ1:「今日の安全行動」を具体的に宣言する
「安全第一で頑張りましょう」という曖昧な声かけでは、行動は変わりません。習慣化したい行動をその日の「きっかけ」とセットで具体的に伝えます。
- 悪い例:
「今日も一日、安全作業でお願いします」 - 良い例:
「今日は強風です。足場材を持つときは、必ず二人一組で。単独で持とうとしている仲間がいたら、すぐに声をかけましょう」
「本日、新規で入場される方が3名います。通路ですれ違う際は挨拶を。昨日の雨でぬかるみもあります。一歩目を踏み出す前に、足元を確認するとアクションを全員で徹底しましょう」
このように、具体的で、その日誰もが遭遇する可能性のある場面を「きっかけ」として提示することで、作業員は一日を通してその行動を意識しやすくなります。
- コツ2:「ポジティブな報酬」をその場で与える
朝礼を減点主義の反省会ではなく、加点主義の賞賛の場にします。安全のために良い行動をした個人やチームを全員の前で称賛することで、強力な「社会的承認」という報酬が生まれます。
- 実践例:
- 「昨日、Aチームの〇〇さんが、脚立の開き止めを確認していました。些細なことですが、素晴らしい行動です。皆さん、拍手!」
- 「B班からのヒヤリ・ハット報告、非常に良い気づきでした。危険を共有してくれてありがとう。全員が注意できます」
誰かが褒められるのを見ることで、「次は自分もみんなのために良い行動をしよう」という健全な欲求が生まれます。これが、現場全体の安全レベルを底上げしていきます。ネガティブな指摘は個別に行い、朝礼の場はポジティブなエネルギーで満たす。これが鉄則です。
安全巡視への”仕込み”:是正から是認へ
安全巡視が、「違反者探し」や「粗探し」の時間になっていませんか?巡視者が来たときだけ安全行動をしているふりをする現場では、本質的な安全は確保できません。巡視を「良い行動を発見し、承認する」ための機会、つまり「報酬」を与える時間に変えましょう。
- コツ1:「是正」より「是認」に力点を置く
巡視の目的を「悪い点」の指摘から、「良い点」の承認にシフトします。もちろん、明白な危険行為は即座に止めなければなりませんが、それ以上に、模範的な行動を積極的に探し、その場で賞賛します。
- 実践例:
- 安全帯を正しく使っている作業員を見つけたら、その場で「〇〇さん、そのフックのかけ方、完璧ですね。ありがとうございます!」と声をかける
- きれいに整理整頓された作業スペースを見たら、「この場所、すごく仕事がしやすそうですね。素晴らしいです」と伝える。
- 許可を得てそれらの様子を写真に撮り、安全掲示板や次の日の朝礼で「今週のグッドプラクティス」として共有する。
人間は、叱られることよりも、褒められることによって行動を強化する生き物です。巡視者が「褒めるために見回っている」と認識されれば、作業員は自発的に安全行動をとるようになります。
- コツ2:フィードバックの仕方を工夫する
改善点を伝えなければならない場合も、伝え方一つで相手の受け取り方は大きく変わります。いきなり欠点を指摘するのではなく、まずは肯定的な点から入る「サンドイッチ話法」が有効です。
- 悪い例:
「おい、そこのコード、養生してないじゃないか。つまずいたらどうするんだ」 - 良い例:
「作業、順調に進んでいますね(肯定)。ありがとうございます。もしよければ、そこのコードを養生テープで固定してもらえると、みんながもっと安全に通れるので助かります(改善要求)。他の部分はきれいに片付いているので、そこだけお願いしますね(再度肯定)」
注意や指示は、相手に「攻撃された」と感じさせ、防衛反応を引き起こします。サンドイッチ話法」あれば、相手の自己肯定感を守りながら、素直な行動変容を促す極めて有効なコミュニケーション技術です。
朝礼と安全巡視は、現場の安全文化を映す鏡です。そこに「きっかけ」と「報酬」の仕込みを入れることで、単なる日課は、安全行動を自動的に生み出し、強化する強力なエンジンへと変わります。
意志力だけに頼る安全管理には限界があります。でも、日々の業務の中に習慣化の『しくみ』を埋め込むことで、現場はもっと良く、もっと安全になることができるのです。
私たちが目指すべきは、個人の意識に頼らない、持続可能な安全管理システムです。それは決して難しいものではありません。皆さんの現場にある既存の仕組みを少し変えるだけで、劇的な効果を生み出すことができるのです。