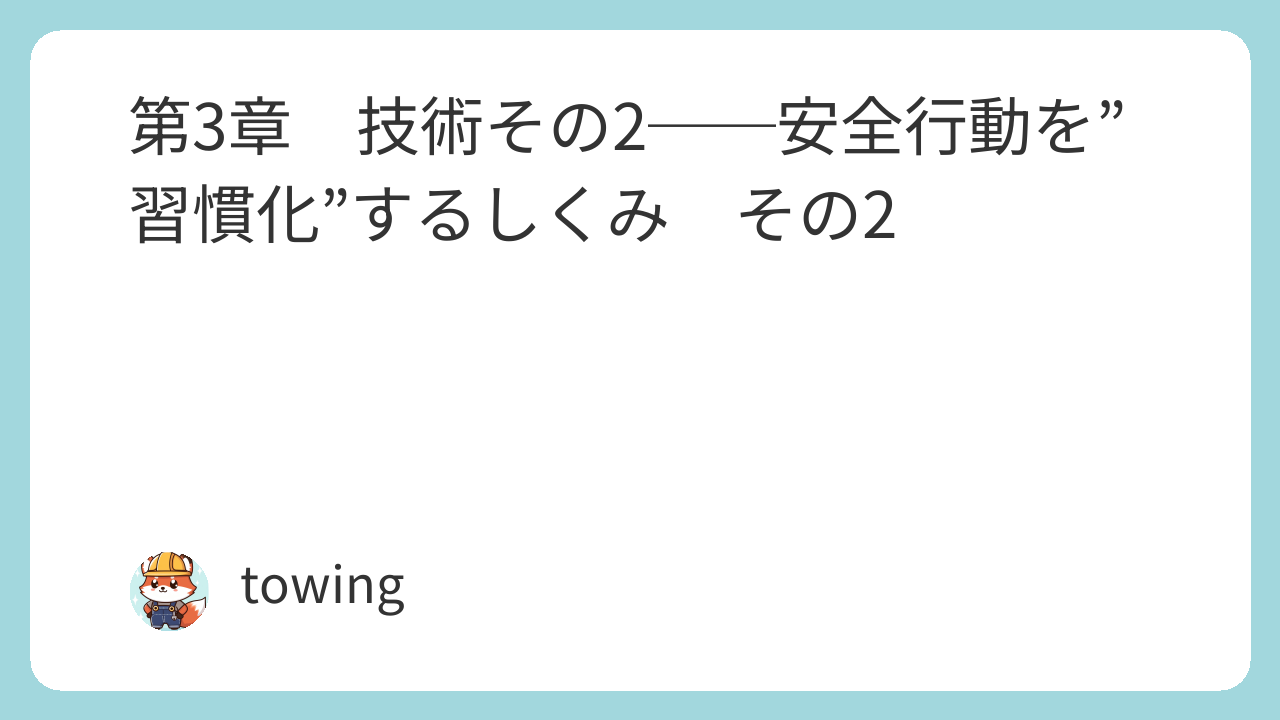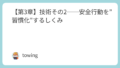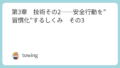習慣化のメカニズム:「きっかけ・実行・報酬」
では、どうすれば安全行動を「習慣」にできるのでしょうか。そのカギは、行動科学の世界で広く知られている「習慣のループ」というモデルにあります。これは、ジャーナリストのチャールズ・デュヒッグがその著書『習慣の力』で紹介し、一躍有名になりました。
どんな習慣も、次の3つの要素で構成されていると彼は言います。
- きっかけ(Cue):
行動のスイッチを入れる特定の合図。トリガーとも呼ばれます。 - 実行(Routine):
実際に行う行動そのもの。習慣化したい(あるいは、やめたい)行動です。 - 報酬(Reward):
その行動の後に得られる快感や満足感。脳が「このループを記憶する価値がある」と判断するためのご褒美です。
この3つが繰り返されることで、私たちの脳は「きっかけ」と「報酬」を強く結びつけ、「きっかけ」に遭遇すると、半ば自動的に「実行」を渇望するようになります。これが、習慣が形成されるメカニズムです。
例えば、「ラーメンを食べた後に一服する」という喫煙者の習慣をこのループに当てはめてみましょう。
- きっかけ: ラーメンを食べ終わる
- 実行: タバコに火をつけて吸う
- 報酬: ラーメンの後味と相まって普段よりおいしく感じるタバコの味、ニコチンによる満足感
このループが繰り返されることで、「ラーメンを食べ終わる」というきっかけだけで、猛烈にタバコが吸いたくなります。
この強力なメカニズムを安全行動の定着に応用しましょう。現場で定着させたい安全行動を「実行」に設定し、その前後に意図的に「きっかけ」と「報酬」を設計するのです。
安全行動を習慣化するループの設計例
実行(Routine):高所作業前の安全帯フックの確認
- きっかけ(Cue)の設計:
「いつでも気をつけろ」では、きっかけになりません。「いつ、どこで、何をしたら」という具体的なレベルまで明確にすることが重要です。
時間で設定する場合:
- 「午後の作業開始時」
- 「足場に上がる直前」
場所で設定する場合:
- 「安全帯を装着する特定の場所」
- 「足場への昇降口」
行動で設定する場合:
- 「ハーネスに袖を通したとき」
- 「仲間が足場に上がり始めたとき」
例えば、「高さ2m以上の足場に上がる直前には、必ずフックを指差呼称する」とルール化すれば、「足場に上がる」という行動が、指差呼称の「きっかけ」として機能し始めます。
- 報酬(Reward)の設計:
ここが、多くの現場がつまずく最大のポイントです。なぜなら、安全行動の本来の報酬は「事故が起きなかった」という、目に見えず、実感しにくいものだからです。災害は起きなくて当たり前。だから、脳はそれをなかなか「報酬」として認識してくれません。
そこで、すぐに得られる「小さな報酬」を意図的に作り出す必要があります。
自己肯定感という報酬
- ポケットサイズのチェックリストを用意し、確認したら自分でチェックを入れる。「☑」という小さな達成感が報酬になります。
- 「フックよし!」。自分の声で確認することで、「今日もちゃんとやったぞ」という自己肯定感が得られます。
社会的承認という報酬
- 二人一組で相互確認し、「〇〇さん、OKです!」「ありがとう!」と声をかけ合います。仲間からの承認は、非常に強力な報酬です。
- 職長が、安全行動を実践している作業員を見つけたら、その場で「いいね!」「ありがとう、助かるよ」と具体的に声をかけます。
感覚的な報酬
- きれいに整理整頓された工具置き場。それを使う心地よさが、整理整頓という行動の報酬になります。
- 正しく装着した保護具のフィット感。「よし、これで守られている」という安心感も、立派な報酬です。そこで、すぐに得られる「小さな報酬」を意図的に作り出す必要があります。
不安全行動のループを理解する
逆に、不安全行動がなぜ習慣化してしまうのかも、このループで説明できます。
- きっかけ: 「急いでいる」「ちょっと面倒くさい」という感情
- 実行: あご紐を締めない、フックをかけない
- 報酬: 「楽ができた」「時間を短縮できた」という即効的なメリット
この「不安全行動のループ」がいかに強力かを理解し、それを上回る「安全行動のループ」を現場全体で設計し、根気よく回し続けること。それこそが、安全を『しくみ』で根付かせるための核となる考え方なのです。