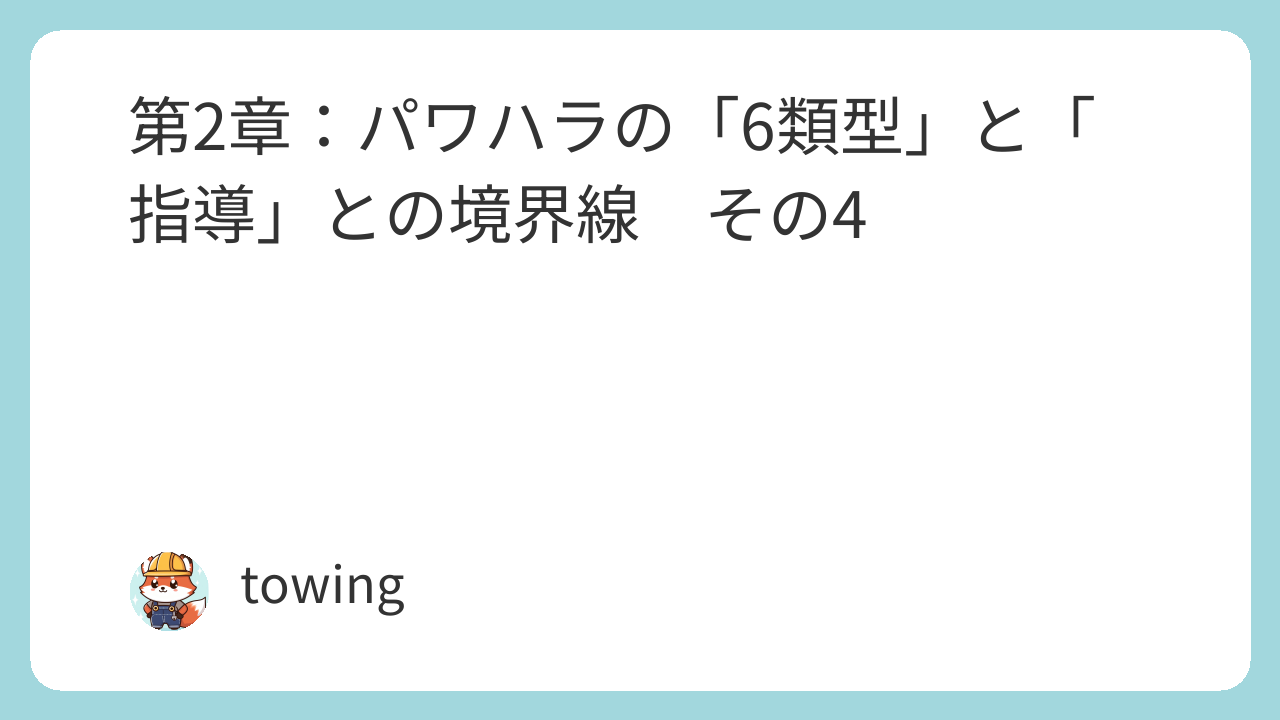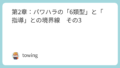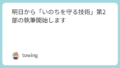4. 現代の職場で特に注意すべき新たなパワハラリスク
従来のパワハラ対策に加えて、現代の職場環境の変化に伴い、新たに注意すべきパワハラのリスクが生まれています。これらについても触れておきましょう。
(1) リモートワーク環境でのパワハラ
コロナ禍以降、リモートワークが普及する中で、新たなパワハラの形態が問題となっています。
注意すべき行為例
- オンライン会議で特定の従業員を意図的に無視する
- 必要以上に頻繁な監視や報告を求める
- プライベート空間が映る状況での会議参加を強要する
- 深夜・早朝の業務連絡を常態化させる
(2) 世代間ギャップによるパワハラ
価値観の多様化により、世代間での認識の違いが原因となるパワハラも増えています。
具体的な課題
- 「これくらいは当たり前」という従来の常識の押し付け
- デジタルネイティブ世代への理解不足
- ワークライフバランスへの価値観の違い
(3) ダイバーシティ時代の配慮事項
性的マイノリティ、外国人労働者、障害者など、多様な背景を持つ従業員への配慮が求められています。
特に注意すべき点
- 無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)による言動
- 文化的背景への理解不足
- 合理的配慮の欠如
まとめ:パワハラと指導の境界線を見極める力
パワハラと指導の境界線は、時に細く、見えにくいものです。しかし、その根底にある**「相手を尊重し、成長を願う心」があるかどうか。その言動に、業務上の目的を超えた「私的な感情や支配欲」**が混じっていないかどうか。その違いが、両者を分ける決定的な差となるのです。
私たちが提供すべき価値
社会保険労務士として、私たちが顧問先に提供すべき価値は、単なる法的知識の提供にとどまりません。それは:
- 予防的な組織風土づくりの支援
- 管理職の指導力向上への貢献
- 多様性を活かした職場環境の実現
- 持続可能な成長を支える人材育成体制の構築
これらすべてが、真のパワハラ防止対策なのです。
実践への第一歩
この章で学んだ知識を、ぜひ明日からの実務に活かしてください。顧問先の管理職が自信を持って部下を指導し、すべての従業員が安心して能力を発揮できる職場づくり。それこそが、私たち社会保険労務士の使命なのです。
私たちは、法律論という「ものさし」と、人間への深い洞察という「共感力」の両輪で、この複雑で重要な問題に立ち向かっていく必要があります。
次章では、セクシュアルハラスメントと妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについて、同様の実践的なアプローチで解説していきます。