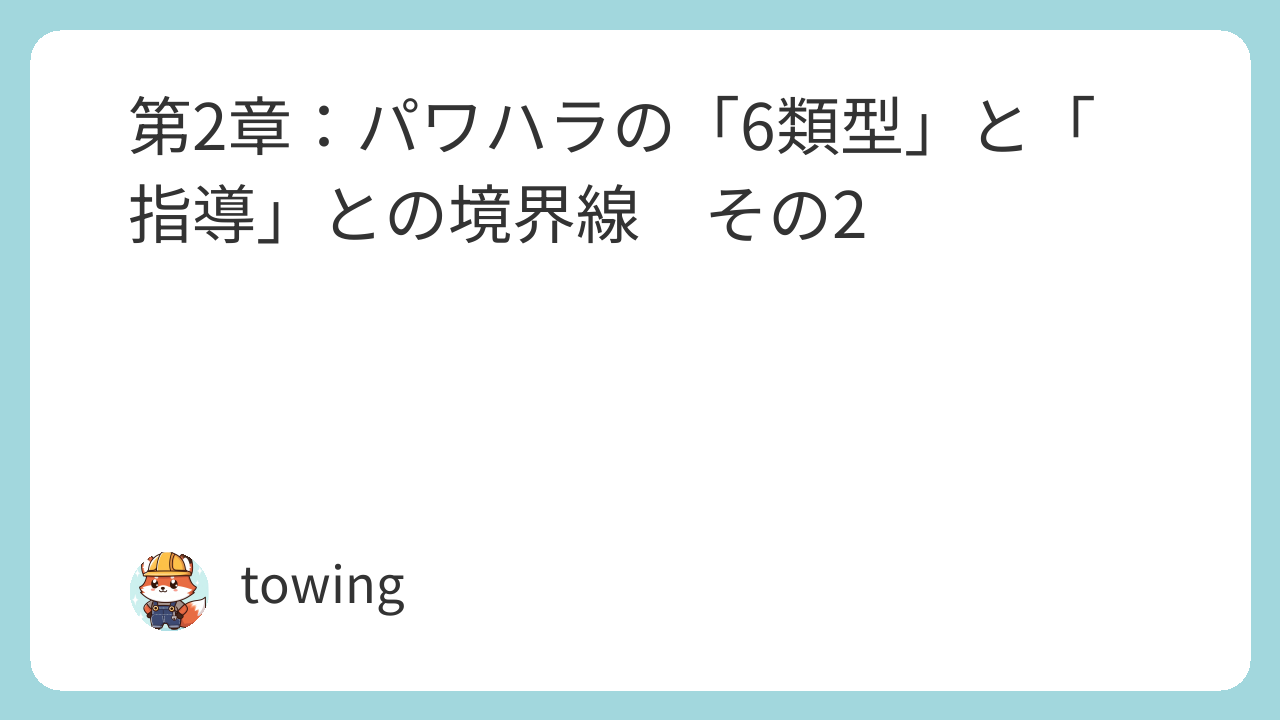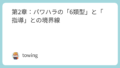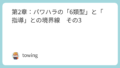2. 実践で活用する「パワハラ6類型」の完全理解
厚生労働省の指針では、パワハラに該当し得る言動を代表的な6つの類型に分類しています1。この「6類型」は、パワハラという漠然とした概念を具体的に理解するための、極めて優れた「思考のフレームワーク」です。
顧問先に説明する際も、この類型に沿って話を進めると、格段に理解が深まります。なぜなら、抽象的な「パワハラはダメ」という説明ではなく、「具体的にどのような行為が問題なのか」が明確になるからです。
各類型について、「該当すると考えられる例(=パワハラ)」と「該当しないと考えられる例(=業務指導の範囲内)」を対比させながら詳しく見ていきましょう。
① 身体的な攻撃
これは最も分かりやすく、かつ最も悪質なパワハラです。暴行・傷害など、相手の身体に直接危害を加える行為を指します。
重要なポイント:いかなる理由があっても、業務指導として正当化されることは絶対にありません。
該当すると考えられる例
- 殴る、蹴る、胸ぐらをつかむ
- 相手に物を投げつける(たとえ当たらなくても、攻撃の意図があれば該当し得ます)
- 机を叩く、壁を殴るなどの威嚇行為
該当しないと考えられる例
- 誤ってぶつかってしまった、手が当たってしまったなど、故意ではない接触
- 安全確保のために、とっさに相手の身体を制止した場合
② 精神的な攻撃
脅迫、名誉毀損、侮辱、ひどい暴言など、相手の人格や尊厳を傷つける言動です。相談件数が最も多く、「指導」との境界線で問題になりやすい類型でもあります。
該当すると考えられる例
- 他の従業員の前で、大声で威圧的な叱責を長時間繰り返す
- 相手の能力を否定し、「給料泥棒」「役立たず」「小学生以下だ」などと罵倒する
- 相手の性的指向・性自認や国籍、病歴などに関する侮辱的な発言をする
- 「お前や家族に何があるか分からないぞ」といった脅迫的な言動
- 「やめてしまえ」「クビだ」といった退職を強要する発言
該当しないと考えられる例
- 遅刻や度重なる業務上のミスなど、社会通念に照らして許されない行為に対して、一定程度強く注意すること
- 企業の業務内容や性質等に照らして、重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意すること
- 業務の遂行に関する指導を、相手の人格を尊重した適切な言葉で行うこと
境界線を判断するポイント 言動の目的、態様、頻度です。育成が目的で、態様も相当であり、一回性の注意であれば指導の範囲内ですが、相手を追い詰める目的で人格攻撃を伴い、執拗に繰り返されればパワハラと判断される可能性が高まります。
③ 人間関係からの切り離し
隔離、仲間外し、無視など、特定の従業員を職場内で孤立させる行為です。この類型は陰湿で、被害者に大きな精神的苦痛を与えます。
該当すると考えられる例
- 自身の意に沿わない従業員に対して、仕事を外し、長期間にわたり別室に隔離したり、自宅研修を命じたりする
- 一人の従業員に対して、同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる
- 必要な業務連絡を意図的に伝えない
- 会議や打ち合わせから意図的に排除する
該当しないと考えられる例
- 新規採用した従業員を育成するために、一時的に別室で研修を受けさせること
- 懲戒処分を受けた従業員に対して、一時的に別室で反省を促すこと
- 業務の都合上、特定の会議への参加が不要と判断されること
判断基準のポイント 業務上の必要性と合理性です。育成や規律維持といった正当な目的があり、その期間や態様も適切であれば指導の範囲内ですが、嫌がらせ目的で合理的な理由なく孤立させるのはパワハラです。
④ 過大な要求
業務上明らかに不要なことや、遂行不可能なことを強制する行為です。相手を困らせる、あるいは退職に追い込むといった意図で行われることがあります。
該当すると考えられる例
- 新入社員に必要な教育を行わないまま、到底達成できないような高い営業ノルマを課し、未達成を厳しく叱責する
- 業務とは全く関係のない、私的な雑用(上司の家の掃除や買い出しなど)を強制的に行わせる
- 他の従業員よりも著しく多い業務量を、嫌がらせ目的で割り当てる
- 終業時間間際に、翌朝までに終わらない大量の業務を命じる
該当しないと考えられる例
- 従業員を育成するために、現状の能力よりも少し高いレベルの業務を任せること
- 繁忙期に、業務上の必要性から、通常よりも一定程度多い業務を任せること
- 緊急事態への対応として、一時的に高い目標を設定すること
判断のポイント 育成目的の「ストレッチ」と、嫌がらせ目的の「過大な要求」は紙一重です。十分な教育やサポート体制の有無、目標設定の合理性が、その境界線を判断する重要な要素となります。
⑤ 過小な要求
過大な要求とは逆に、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないことです。従業員のプライドを傷つけ、働く意欲を奪う行為です。
該当すると考えられる例
- 管理職として採用した従業員に対して、嫌がらせ目的で、一日中シュレッダー係や草むしりだけを命じる
- 気に入らないという理由で、ある従業員にだけ一切仕事を与えず、机に座らせておくだけにする
- 能力や経験に見合わない単純作業のみを継続的に割り当てる
該当しないと考えられる例
- 従業員の能力に応じて、一時的に従前の業務より簡単な業務に就かせること
- 経営上の理由により、一時的に仕事が減少し、待機を命じること
- 体調不良から復帰した従業員に、段階的に業務を再開させること
判断基準 嫌がらせの意図の有無と業務上の合理性が判断の分かれ目です。経営判断や本人の能力への配慮といった合理的な理由があれば問題ありませんが、意図的に尊厳を傷つける目的で行われればパワハラとなります。
⑥ 個の侵害
私的なことに過度に立ち入る行為です。プライバシーの侵害とも言えます。近年、特に注意が必要なのは「アウティング」と呼ばれる行為です。
該当すると考えられる例
- 交際相手や配偶者について、執拗に尋ねたり、別れるように強要したりする
- 職場外でも従業員を継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする
- 本人の了解を得ずに、その従業員の性的指向・性自認や病歴、不妊治療などの機微な個人情報を、他の従業員に暴露する(アウティング)
- 宗教や政治的思想について、執拗に質問したり、自分の考えを押し付けたりする
該当しないと考えられる例
- 従業員の体調を気遣い、家族の状況などを適度に尋ねること
- 従業員への配慮を目的として、本人の同意を得た上で、家族の状況などを人事部門の担当者に伝えること
- 業務上必要な範囲で、個人情報を確認すること
特に注意すべき「アウティング」 アウティングは、被害者に深刻な心理的苦痛を与え、取り返しのつかない事態を招きかねない極めて悪質な行為です。顧問先には、この重大性をはっきりと伝える必要があります。