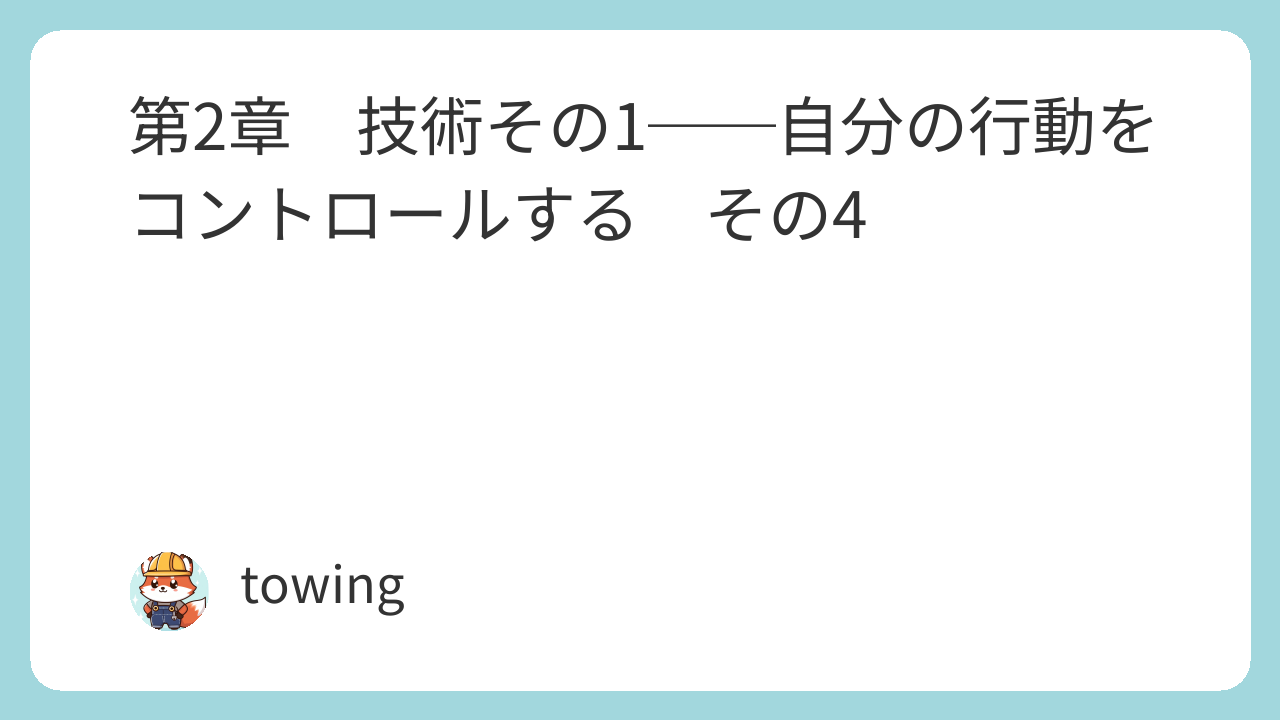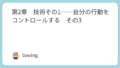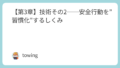習慣2:「もしも…」を問う、一人KY活動
作業前のKY(危険予知)活動も、形骸化しやすいものの代表例です。「墜落災害に注意」「熱中症に注意」といった、漠然とした目標を唱和するだけで終わってしまっては、危険感受性は高まりません。
より実践的な方法は、作業を始める直前に、たった30秒でも良いので、具体的な危険を「自分ごと」としてイメージする「一人KY」を習慣にすることです。
その際の問いは、「もしも(What if)、~だったら?」です。
- 「もしも、今持っているこのスパナを落としたら、下にいる誰の頭に当たるだろうか?」(高所作業中)
- 「もしも、この段差でつまずいたら、運んでいる資材はどのように崩れるだろうか?」(資材の運搬中)
- 「もしも、オペレーターが自分の合図を見誤ったら、次に何が起こるか?」(重機作業の合図中)
このように、「もしも」を自身に問いかけることで、抽象的だった危険が、生々しい現実味を帯びてきます。「落ちるかもしれない」ではなく、「自分が落ちたら、頭から落ちるか、足から落ちるか。どこに体を打ち付けるか」とまで具体的に想像してみることです。
失敗を想像することに抵抗があるかもしれませんが、最悪の事態を具体的にシミュレーションする訓練こそが、危険に対する感度を研ぎ澄ませ、「じゃあ、こうしておこう」という具体的な対策行動へとつながる、最も効果的な思考のトレーニングとなります。
習慣3:「いつもと違う」を探す観察の目
ベテランの職人さんが持つ「勘」や「経験」の正体は、多くの場合、無意識のうちに蓄積された膨大な観察データに基づくものです。「なんだか、いつもと違うな」という微細な違和感を察知する能力、それが彼らの安全を意識せずとも支えています。
この能力は、特別な才能ではありません。意識的な観察の習慣によって、誰でも後から身につけることができます。
現場を歩くとき、ただ目的地に向かって歩くのではなく、意識的に「いつもと違うところはないか?」という探偵のような視点を持ってみましょう。
- 視覚:
いつもと違う場所に工具が置かれていないか?足場の手すりがわずかに歪んでいないか? - 聴覚:
機械から異音がしていないか?周囲の会話に焦りや怒気が含まれていないか? - 嗅覚:
ガスの臭いや、何かが焦げるような化学的な臭いはしないか? - 触覚・体感:
地面の揺れ、気温、風の強さはいつもと違わないか?
五感をフル活用し、現場の「平常時」の状態を自分の中にインプットしておくのです。そうすることで、わずかな「異常」にも「違和感」として気づくことができるようになります。この違和感こそが、大きな災害の前兆(シグナル)であることが少なくありません。
最初は難しいかもしれませんが、例えば「今日は、3つ『いつもと違う』を見つけてから帰る」といった自分なりのルールを設けてみるのも良いでしょう。観察の習慣は、危険感受性を高めるだけでなく、作業の段取りや品質管理にも役立つ、すべての現場技術の基礎となるスキルです。
自分の行動をコントロールする技術とは、精神力で自分を律することではありません。それは、「わかっていても、やらない」という人間の弱さを前提として、
- 危険な行動ができない・したくなくなる「環境」を設計する技術
- 危険の兆候に気づける「感受性」を日々の取組で鍛える技術
この二つを両輪として成り立っています。
次の章からは、この行動コントロールをさらに確実なものにし、「安全行動」をチーム全体の「習慣」へと昇華させていくための、より具体的な『しくみ』について掘り下げていきます。
まずは今日から、あなたの現場の「障壁」を探し、指差し呼称のやり方を少しだけ変えてみることから始めてみませんか。その小さな一歩が、あなたと仲間のいのちを守る、確かな技術となるはずです。たの現場の「障壁」を探し、指差し呼称のやり方を少しだけ変えてみることから始めてみませんか。その小さな一歩が、あなたと仲間のいのちを守る、確かな技術となるはずです。