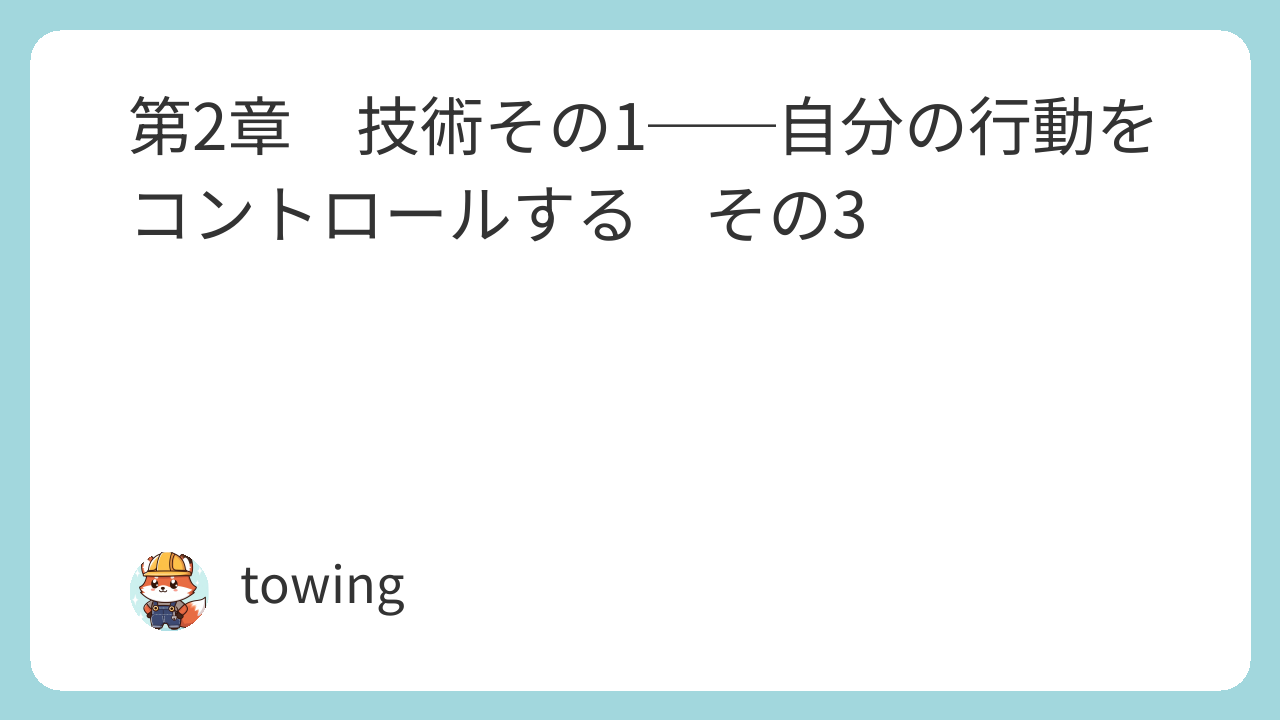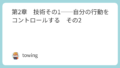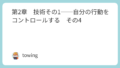「危険感受性」を高める3つのシンプルな習慣
環境を整える外からのアプローチと同時に、私たち一人ひとりの内からのセンサー、つまり「危険感受性」を高めていくことも、行動コントロールの重要な要素です。
危険感受性とは、単に「ここに危険があります」と知識として知っていることではありません。目の前の状況に潜むリスクを「自分ごと」としてリアルに感じ取り、「おや、何かおかしいぞ」「これは危ないかもしれない」と直感的に察知する能力のことです。
この感受性は、残念ながら日々の作業に慣れるほど、錆びつき、鈍化していく傾向があります。いつも見ている光景、いつもやっている作業だからこそ、「今日も大丈夫だろう」という正常性バイアス(自分にとって都合の悪い情報を無視してしまう傾向)が働き、危険の兆候を見過ごしてしまうのです。
でも、この危険感受性は、意識的な「取組」によって鍛え、維持することができます。ここでは、誰でも今日から実践できる3つのシンプルな習慣をご紹介します。
習慣1:脳にスイッチを入れる儀式「指差し呼称」
「安全帯、ヨシ!」「電源、ヨシ!」「吊り荷、ヨシ!」
建設現場ではおなじみの「指差し呼称」ですが、あなたはこれを単なる形式的なセレモニーだと思っていませんか?もしそうなら、非常にもったいないことです。指差し呼称は、脳科学にも裏付けられた、極めて効果的なエラー防止技術なのです。
私たちの脳は、隙さえあれば省エネモードで動こうとします。慣れた作業は、いちいち意識しなくても「自動運転モード」でこなせてしまいます。しかし、この自動運転こそが、見落としや思い込みによるミスの温床なのです。
指差し呼称は、この自動運転モードに強制的に介入し、意識を「今、ここ」に集中させるためのスイッチです。
- 指を差す(Pointing):
対象物に注意を向け、脳に「これを見ろ」と命令します - 呼称する(Calling):
対象物の状態を口に出して言語化し、意味を明確にします - 耳で聞く(Listening):
自分の声を聞いて、脳で再確認し、記憶に定着させます
この一連の動作は、視覚、聴覚、触覚(指を動かす感覚)など、五感を総動員して脳を活性化させます。JRの研究によれば、指差し呼称を実践することで、作業ミスが約6分の1にまで減少したという驚くべきデータもあります。
大切なのは、「心ここにあらず」で形だけ真似るのではなく、一つひとつの動作を意識することです。面倒くさがらず、恥ずかしがらず、自分の脳に安全のスイッチを入れるための大切な「儀式」として、日々の作業に取り入れてみてください。みてください。