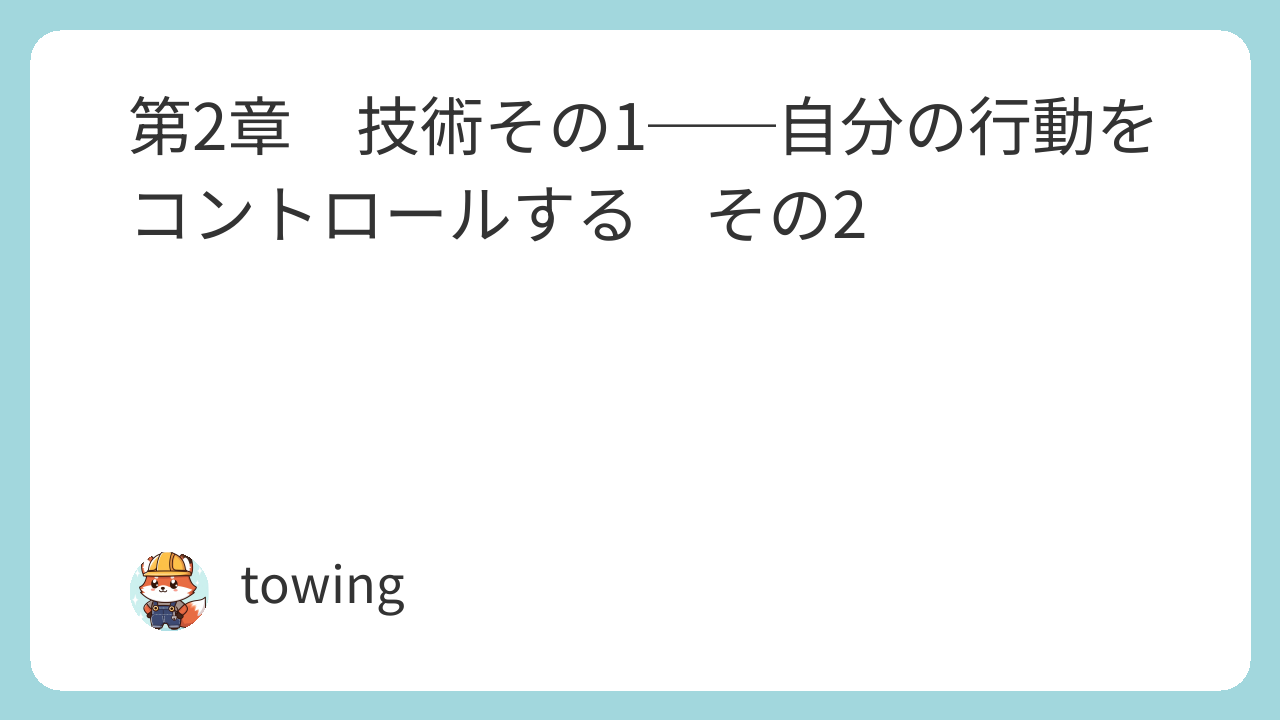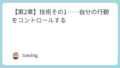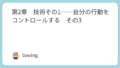行動の法則を理解する
ここで、第1章で触れた社会心理学者クルト・レヴィンが提唱した法則を、もう一度思い出してみてください。
B = f(P, E) (行動 = 人と環境の関数)
この法則が示すように、人間の行動(Behavior)は、その人の個性(Personality)だけで決まるのではありません。その人を取り巻く環境(Environment)との相互作用によって生まれるのです。
つまり、「わかっていても、やらない」という行動は、その人のやる気や意識が低いからという単純な理由ではないとういうことです。そうさせてしまう「環境」にこそ、本質的な原因が潜んでいます。
例えば、「ヘルメットのあご紐を締めない」という一つの行動の裏には、実に様々な要因が隠れています。
- 環境要因1(面倒):
すぐに外したり着けたりするのが、単純に「面倒くさい」 - 環境要因2(不快):
汗で蒸れてしまい、作業に集中できないほど「不快だ」 - 環境要因3(同調圧力):
周囲の誰も締めておらず、「自分だけが真面目に締めるのが気まずい」 - 環境要因4(時間的制約):
とにかく急いでいて、紐を締めるわずかな時間すら惜しいと感じる
これらの一つひとつが、安全行動を阻む「障壁(バリア)」として機能しているのです。これらの障壁が、私たちの「まあ、いいか」という悪魔のささやきを後押しし、「わかっていても、やらない」という不安全な行動へとつながっていくのです。
したがって、いのちを守るための技術の第一歩は、自分や他人の「意識の低さ」を責めることではありません。
行動をコントロールできないのは、意志が弱いからではない。そうさせてしまう『しくみ』と『環境』が存在する
からです。
本章では、この「わかっていても、やらない」という人間の抗いがたい特性から目をそらさず、それを乗り越えるための具体的な「技術」を解説します。それは、根性論や精神論に頼るのではなく、行動科学の知見に基づき、安全行動を阻害する「障壁」を一つひとつ丁寧に取り除いていく、極めて実践的なアプローチです。
誘発要因を取り除く「人と環境の設計」
「わかっていても、やらない」を引き起こす「誘発要因」を取り除くには、どうすればよいのでしょうか。
その答えが、「人と環境の設計」という考え方です。これは、人間の行動特性や心理をあらかじめ理解した上で、望ましい行動(つまり、安全行動)を“つい、やってしまう”ような環境を、意図的に設計するアプローチです。
強制的に「やらせる」のではなく、無意識のうちに「やっていた」という状況を作り出す。これこそが、行動コントロール技術の核心です。
そのための代表的な3つの手法を、具体的に見ていきましょう。
1. 物理的に「できない」ようにする(フールプルーフ)
最も強力な環境設計は、そもそも危険な行動を物理的に不可能にしてしまうことです。これを「フールプルーフ(Fool-proof)」と言います。
操作を誤ったり、ルールを知らない人が扱ったりしても、重大な事故が起きないように工夫された、いわば「失敗の入り口」を塞ぐ設計思想です。
- 代表例:インターロック機構
プレス機や工作機械などで、安全カバーが開いている状態では電源が入らない、あるいは機械が作動しないようにする「インターロック」は、フールプルーフの代表例です。「カバーを閉め忘れる」というヒューマンエラーが発生したとしても、事故に至るプロセスそのものを物理的に遮断してくれます。 - 建設現場への応用
クレーンの過負荷防止装置は、定格荷重を超えるとブザーが鳴り、自動的に停止します。これにより、オペレーターの「このくらい大丈夫だろう」という危険な過信による操作を許しません。特定の鍵がなければ操作できない重機や、正しい手順でなければ作動しない電動工具なども、この考え方に基づいています。
あなたの現場で「ついついやってしまいがち」な危険行動を思い浮かべてみてください。それを物理的に不可能にする方法はないでしょうか?「~してはいけない」というルールを追加する前に、「~できない『しくみ』」を考える。この視点が、現場の安全レベルを飛躍的に引き上げます。
2. 間違えても「安全な側」に倒れる(フェイルセーフ)
機械の故障や人間のミスが避けられないことを前提に、異常が発生した際には、必ず安全な状態で停止・制御されるように設計するのが「フェイルセーフ(Fail-safe)」です。これは「失敗が起きても、致命傷には至らない」という出口戦略とも言えます。
- 代表例:停電で閉まる踏切
鉄道の踏切は、停電などで制御システムが故障した場合、遮断桿が自重で自動的に下がるように設計されています。これは、万が一の際に「開いたまま」という最も危険な状態を避けるための、賢明なフェイルセーフ機能です。 - 建設現場への応用
ロープが切断するなど万一の故障の際に、落下を防止する緊急ブレーキを備えたエレベーターなどがこれにあたります。
フールプルーフが「エラーの入り口」を塞ぐのに対し、フェイルセーフは「エラーが起きた後の出口」を安全な方向へ導く技術と言えます。この二つの考え方を組み合わせることで、事故を防ぐための多重の安全網を構築することができるのです。
3. 無意識を味方につける「行動デザイン(ナッジ)」
物理的な制約を設けるのが難しい場面では、人間の心理に巧みに働きかけて、自発的に行動を変えることを促す「ナッジ(Nudge)」、つまり「そっと後押しをする工夫」が極めて有効です。これは、選択の自由を奪うことなく、より良い選択をしやすくするための、賢い仕掛けです。
- 代表例:小便器のハエのシール
オランダのスキポール空港で、男性用小便器の内側にハエの絵のシールを貼ったところ、的を狙う男性の習性により、便器周りの汚れが8割も減少したという有名な話があります。「きれいに使ってください」と警告するのではなく、遊び心のある仕掛けで望ましい行動を自然に引き出した、ナッジの好例です。 - 建設現場への応用
- 動線の工夫:
危険なエリアや重機の作業範囲を明確にカラーコーンなどで囲い、安全な通路にペンキで足跡マークを描くだけで、人は無意識に安全なルートを選ぶようになります。遠回りでも安全な通路の方を「公式ルート」として歩きやすく整備し、危険な近道はあえて通りにくくする(資材を置く、段差を設けるなど)のも有効です。 - 整理整頓の工夫:
工具やヘルメットの置き場所をただ線で囲うだけでなく、そのモノの形にくり抜いたウレタンマット(形跡管理)を用意したり、壁に影の絵を描いたりします。すると、人はパズルのピースを埋めるような感覚で、自然と元の場所に戻したくなります。「片付けてください!」と指示するより、はるかに効果的です。 - 視覚的なリマインダー:
開口部や段差など、特に注意すべき場所の手前に、「指差し呼称」をしている現場代理人や職長の実写ポスターやイラストを掲示します。これにより、作業員の方は「ああ、ここでは指差し呼称をするんだったな」と行動を思い出しやすくなります。
これらの工夫に共通するのは、人間の「つい、~してしまう」という習性を利用している点です。「面倒なことは避けたい」「楽をしたい」「面白いものに惹かれる」といった、ごく自然な感情を否定せず、むしろそれを安全行動へと導くエネルギーとして活用するのです。
「人と環境の設計」とは、大掛かりな設備投資やシステムの導入だけを指すのではありません。現場の状況をよく観察し、人間の心理を少しだけ理解すれば、お金をかけずとも実践できる知恵の集合体なのです。
安全行動を阻害している「面倒くさい」「わかりにくい」「やりづらい」といった障壁は何か。それを取り除くための、ちょっとした「後押し」は何か。この問いこそが、現場を劇的に変える第一歩となります。