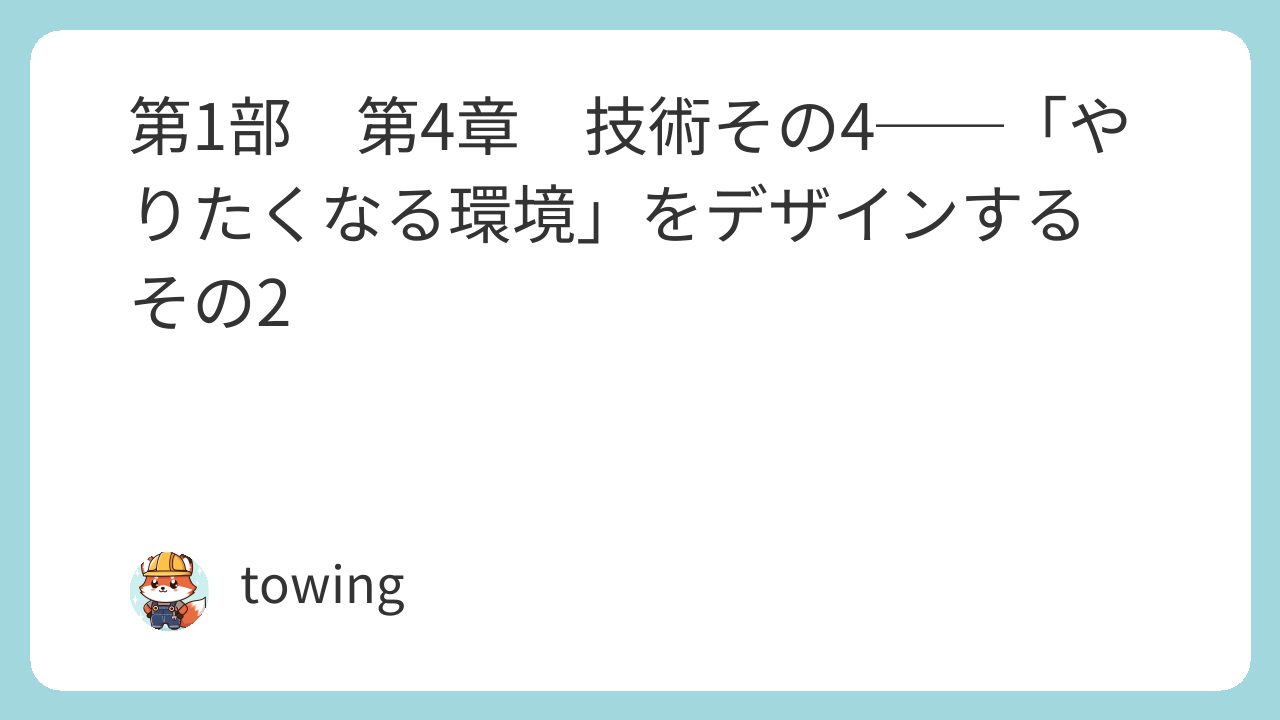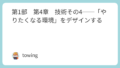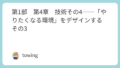「やらないと怒られる」では人は動かない
「なぜ、うちの現場は指示されたことしか実行できないのか」
「若手が自発的に行動してくれず困っている」
多くの現場責任者やリーダーが抱える悩みではないでしょうか。その根本原因は「やらないと怒られる」という動機付けに頼りすぎているからかもしれません。
心理学において、人間の動機付けを大きく二つに分類します。一つは、報酬や罰則といった外部からの働きかけによる「外的動機づけ」。もう一つは、本人の内側から湧き出る興味や関心、やりがいなどによる「内発的動機づけ」です。
「怒られるからやる」というのは、外的動機づけの典型です。確かに外的動機づけが短期的に人の行動を変える力を持つことは事実です。でも、それには大きな限界が存在し、副作用が伴います。
- 限界1:監視がないとやらない
罰を避けることが目的なので、監視の目がない場所では、すぐに元の行動に戻ってしまいます。「上司が見ている時だけヘルメットのあご紐を締める」といった行動は、その典型です。これでは24時間365日、管理者が現場に張り付いていなければ安全は保てません。 - 限界2:指示待ち人間を生む
常に「これをやらないと怒られる」という環境にいると、人は自分の頭で考えることをやめてしまいます。言われたことだけをこなす「指示待ち」の姿勢が染みつき、イレギュラーな事態や想定外の危険に対応できなくなります。自発的な改善提案など、生まれるはずもありません。 - 副作用:ヒヤリ・ハットの隠蔽
これが最も危険な副作用です。「ミスをしたら怒られる」という恐怖は、失敗の報告をためらわせます。小さなヒヤリ・ハットや「ちょっと危なかった」という経験は、本来なら重大災害を防ぐための貴重な情報源です。しかし、報告すれば叱責されるとなれば、誰だって隠したくなるのが人情です。その結果、問題が水面下で進行し、取り返しのつかない大事故となって初めて発覚するのです。声の出ない現場には、危険の芽が確実に育ちます。
では、どうすれば人は自ら「やりたい」と思うようになるのでしょうか。内発的動機づけを高めるカギは、アメリカの心理学者エドワード・デシとリチャード・ライアンが提唱した「自己決定理論」にあります。彼らは人間が内発的に動機づけられるためには、次の三つの欲求が満たされることが重要だと指摘しました。
- 自律性(自己決定感):「自分の行動は、自分で決めている」という感覚
- 有能感:「自分はできる、うまくやれる」という感覚
- 関係性:「周囲の人たちと尊重し合い、つながっている」という感覚
これを現場の安全管理に応用してみましょう。
- 「自律性」を高める工夫
ルールを一方的に押し付けるのではなく、その目的や背景を丁寧に説明し、全員で話し合って決めるプロセスを設けます。「会社が決めたから」ではなく、「自分たちが安全のために決めたルールだ」と思えれば、やらされ感は薄れます。例えば、KY(危険予知)活動で「今日の安全目標」を決めるとき、リーダーが一方的に決めるのではなく、チームのメンバーから意見を募り、全員で採択します。それだけでも、「自分たちで決めた」という当事者意識が芽生えます。
- 「有能感」を高める工夫
安全行動を「実行できたこと」として認め、褒める文化を作ることが重要です。叱責ではなく、承認が人の有能感を育てます。例えば、若手が率先して整理整頓をしていたら、「よく気がついたね、ありがとう。おかげで通路が安全になったよ」と具体的に声をかけます。安全パトロールを「できていないこと探し」ではなく、「良い取り組み探し」の機会と位置づけ、素晴らしい行動を朝礼で共有します。こうした小さな成功体験の積み重ねが、「自分は安全に貢献できている」という自信につながります。
- 「関係性」を高める工夫
安全は、個人プレーではなくチームプレーです。「自分の身は自分で守る」のは基本ですが、それだけでは限界があります。「仲間が危険な状態であったら声をかける」「チーム全体で安全な現場を作る」という連帯感を醸成することが不可欠です。職人さん一人ひとりを名前で呼び、朝礼で「◯◯さん、昨日はありがとうございました」といった感謝を伝えます。たったそれだけでも、現場の心理的な距離は縮まります。
「やらないと怒られる」という恐怖のマネジメントから、「やりたくなる」を後押しするマネジメントへ。それは、単に現場の雰囲気が良くなるだけでなく、一人ひとりのパフォーマンスを引き出し、災害に強い柔軟な現場を作るための最も効果的な取組です。