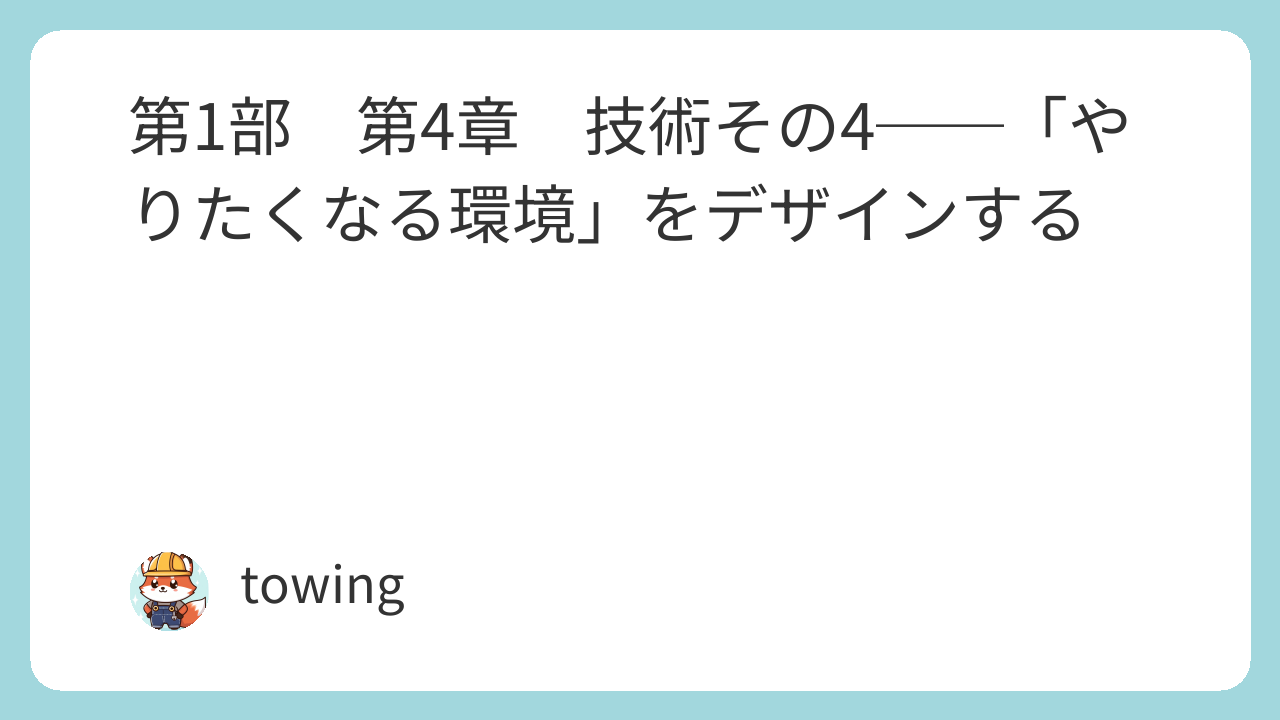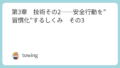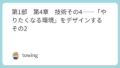強制から自発へ──行動デザインの考え方
「クレーンの荷の下に入るな!」
「外した手すりは元に戻せ。何度言ったらわかるんだ!」
現場で、今日も誰かの怒声が響いていませんか?
安全を守るためだとわかっていても、こうした声かけは、言う側、言われる側の双方にとって決して心地よいものではありません。むしろ、現場の空気をピリピリと悪化させ、かえって作業への集中を妨げてしまうことさえあります。
従来の安全管理では、「ルールで縛り、罰で従わせる」という発送が支配的でした。「〜してはならない」「〜すべし」という禁止と強制の文言が、現場の至る所に掲示されています。でも、私たちは経験的に理解しているはずです。ルールや罰則だけでは、人の行動を根本的に変えることはできないということを。監視の目があれば従うものの、誰も見ていなければ元の行動に戻る。これでは、本当の意味で“いのちを守る”ことはできません。
そこで本書が提案するのが、「行動デザイン」という考え方です。
行動デザインとは、端的に表現すれば
「人が自然と望ましい行動をとってしまうような『環境』を設計する技術」
のことです。強制するのではなく、人の心理や行動特性をうまく活用し、自発的な行動を後押しするアプローチを採用します。
近年、「ナッジ(nudge)」という言葉を耳にした方も多いいのではないでしょうか。ノーベル経済学賞を受賞したリチャード・セイラー教授が提唱した理論で、
「ヒジでそっと合図をして後押しするように、人々がより良い選択をするよう促す手法」
を意味します。行動デザインは、このナッジの理論を現場の安全管理に応用する取り組みです。
有名な事例をいくつかご紹介しましょう。
- オランダ・スキポール空港の小便器の「ハエ」
男性用小便器の内側に小さなハエの絵を描いたところ、利用者がそこを「的」にして狙うようになり、便器周りの汚れが8割も減ったという話はあまりに有名です。誰一人として「きれいに使え」と強制されたわけではありません。ただ、小さな絵があるだけで、人の行動が無意識のうちに変わりました。 - スウェーデン・ストックホルムの「ピアノの階段」
地下鉄の駅で、階段をピアノの鍵盤のようにデザインし、踏むと音が鳴るようにしました。すると、それまで多くの人が使っていたエスカレーターではなく、楽しんで階段を使う人が66%も増加したそうです。「健康のために階段を使いましょう」というポスターを貼るよりも、はるかに効果的でした。
これらの事例に共通するのは、「禁止」や「強制」ではなく、「楽しさ」や「ちょっとした工夫」によって人の行動を良い方向へ導いている点です。これを私たちの現場に応用してみましょう。
「頑張って安全行動をしよう」と精神論に頼るのではなく
「頑張らなくても、自然と安全な行動ができてしまう」
環境を作る。
「罰が怖いからルールを守る」のではなく、
「その方が気持ちいいから、やりやすいから、ついやってしまう」
という状況を作り出す。
そんな現場を作ることができれば、安全管理は「監視と叱責」という非生産的な業務から、「創造的でやりがいのある仕事」へと変わっていきます。本章では、この行動デザインの考え方に基づき、「強制」から「自発」へと現場を変えるための具体的な技術を解説していきます。