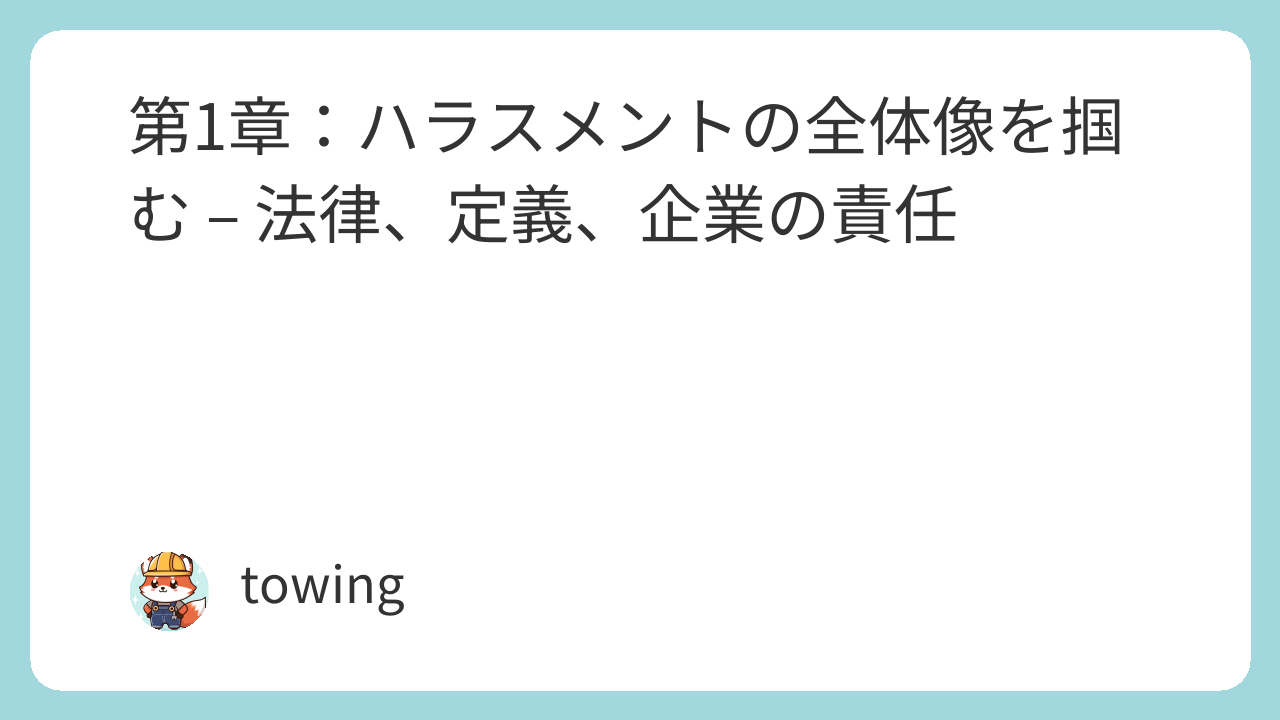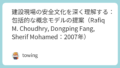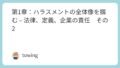社会保険労務士の皆さん。時代の変遷と共に顧問先からの相談内容が劇的に変化していることを、肌で感じていませんか。かつては「残業代の計算方法を教えて」「就業規則を見直したい」といった、いわば「守りの人事労務」に関する相談が大半でした。
しかし今、私たち社会保険労務士の元に寄せられる相談の多くは、「パワハラで従業員が休職してしまった」「セクハラの訴えがあったがどう対応すべきか」といった、企業の存続基盤を根底から揺るがしかねない、極めて重大な問題ばかりです。これは、単なる相談内容の変化ではありません。私たちが向き合うべき「現実」そのものが、根本的に変わったのです。
「ハラスメント対策は難しい」—— そう感じていらっしゃる先生方も多いでしょう。確かに、この領域は法的知識、心理学的理解、そして何より高度なコミュニケーション能力が求められる、極めて複合的な課題です。しかし、だからこそ、私たち社会保険労務士の真価が問われる分野でもあるのです。
第1部では、このハラスメント対策という複雑な迷宮を、確実に歩き抜くための「地図」を手に入れていただきます。家を建てる際に、まず地盤調査を行い、強固な基礎を築くのと同じように、まずは揺るぎない法的知識という「土台」を固めることから始めましょう。
この基礎がなければ、どんなに実践的なテクニックを身につけても、「なぜその対応が必要なのか」を顧問先に説得力を持って説明することはできません。逆に、この土台さえしっかりしていれば、どんな複雑な相談を受けても、冷静に対処の道筋を描くことができるようになります。
本章では、その基礎工事の第一歩として、3つの核心的な問いに明確な答えを出していきます。
- 「ハラスメントとは法的に何なのか?」
- 「企業には具体的に何が求められているのか?」
- 「それを怠るとどのような結末が待っているのか?」
「法律の話は苦手で…」と感じる方がいらっしゃるかもしれません。しかし、ご安心ください。ここでは単に条文を暗記するのではなく、その背景にある立法趣旨や、実務で「使える」知識の形に分解して解説していきます。
この章を読み終える頃には、あなたは顧問先から「先生、うちの会社は大丈夫でしょうか?」と相談されたとき、的確な現状分析と具体的な改善提案ができるだけの「武器」を手にしているはずです。
それでは、始めましょう。
1. 3大ハラスメントの定義と関係性 —— 複雑に絡み合う現実を整理する
「ハラスメント」という言葉が氾濫する現代において、私たちがまず明確にしなければならないのは、「法的に対策が義務付けられているハラスメント」の正確な範囲です。感情論ではなく、法律という確固たる根拠に基づいて判断できるようになることが、プロとしての第一歩だからです。
現在、日本の法律で事業主に明確な対策義務(措置義務)が課されているのは、以下の3つのハラスメントです。私はこれらを「3大ハラスメント」と呼んでいます。
- パワーハラスメント(根拠法:労働施策総合推進法)
- セクシュアルハラスメント(根拠法:男女雇用機会均等法)
- 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(根拠法:育児・介護休業法)
「3つもあるのですか?」と驚かれる方もいるかもしれません。しかし、現実の職場では、これらは決して独立した問題として発生するわけではないのです。
例えば、こんなケースを想像してみてください。男性上司が女性部下に対して「女のくせに生意気だ」と発言したとします。これは一見、性別を理由とした発言なのでセクシュアルハラスメントに思えます。しかし同時に、優越的地位を背景とした人格攻撃でもあるため、パワーハラスメントの側面も持っています。
さらに、その女性が妊娠を報告した途端に「どうせすぐ辞めるんだろう」と言われたとすれば、今度は妊娠・出産等に関するハラスメントの要素も加わります。
つまり、一つの言動が複数のハラスメントに該当することは、決して珍しくないのです。だからこそ私たちは、それぞれの定義を正確に理解しつつ、それらが重なり合う「グレーゾーン」の存在も常に意識しておく必要があります。
では、一つずつ詳しく見ていきましょう。
パワーハラスメント(労働施策総合推進法)—— 最も判断が困難な領域
2020年6月1日、労働施策総合推進法の改正により、パワーハラスメント対策が法的義務となりました(大企業は2020年6月1日、中小企業は2022年4月1日から施行)。これは、日本の雇用環境における歴史的転換点と言っても過言ではありません。
法律(指針)では、職場のパワーハラスメントを以下の3つの要素をすべて満たすものと明確に定義しています1。
- 優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
この3要素は、パワハラの「判定基準」として機能します。いわば、パワハラという「病気」を診断するための「検査項目」だと考えてください。3つの検査すべてで「陽性」が出て初めて、法的な意味での「パワーハラスメント」という診断が下されるのです。
第1要素:優越的な関係を背景とした言動
「優越的な関係」と聞いて、多くの方は「部長が課長に」「課長が一般社員に」という、職位の上下関係を思い浮かべるでしょう。もちろん、それが最も典型的なパターンです。
しかし、法律が想定する「優越的な関係」の範囲は、それよりもはるかに広いのです。例えば、以下のようなケースも該当します。
- 知識・経験による優越性:ITシステムに精通した若手社員が、システム音痴の年上の同僚に対して「こんなことも分からないんですか?使えないですね」と繰り返し嘲笑する
- 集団による優越性:職場の複数の同僚が結託して、特定の一人を無視したり、意図的に情報を共有しなかったりする
- 専門性による優越性:資格を持つ従業員が、無資格の同僚に対して「素人は黙っていろ」と発言し、業務から排除する
つまり、**形式的な職位の上下ではなく、実質的に「抵抗・拒絶することが困難な関係性」**全般を指すのです。
これは、従来の「上司から部下へのいじめ」という単純な図式では捉えきれない、現代の職場の複雑な人間関係を反映した定義と言えるでしょう。
第2要素:業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
この要素こそが、パワハラ対応において最も頭を悩ませる「正当な業務指導との境界線」を決定する重要な判断基準です。
企業にとって、業務上の指導や注意は不可欠です。しかし、その指導が以下のような場合には、この要件を満たすことになります。
- 業務上の必要性が認められない場合:私的な感情の発散や、個人的な嗜好の押し付けなど
- 業務上の必要性は認められるが、その手段が不相当な場合:目的は正当だが、手段が社会通念に照らして行き過ぎている
具体例を見てみましょう。
【業務上の必要性なし】
- 「お前の顔を見ていると虫酸が走る」(人格否定)
- 「新人のくせに偉そうに」(立場を利用した威圧)
【必要性はあるが手段が不相当】
- ミスを指摘する際に「バカ」「使えない」と人格を否定する言葉を使う
- 他の従業員の前で長時間にわたって執拗に叱責する
- 一度のミスを何日間も蒸し返して責め続ける
この判断において重要なのは、「指導者の意図」ではなく、「客観的な必要性と相当性」です。「指導のつもりだった」という弁解は、基本的に通用しないということを理解しておきましょう。
第3要素:労働者の就業環境が害されるもの
この要素は、その言動によって労働者が身体的または精神的な苦痛を感じ、職場環境が不快なものとなったために、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します2。
ここでの判断基準は「平均的な労働者の感じ方」です。つまり、当事者が「つらかった」と主観的に感じただけでは不十分で、同じ状況に置かれた他の多くの労働者も「これは看過できない」と感じるであろう、という客観性が求められます。
ただし、この「平均的な労働者」は、当該労働者と同様の状況(年齢、経験、職位など)にある者を基準として判断されます。新入社員と管理職では、同じ言動に対する受け取り方が異なるのは当然だからです。
セクシュアルハラスメント(男女雇用機会均等法)—— 意図は関係ない
セクシュアルハラスメント(セクハラ)は、男女雇用機会均等法第11条に基づき、事業主に防止措置義務が課されています3。
法律(指針)では、職場のセクシュアルハラスメントを「職場において行われる、労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されたりすること」と定義しています。
パワハラとの最大の違いは、「労働者の意に反する」という表現にあります。これは、行為者に悪意やセクハラの意図がなくても、相手が不快に感じればセクハラに該当し得るということを意味します。
「そんなつもりじゃなかった」「冗談のつもりだった」という弁解は、セクハラにおいては基本的に通用しません。重要なのは「受け手の感じ方」なのです。
セクハラは、その結果によって2つの類型に分けられます。
1. 対価型セクシュアルハラスメント
これは、労働者が性的な言動を拒否したり抵抗したりしたことの「対価」として、解雇、降格、減給、契約更新の拒否といった不利益な取扱いを受けることです。
典型例:
- 上司が部下に交際を申し込み、断られたことを理由に人事評価を不当に下げる
- 性的な関係を求め、拒否されたことを理由に配置転換や契約更新を拒否する
これは「取引」の構造を持つ、極めて悪質なハラスメントです。権力関係を悪用した、許し難い行為と言えるでしょう。
2. 環境型セクシュアルハラスメント
これは、性的な言動によって労働者の就業環境が不快なものとなり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、見過ごせない程度の支障が生じることです。
典型例:
- 職場に水着姿の女性のポスターが貼られている
- 性的な冗談や下ネタが日常的に飛び交っている
- 身体的特徴について性的な発言がなされる
- 性的な経験について質問される
特定の個人に直接的な不利益を与えなくとも、職場の「空気」そのものを害する行為もセクハラに該当するのです。
また、セクハラは性別を問いません。男性が被害者となるケース、同性間で発生するケースも当然含まれます。「セクハラは男性から女性へのもの」という固定観念は、今や完全に時代遅れです。
妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント—— 制度利用への不利益取扱い
通称「マタニティハラスメント(マタハラ)」「パタニティハラスメント(パタハラ)」と呼ばれるもので、育児・介護休業法第25条に基づき、事業主に防止措置義務が課されています4。
法律(指針)では、「**職場において行われる、上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用に関する言動)**により、妊娠・出産した女性労働者や育児休業等を申し出・取得した男女労働者の就業環境が害されること」と定義されています。
このハラスメントも、その態様によって2つの類型に分けられます。
1. 制度等の利用への嫌がらせ型
産前産後休業、育児休業、時短勤務、子の看護休暇など、法律で認められた制度の利用を申し出たり利用したりしたことを理由とする嫌がらせです。
典型例:
- 「男のくせに育休なんて取るな。キャリアを諦める気か」
- 「時短勤務なら重要な仕事は任せられない。パート並みの扱いで十分だ」
- 「育休取得者のしわ寄せで残業が増えて迷惑だ」
2. 状態への嫌がらせ型
妊娠したこと、出産したことといった、労働者の生理的な「状態」そのものを理由とする嫌がらせです。
典型例:
- 「妊娠するなんて計画性がない。仕事に支障が出て困る」
- 「つわりなんて病気じゃない。甘えだ」
- 「また妊娠?会社を何だと思ってるんだ」
重要なのは、これらの言動が、たとえ業務上の必要性から発せられたものであっても、労働者の意に反し、就業環境を害するものであれば、ハラスメントに該当するという点です。
「人手不足で困っているから正直に話しただけ」という弁解は通用しません。制度利用は法的に保障された権利であり、それを理由とする不利益取扱いや嫌がらせは、明確な法律違反なのです。