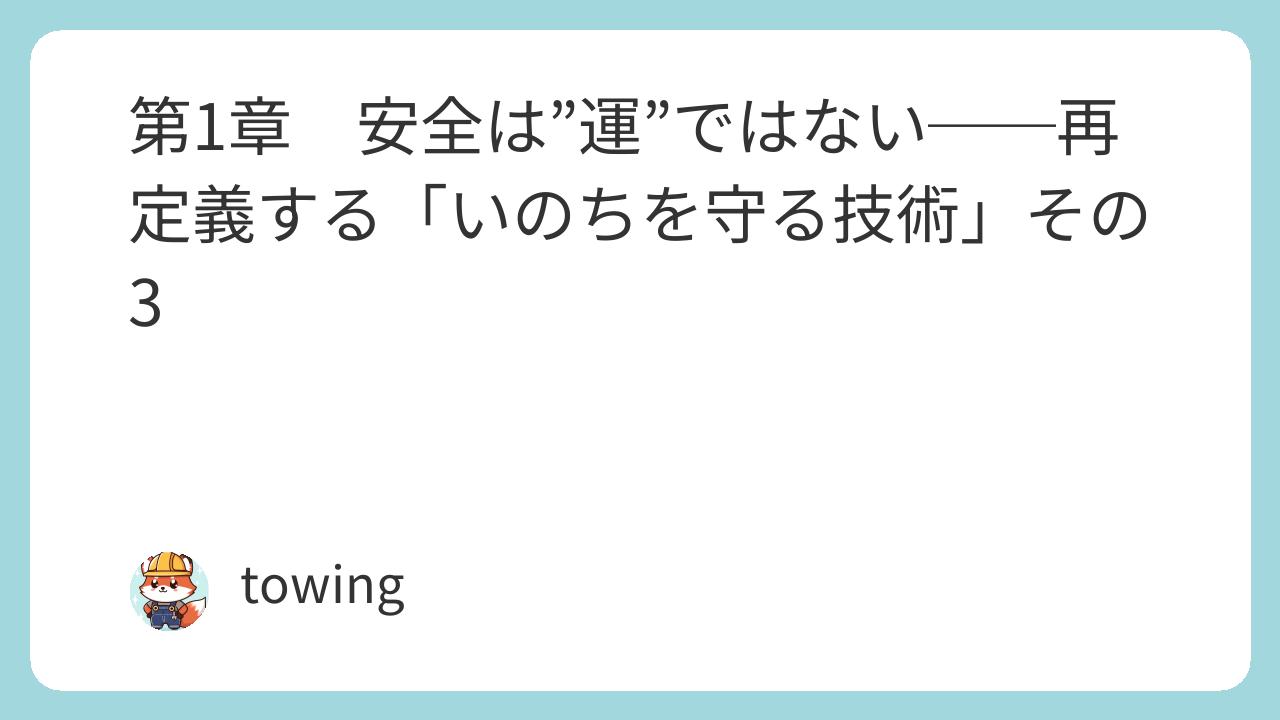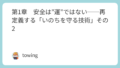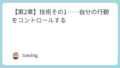現場は”技術”で安全になる
レヴィンの法則を理解すると、私たちが目指すべきは、望ましい行動を支える環境(E)、すなわち『しくみ』を作ることだとわかります。
この『しくみ』を設計し、現場に導入し、継続的に改善していく一連の活動こそが、本書で提案する「いのちを守る技術」です。なぜ、これをあえて「技術」と呼ぶのか。それには3つのはっきりした理由があります。
- 再現性があるから
「技術」というのは、特定の個人の才能やカリスマに頼らず、正しい手順と原理を学べば誰でも実践できるものです。この本で紹介するのは、あなたの現場で、あなたのチームで実際に使える具体的な方法です。
「あの職長がいるから現場が安全だ」というのは、その人に依存した管理であって、技術とは言えません。でも「なぜ、その職長の現場が安全なのか」を分析して、その要因を他の現場でも実現できる『しくみ』として整理すれば、それは組織の財産となる立派な技術になります。
- 学習可能であるから
技術は学んで練習すれば、必ず上達します。この本で解説する12の技術を現場で試して、失敗と成功を繰り返すことで、あなたの「安全スキル」は着実に向上し、それは一生使える専門性になります。
安全管理を「センス」や「長年の経験」といった曖昧な言葉で片付けるのではなく、明確な理論と手法に基づいた学習可能なスキルとして捉え直すこと。それが、あなた自信と組織全体の安全レベルを着実に底上げできるのです。
- 体系化できるから
優れた技術は、要素に分けて体系的に理解できます。この本では「いのちを守る技術」を12の要素に分けて説明します。これらはバラバラの精神論ではなく、行動科学や心理学といった科学的な根拠に基づいた、互いに関連し合う技術体系なのです。
例えば「コミュニケーション技術」と「記録の技術」は、それぞれ独立した技術でありながら、組み合わせることで「現場の危険情報を効果的に共有し、組織の記憶として蓄積する技術」として機能します。このような技術の組み合わせと応用によって、あなたの現場特有の課題に対する最適解をあなた自身で見つけ出すことができるのです。
「安全は”運”でも”気合い”でもなかった。安全は、学んで実践できる”技術”だったんだ」
この章を読み終えたあなたが、そう感じてくださることが私の一番の願いです。
新しい安全管理への招待
さあ、もう「気をつけろ」と叫ぶだけの安全管理とはお別れしましょう。
不安全行動をした個人を責めるのではなく、その行動を引き起こした『しくみ』に目を向ける。そして、科学的な根拠に基づいた「技術」を武器に、誰一人ケガをすることのない現場を、あなたの手で創り上げていきましょう。
私が長年の現場指導で痛感してきたのは、「安全への思い」だけでは現場は変わらないという現実です。でも、正しい技術とそれを支える『しくみ』があれば、現場は必ず変わります。それも、驚くほど劇的に変わります。
次の章からは、この「いのちを守る技術」の具体的な中身に、一つずつ踏み込んでいきます。理論だけでなく、明日からあなたの現場で実践できる具体的な手法を、事例と一緒にお伝えしていきます。