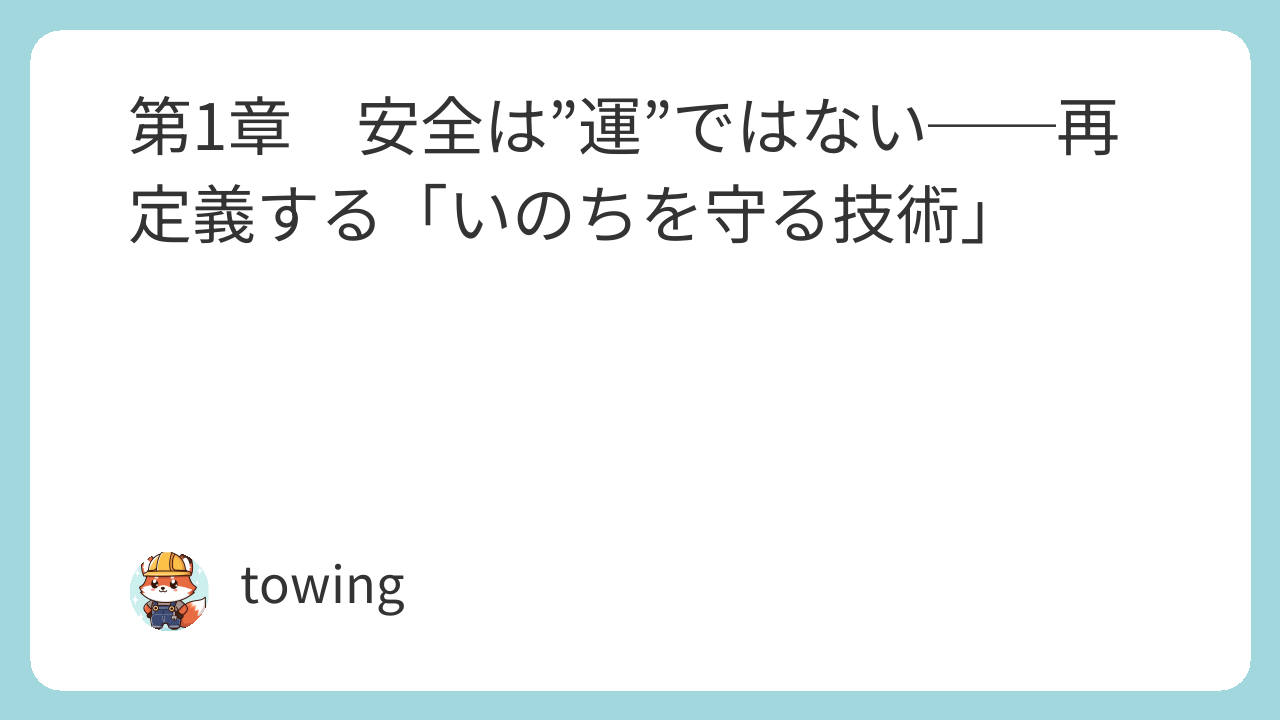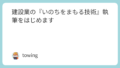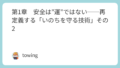「安全」は”気をつける”ことでは守れない
「今日も一日、ご安全に!」
私たちは毎朝、この言葉を交わしながら現場に向かいます。入り口の「安全第一」の看板を見上げ、KY活動で危険を話し合う。自分の命、そして大切な仲間の命を守るために、本当に真剣に取り組んでいるつもりです。
でも、現実はどうでしょうか。
あんなに「安全第一」って誓ったのに、ヒヤッとする瞬間が、まるで現場の日常風景みたいになっていませんか。「まあ、これくらいなら大丈夫でしょう」という、慣れから生まれる油断。いつものやり方だから問題ないという思い込み。そのちょっとした心の隙が、取り返しのつかない事故につながる可能性がある。その怖さを、私たちは身に染みて知っているはずです。
労働災害の統計を見れば、建設業の事故が減らない現実が冷たい数字として突きつけられます。災害報告書には、原因として「不安全行動」や「安全意識の欠如」といった言葉が、まるでテンプレートのように並んでいる。そして対策といえば、いつも「安全教育の徹底」「注意喚起の強化」といった、個人の意識に頼るものばかりです。
「もっと注意しろ」「集中しろ」「気を抜くな」
私たちはこれまで、何度もそう言われてきました。そして、同じことを後輩や部下に言ってきた。でも、正直に考えてみてください。本当にそれだけで、現場から事故をなくせるのでしょうか。
答えははっきりしています。「No」です。
個人の注意力、いわゆる”気をつける”ことだけに頼る安全管理は、もう限界なんです。なぜかって?それは、私たち人間が、そもそも
「いつでも完璧に注意し続ける」ようにはできていない
からです。
心理学の研究でも明らかになっていますが、人間の注意力には限界があります。どんなに優秀で責任感の強い人でも、集中力は永遠には続かない。体調が悪い日もあれば、プライベートな悩み事で頭がいっぱいになる時もあるでしょう。慣れた作業ほど、無意識に手順を飛ばしてしまったり、うっかり何かを忘れてしまったりする。こういうヒューマンエラーは、ダメな人にだけ起こることじゃなく、私たち全員に起こりうることなんです。
災害報告書に「本人の不注意」と書くのは簡単です。でも、その一言で片付けてしまっうのは、考えるのをやめているのと同じ。それは、事故の責任を個人の問題として押し付けて、「運が悪かった」で終わらせているようなものです。本当に向き合うべきは、
「なぜ、その人は不注意になってしまったのか」
という、もっと根本的な問題なんです。
「気をつけろ」という言葉は、確かに便利です。言った側は指導した気になるし、言われた側は反発するか、なんとなく憂うつな気持ちになるだけ。具体的な行動の変化には、なかなかつながらないのが現実です。
もし安全が個人の心がけだけで守れるなら、労働災害なんて、とうの昔にこの世からなくなっているはずです。私たちは、個人を責める文化から抜け出して、個人がミスを起こすことを想定していなかった「現場のあり方そのもの」に、目を向けなければなりません。
本書では、「”気をつける”ことに頼る安全管理」からの脱却を強く提案します。安全は、根性や運といった曖昧なもので左右されるのではなく、私たちが意図的に設計し、築き上げることができる「技術」なのです。