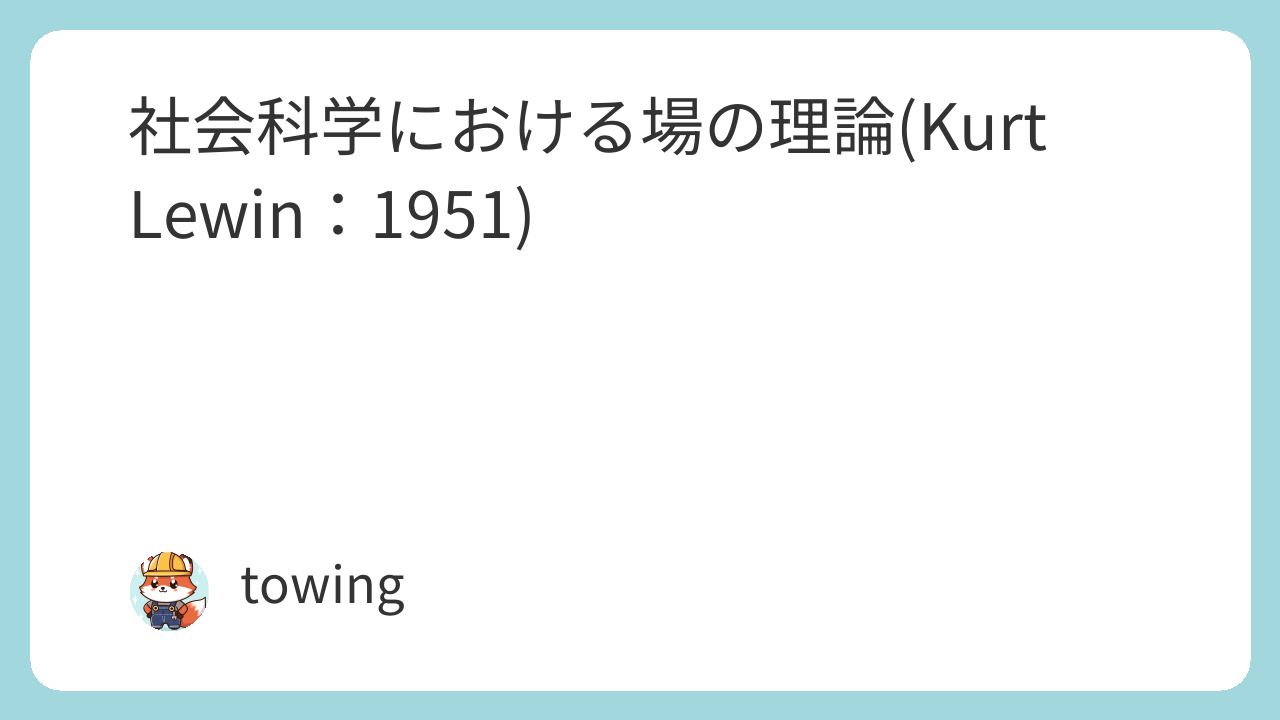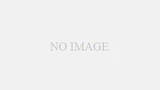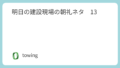レヴィンの「場の理論」を労働災害防止に活かす──行動科学で安全を設計する
「安全に作業してください」と声をかけるだけでは、現場の事故は防げません。
では、人はなぜ危険な行動をとってしまうのか。どうすれば安全行動を“自然にとれる”環境をつくれるのか。
そのヒントを与えてくれるのが、心理学者クルト・レヴィンが提唱した「場の理論(Field Theory)」です。
レヴィンは、人間の行動を「個人と環境との相互作用」として捉えました。これは単なる心理学の理論にとどまらず、職場の安全管理に応用できる非常に実践的な考え方でもあります。
ここでは、労働災害防止に役立つ「場の理論」の7つの概念を整理しながら、現場でどう活かせるかを考えていきます。
1. 行動は「場」の機能である
レヴィンの基本原則は「行動は、その時点の『場』によって決まる」というものです。
「場」とは、個人の心理状態(疲労、知識、スキル、不安など)と、職場環境(安全文化、ルール、人間関係、設備、作業プレッシャーなど)の総体です。
つまり、ある作業員が危険行動をとったとき、それは「本人の不注意」だけではなく、生活空間全体が生み出した結果なのです。
2. 同時性の原則──「今の場」が行動を決める
レヴィンは「過去の出来事は直接行動を決めない。行動は常に“今の場”の特性に左右される」と述べています。
例えば、「去年事故を起こしたから気をつけよう」だけでは不十分です。重要なのは、現在の疲労度、納期プレッシャー、新しい設備や人間関係の影響を分析すること。
「いま、この瞬間の場」に働きかけることが事故防止のカギになります。
3. 相互依存性──職場の要素はすべてつながっている
新しい機械を導入すると、作業員のスキルや負担が変わり、作業手順やチームのコミュニケーションにも影響が及びます。
場の理論は「生活空間の要素は相互依存している」と考えます。
つまり、安全管理は設備だけでなく、人・ルール・文化の全体を見渡すことが求められるのです。
4. 緊張システムと力──安全と危険のせめぎ合い
作業者の頭の中には「早く作業を終わらせたい」という力と「安全規則を守らなければ」という力が同時に働きます。
この葛藤(緊張システム)が解消されないまま進むと、事故につながりやすくなります。
安全を促すには、「危険行動を生む力を弱める」「安全行動を強める」工夫が必要です。
例えば、納期短縮のプレッシャーを和らげる仕組みや、安全行動を評価する制度が効果的です。
5. 概念の構築と形式化──安全を“見える化”する
レヴィンは「心理学も科学として概念を測定可能にすべきだ」と主張しました。
安全管理に置き換えると、「安全意識」を単なる抽象的な言葉にせず、ヒヤリハット報告数や安全会議参加率といった具体的な指標に変えることが重要です。
そうすることで、安全文化を数値で追跡でき、改善も科学的に行えるようになります。
6. 学習と分化──危険を細かく見分ける力を育てる
学習とは、生活空間の「分化」を進めること。
たとえば、新人作業員が「足場は危ない」と漠然と思っている段階から、「この場所の支柱は揺れやすい」「この高さでは必ずフルハーネスが必要だ」と具体的に判断できるようになることです。
安全教育の目的は、知識の暗記ではなく、危険を細かく識別し、安全な迂回路を選べる力を育てることにあります。
7. 心理的生態学──「安全の門番」の存在
食習慣の研究から生まれた「門番(gatekeeper)」という概念は、安全管理にも応用できます。
現場監督やベテラン作業員は、安全情報やルールの流れをコントロールする「安全の門番」です。
この「門番」が安全を軽視すれば、現場全体に危険行動が広がります。逆に、門番が安全の重要性を強調すれば、現場文化も自然と変わっていきます。
まとめ──安全は「場」を変えることで実現できる
レヴィンの場の理論を労働災害防止に応用すると、次の視点が得られます。
- 行動は「個人と環境の相互作用」で決まる
- 過去ではなく「今の場」に介入することが重要
- 危険行動を誘発する力を弱め、安全行動を強める仕組みづくり
- 安全を抽象概念でなく“測定可能な行動”として定義する
- 教育で危険を細かく見分け、安全な選択をできる力を育む
- 「安全の門番」を特定し、その役割を強化する
安全は「人に気をつけさせる」ことではなく、「場をデザインすること」で実現します。
レヴィンの理論は、そのための羅針盤となりうるのです。
——————————————————————————–
論文タイトル(日本題):社会科学における場の理論
著者:クルト・レヴィン (Kurt Lewin)
発行年:1951年