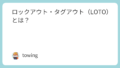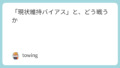現場で繰り返される重篤災害には、共通する特徴があります。
その一つが、「動いている機械に触れる」という危険な行動です。
製造業では、作業効率を優先してスイッチを切らずにメンテナンスを行う場面が後を絶ちません。
機械を止めずに触る癖をなくすには、正しい順番で意識と行動を変えていく必要があります。
危険に気づく感覚を養う
現場での事故の多くは、「まさか自分が」という油断から起こります。
まずはその感覚を揺さぶり、安全への感度を高めます。
- 同業種で実際に起きた事故の映像を視聴
- 通電中にメンテナンスしていた場面の写真展示
- グループ討議で「止めなかった理由」を言語化
事故の当事者と自分との違いは存在しません。
他人事の危険を、自分事へ変えていきます。
機械停止を「個人判断」にしない
ルールがあいまいなままでは、誰も止めません。
判断の責任を個人に押しつけない仕組みを作ります。
- 「止める・遮断する・確認する」の基本動作を明文化
- 作業手順書に「停止確認欄」を追加
- ロックアウト・タグアウト(LOTO)の基本操作を共有
「止めること」が仕事の一部だと全員が認識することで、迷いがなくなります。
実機で安全手順を体にしみこませる
頭で理解しても、手が勝手に動けば意味がありません。
現場では、身体で覚えることが何よりの安全対策になります。
- 模擬設備を使って停止→点検→復旧の流れを実演
- 非常停止ボタンの位置を全員で確認
- 「電源が落ちたふり」訓練で反射的な動きを点検
繰り返し練習することで、条件反射のレベルまで高めましょう。
現場全体でルールを“見える化”する
誰かの習慣ではなく、現場全体のルールにする必要があります。
仕組みが支えることで、安全行動は継続します。
- 点検中は札やフラッグで「作業中」を表示
- 電源遮断後に「確認サイン」を出すルールを導入
- 作業ごとの手順書に赤字で停止動作を記載
判断の余地をなくす設計が、事故の芽を摘み取ります。
安全行動を「評価」して定着させる
叱られて覚える安全には限界があります。
良い行動に光を当て、続けたくなる仕掛けを用意します。
- 機械を止めてから作業した報告を毎月表彰
- 「止めてよかった体験」を共有する掲示板を設置
- ヒヤリ報告にポイントを付けてインセンティブ化
止める人が正しく評価されれば、風土が変わり始めます。
管理者が“起こる前”にチェックする
ルールは整えても、管理の目がなければ元に戻ります。
日々の巡視と観察で、危険の兆候をつかみましょう。
- 抜き打ちでの「通電作業チェック」項目を設定
- 日報や報告書に「停止確認」の記入欄を追加
- 停止手順を守らなかった場合の是正ルールを徹底
気づいた段階での介入が、最悪の事態を防ぎます。
機械を止めてから作業する現場を目指す
「止めてから触る」は、個人の意識だけで守れません。
教育、訓練、仕組み、評価、管理という5つの柱がそろって初めて、安全な職場が築かれます。
機械を止めることを、例外ではなく“当たり前”にしていきましょう。