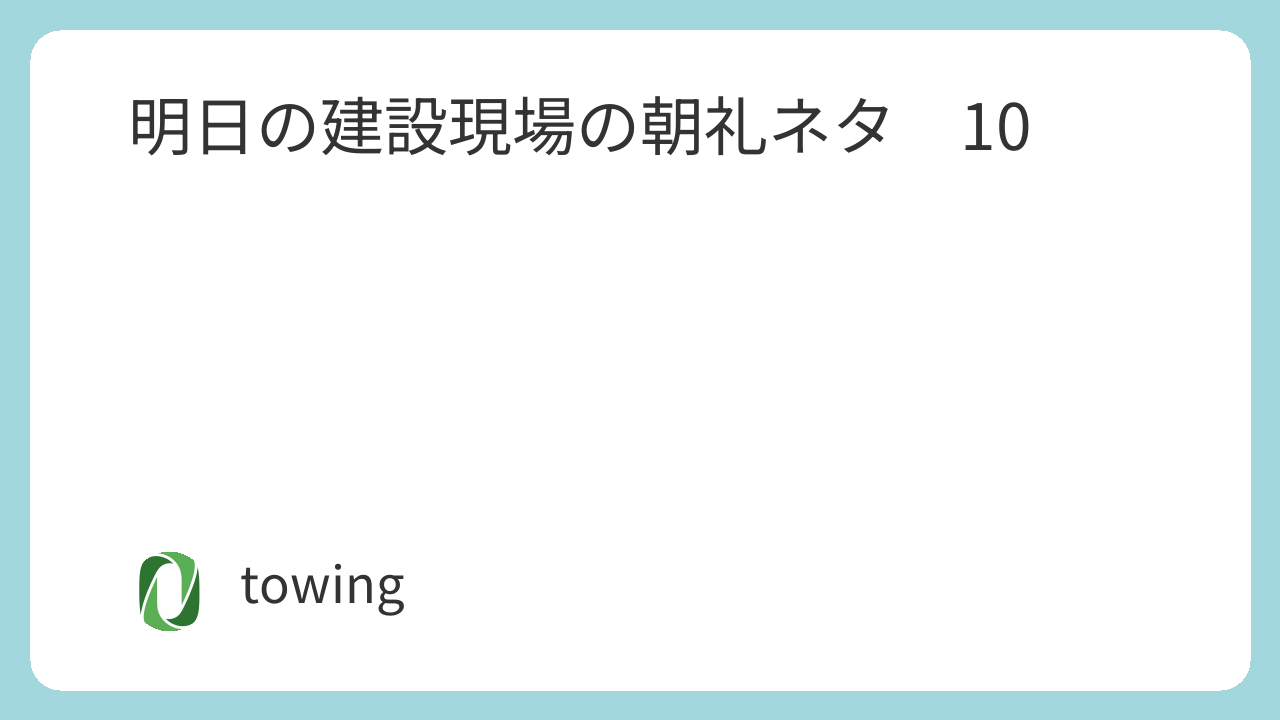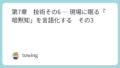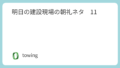建設現場朝礼安全講話集
【土木工事向け】港湾荷役事故に学ぶ「重心」と「固縛」の重要性
皆さん、おはようございます!
今朝は、ちょっと違った角度から安全について話をしたいと思います。先日、海外の港で起きた事故の話なんですが、これが私たちにとって他人事じゃないんです。
大型クレーンがコンテナを船に積み込む作業中、コンテナがバランスを崩して落下し、周りの作業員が危険にさらされる事故が起きました¹。映像を見ていて、本当にゾッとしましたよ。
何が原因だったか?コンテナの中身の偏り、つまり「重心」の管理が甘かったこと。そして、吊り上げるワイヤーの「固縛」が不完全だったことです。
「港のコンテナなんて関係ないじゃないか」って思いますか?違うんです。これ、まさに私たちの現場で毎日やってる作業と同じなんです。
私たちだって、ヒューム管やボックスカルバート、大型の鋼材を日常的にクレーンで吊り上げてますよね。その時、ただ吊り上げれば良いって思ってませんか?
現場で見落としがちな重要ポイント
私が現場で見ていて気になるのは、こんな場面です:
- その吊り荷、本当に重心は安定してますか?
- ワイヤーやシャックル、スリングの選定と固縛は、本当に万全ですか?
- 吊り荷が回転したり、揺れたりする可能性を予測してますか?
コンテナも、私たちが扱うコンクリート製品も、見た目は同じような「箱」や「筒」に見えます。でも、その中身や形状によって重心は全然違うんです。
重心を無視した玉掛けは、吊り上げた瞬間に荷が傾いて、落下する大事故に直結します。これは脅しじゃありません。現実に起こりうることです。
今日から実践してほしい3つのこと
そこで、皆さんに徹底してもらいたいのが「玉掛け作業前の再確認」です。
- 吊り荷の正確な把握
形状と重量を正確に把握し、重心の位置を予測する。「だいたい」じゃダメです。 - 適切な吊り点の選定
重心を考慮して、吊り点とワイヤーの長さを適切に選ぶ。経験だけに頼らず、計算も大切です。 - 地切り確認の徹底
吊り上げる前には、必ず地切り(少しだけ吊り上げて安定性を確認)を行う。この一手間を絶対に省かない。
全員参加の安全管理
玉掛けは資格を持った人がやる専門作業ですが、周りの作業員も無関係じゃありません。
吊り荷の下には絶対に入らない。これは基本中の基本です。
そして、玉掛け作業に少しでも不安な点があれば、遠慮なく「本当に大丈夫か?」って声をかけてください。その一言が、チーム全体の安全意識を高めるんです。
「うるさいやつだな」って思われても構いません。事故が起きてからでは遅いんです。
基本に立ち返ろう
重量物の取り扱いは、一歩間違えれば即座に重大災害につながります。
「いつものことだから」「今まで大丈夫だったから」。この慣れが一番危険です。
基本に立ち返って、慎重すぎるくらい慎重に作業を進めましょう。それが、皆さんと皆さんの家族を守ることにつながるんです。
今日も一日、ご安全に!
【建設工事向け】食品工場の火災から学ぶ「可燃性ガス」の恐怖
皆さん、おはようございます!
今日は、火災について話をしたいと思います。先日、ある食品工場で大変な事故がありました。パンを焼くオーブンから発生したガスが原因とみられる爆発火災です²。幸い死者は出ませんでしたが、工場は大きな被害を受けました。
「パン工場の話が、なぜ建設現場で関係あるんだ?」って思いますよね。
でも、この事故は私たちに「目に見えない可燃性ガス」の恐ろしさを教えてくれるんです。
建設現場に潜む見えない危険
私たちの現場、特に内装工事や改修工事の現場を思い出してください。
- 接着剤や塗料を使う時の、あのツンとした有機溶剤の臭い
- 防水工事で使う、ウレタンやプライマーの強烈な臭い
- スプレー缶タイプの断熱材や補修材
これら全部、空気中に可燃性のガスを放出してるんです。
窓を閉め切った室内で作業してると、気づかないうちに室内にガスが充満する。そこに電動工具の火花、静電気、誰かが吸うタバコの火。ほんの小さな火種で爆発・火災を引き起こす危険があるんです。
慣れが生む落とし穴
食品工場の事故も、おそらく換気が不十分だったんでしょう。「いつもの作業だから」という慣れが、危険な状況を生み出してしまった。
私たちも同じです。毎日使ってる材料だから、毎日嗅いでる臭いだから、つい「大丈夫だろう」って思いがちです。
でも、それが一番危険なんです。
今日から実践する3つの鉄則
そこで、皆さんに徹底してもらいたいのが「換気の徹底」と「火気管理の再確認」です。
- 十分な換気の確保
有機溶剤を含む材料を使う時は、必ず窓やドアを開ける。送風機を回すなど、とにかく風の流れを作る。「ちょっとくらい」は禁物です。 - 明確な火気管理
作業場所の周辺では、動火作業(火気使用作業)を厳禁とする。そして、その旨を誰が見てもわかるように掲示する。 - ガス濃度の定期測定
作業中は、ガス検知器で空気中の可燃性ガス濃度を定期的に測る。数値で確認することが大切です。
見えない危険との戦い
臭いに慣れてしまうと、危険な濃度になっても気づかないんです。鼻は嘘をつきます。
危険は「目に見えない」「臭いに慣れる」という形で、私たちのすぐそばまで迫ってきます。それを忘れちゃいけません。
現場全体での意識共有
自分たちの作業が火種を生んでないか。周りの作業で可燃性ガスが発生してないか。
常に広い視野で現場全体を見渡して、火災・爆発のリスクを全員で管理していきましょう。
一人の油断が、現場全体の災害につながります。でも、一人の気づきが、現場全体を救うこともあるんです。
今日も一日、ご安全に!
引用・参考文献
- 港湾荷役作業における重大事故事例(労働災害データベースより)
- 食品工場における爆発・火災事故事例(消防庁・事故事例データベースより)