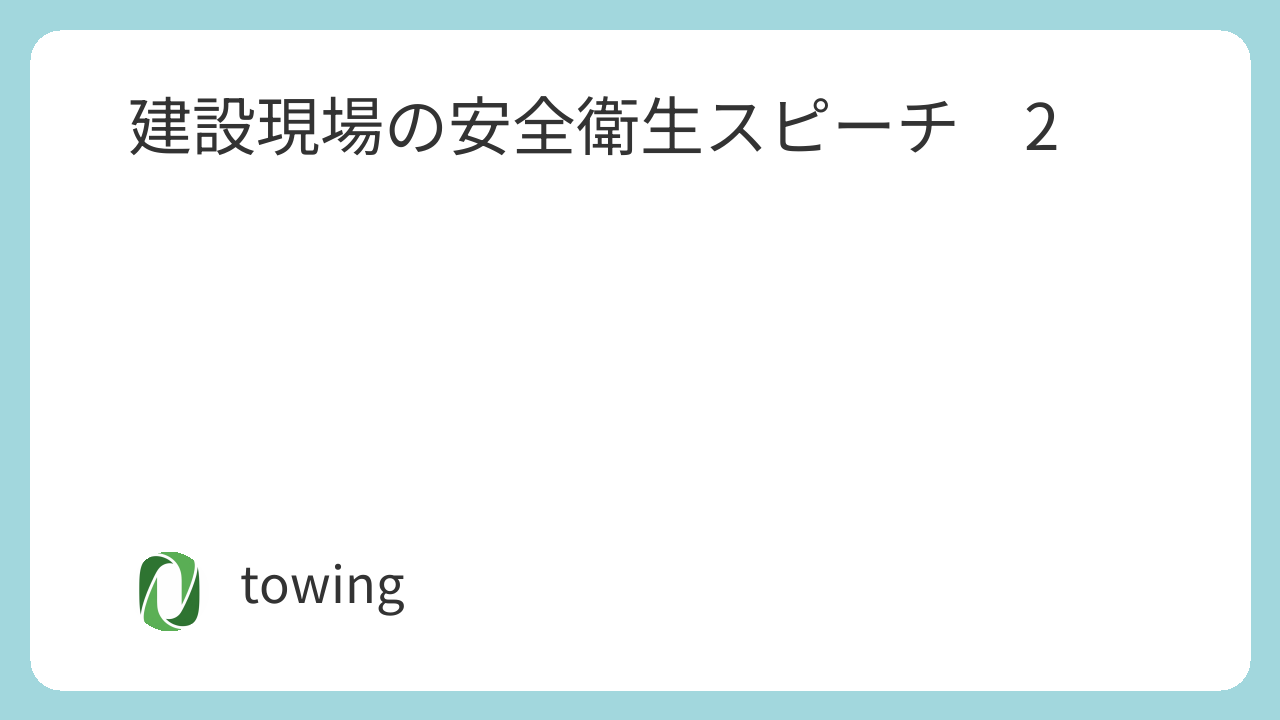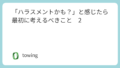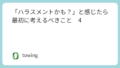建設現場朝礼用安全講話
ミキシングプラント事故を教訓とした安全作業について
皆さん、おはようございます!
今朝は少し重たい話になりますが、私たちの安全に直結する大切な内容です。最後までしっかりと聞いてください。
先日、とある地盤改良工事の現場で起きたミキシングプラント事故について、皆さんと一緒に考えてみたいと思います。この事故は、決して他人事ではありません。明日は我が身かもしれないのです。
事故の概要
地盤改良工事を行っていた現場でのことです。作業員の方がミキシングプラントのドラム内を清掃していました。いつものように、終業前の清掃作業でした。
ところが突然、止まっているはずの攪拌翼が動き出したのです。作業員の方は攪拌翼に巻き込まれてしまいました。
幸い、命に別状はありませんでした。しかし、一歩間違えれば取り返しのつかない大事故になっていたでしょう。私たちは、この「もしも」を真剣に受け止めなければなりません。
なぜこの事故が起きたのか
事故というのは、一つの原因だけで起きることは稀です。いくつもの要因が重なって、最悪の結果を招くのです。今回の事故も例外ではありません。
1. 作業手順が決まっていなかった
清掃作業について、きちんとした手順書がありませんでした。「いつものように」「なんとなく」で作業をしていたのです。これでは安全を確保できません。
2. 電源を切らずに作業していた
清掃に入る前に、機械の電源を切っていませんでした。スイッチが入ったままの状態で、ドラム内に入ってしまったのです。これは非常に危険な行為です。
3. 安全装置が不十分だった
誤って機械が動かないようにする「ロックアウトキー」が操作盤についていませんでした。電源を切っても、誰かが間違ってスイッチを入れてしまう可能性があったのです。
4. ボタンの見分けがつかなかった
これが今回の直接的な原因です。貯水槽の水を抜くポンプのボタンと、攪拌翼を動かすボタンが同じ色、同じ形で並んでいました。別の作業員が水を抜こうとして、間違って攪拌翼のボタンを押してしまったのです。
5. 教育が行き届いていなかった
電源を切ることの重要性や、ロックアウトの方法について、作業員への指導が不十分でした。知らなければ、安全な作業はできません。
私たちが今すぐできること
この事故を教訓に、私たちの現場では以下の対策を徹底します。皆さん一人ひとりが意識してください。
1. 作業手順書の作成と教育
危険を伴う機械の清掃や点検については、必ず詳細な作業手順書を作ります。そして、全員がその手順を理解し、実践できるまで繰り返し教育を行います。
手順書は難しい言葉で書きません。誰が読んでもわかるように、シンプルで具体的な内容にします。
2. ロックアウト方式の完全実施
機械の清掃や点検を行う際は、必ず以下の手順を踏んでください:
- 電源を完全に切る
- プラグをコンセントから抜く
- ロックアウトキーで施錠する
- 「清掃中・点検中」の表示を掲示する
これは私たち元請けだけでなく、協力会社の皆さんにも徹底していただきます。
3. 電源オフの習慣化
「機械に触る前には電源オフ」これを合言葉にしましょう。どんなに短時間の作業でも、どんなに慣れた機械でも、必ず電源を切ってから作業に入ってください。
4. 誤操作防止対策の強化
似たようなボタンは色を変える、ラベルを貼る、位置を離すなど、間違えようがない工夫をします。皆さんからも「これは紛らわしい」「間違えそうだ」という意見があれば、遠慮なく教えてください。
5. 継続的な安全教育
安全教育は一度やれば終わりではありません。定期的に、繰り返し行います。新しく入った方はもちろん、ベテランの方も含めて全員が対象です。
最後に
皆さん、事故は「まさか」の時に起きます。「自分は大丈夫」「いつものことだから」という油断が、取り返しのつかない結果を招くのです。
今回の事故では、幸い命は助かりました。しかし、その方のご家族はどれだけ心配されたでしょうか。私たちは、単に自分の身を守るだけでなく、家族や仲間の笑顔を守る責任があるのです。
小さな疑問でも、ちょっとした不安でも、遠慮せずに声を上げてください。「こんなこと言って恥ずかしい」なんて思わないでください。皆さんの一言が、大きな事故を防ぐことになるのです。
私たちは一つのチームです。全員で協力して、誰一人ケガをしない現場を作り上げましょう。
それでは今日も一日、ご安全に!
引用・参考文献
○ 厚生労働省「職場のあんぜんサイト」労働災害事例:ミキシングプラントのドラム内清掃中に攪拌翼に巻き込まれた