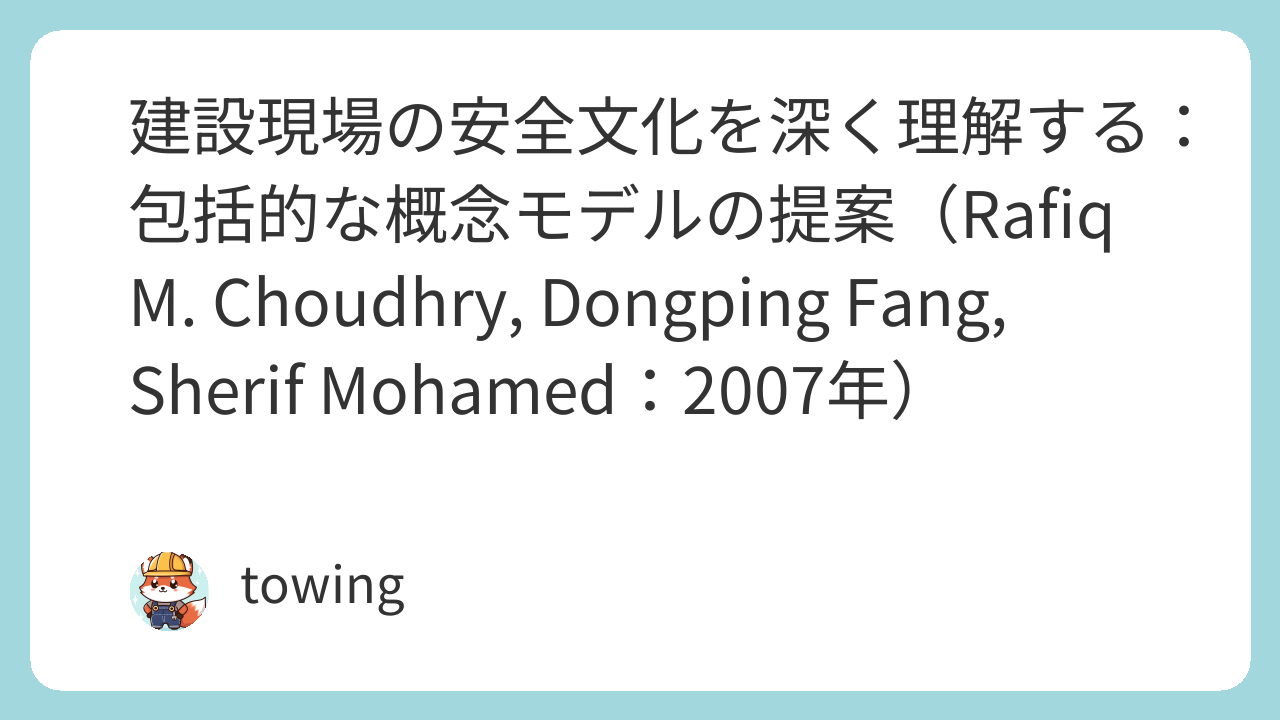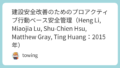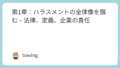建設現場の安全文化を深く理解する:包括的な概念モデルの提案
なぜ安全管理が機能しないのか?―見えない壁の正体
建設業界において、現場の安全性の向上が常に最優先事項であることは、皆さんもご承知の通りでしょう。
しかし、このような経験はありませんか?
安全規則は完備している。研修も実施している。それでも重大事故が発生してしまう。なぜ現場の安全意識が思うように向上しないのか。
実は、近年発生した多くの重大事故の背景調査において、安全管理システムが機能不全に陥る根本原因として「安全文化の欠如」が繰り返し指摘されているのです。
この「安全文化」という概念は比較的新しく、その多角的で複雑な性質から、建設現場での検証可能な分析プロセスが不足しているのが現状でした。
私は長年にわたり、数多くの建設現場で安全管理の指導を行ってまいりました。その経験から確信できるのは、真の安全向上には、目に見える対策だけでなく、現場に根付く「文化」そのものを変革する必要があるということです。
この記事では、建設現場における安全文化を包括的に捉え、その理解と向上を支援する堅牢な概念モデルについて、皆さんと共に深く掘り下げていきたいと思います。
安全文化とは何か?―その本質を理解する
安全文化という概念の誕生
「安全文化」という言葉が初めて世に出たのは、1986年のチェルノブイリ事故でした。INSAG(国際原子力安全諮問グループ)の報告書において導入されたのです。
当初はその意味が広く解釈され、個人の献身と説明責任を指していました。しかし、具体的な評価方法は示されていませんでした。
その後、ACSNI(原子力施設安全諮問委員会)がより具体的な定義を提示しました。
「組織の安全文化とは、個々人およびグループの価値観、態度、認識、能力、行動パターンが、組織の健康・安全管理へのコミットメントと、そのスタイルおよび熟練度を決定する産物である」
安全文化の核心的特徴
学術文献には多数の定義が存在しますが、共通する特徴があります。それは「人々が安全に関してどのように考え、どのように行動するか」に焦点を当てている点です。
定義は多様ですが、安全文化が安全に対する積極的(プロアクティブ)な姿勢であるという点については、ほぼ普遍的な合意が形成されています。
つまり、安全文化とは単なる規則の遵守ではなく、組織全体が自発的に安全を追求する風土なのです。
安全文化を構成する三つの柱―「みる・はかる・ととのえる」のフレームワーク
安全文化をより深く理解し、その実態を把握するためには、密接に関連する以下の三つの概念を理解することが不可欠です。これらは、今回提案されている建設安全文化モデルの主要な構成要素でもあります。
私はこれらを「みる・はかる・ととのえる」のフレームワークとして整理いたします。
1. 安全風土(Safety Climate)―現場の「空気」をみる
安全風土の本質
安全風土は、「従業員が自身の職場環境について共有する全体的な認識の要約」として定義されます。これは組織の安全管理システム(方針、慣行、手順など)について従業員が抱く認識を反映したものです。
分かりやすく表現するなら、「今、ここで私たちが物事を行うやり方」を示すスナップショットと言えるでしょう。
建設業界における特徴
建設業界では、以下のような区別がなされています。
- 安全文化:組織全体の安全管理能力(トップダウン)
- 安全風土:労働者の職場の安全に対する認識(ボトムアップ)
研究者たちは安全風土を安全文化のサブコンポーネントと見なしており、実際の安全文化の反映であると考えています。
安全風土調査の効果
安全風土調査は、従業員の安全知識を高め、モチベーションを提供し、安全活動への参加を促す上で非常に有効なツールです。現場の「見えない課題」を可視化することができるのです。
2. 行動ベース安全(Behavior-Based Safety – BBS)―安全行動をはかる
BBSの基本概念
BBSは、人間の行動に関する心理学的研究を体系的に応用するデータ駆動型のアプローチです。
注目すべき事実として、職場での事故やインシデントの80%以上が安全でない行動に起因するとされています。BBSは、この特定の安全関連行動を特定し、改善目標とすることに重点を置きます。
BBSプログラムの実施手順
BBSプログラムでは、以下のような段階的なアプローチを取ります。
- 観察とベースライン設定:労働者の行動を体系的に観察し、ベースラインスコアを設定
- 目標設定:労働者の参加を得て現実的で達成可能な目標を設定
- 行動促進:安全行動の実践を奨励
フィードバックの重要性
望ましい安全行動を強化し、継続的な改善を促すためには、フィードバックの提供が不可欠です。
BBSプログラムの出力は数値として示されるため、例えば86%や95%といったスコアにより、現場の安全行動の状況を従業員全員に明確に伝えることができます。
3. 安全システム(Safety System)―組織全体をととのえる
安全システムの包括的定義
安全システムは、組織の安全管理システムのすべての側面を含みます。具体的には安全方針、手順、委員会などです。
これは安全パフォーマンスの計画、実施、監視、レビューのための体系的なプロセスを提供するものです。重要な点は、単なる文書化に留まらず、プロセス、運用管理手順、慣行の実際の実施を意味することです。
建設安全システムの構成要素
建設安全システムには、以下の要素が含まれます。
- 安全方針と目標
- 安全基準と目標
- 作業の計画と組織化
- 実施と通常の運用慣行
- 監視、フィードバックと監査
- 是正措置
- レビューと継続的改善
実践的定義
著者らは安全システムを、「サイトの安全な運用を管理するためのすべての方針、目標、役割、責任、説明責任、規定、基準、コミュニケーション、プロセス、手順、ツール、データ、文書を含むもの」と定義しています。
プロジェクト固有のサイト安全計画は、環境的・状況的問題に積極的に対処するための重要なツールとなります。
建設安全文化の包括的モデル―三つの柱が織りなす相互作用
従来の安全測定の限界
従来の安全測定は、事故発生後の事後的な指標(事故率や補償費用など)に焦点を当てていました。これは「鍵のかかったドアを力ずくで開けようとするようなもの」で、根本的な解決には至りません。
近年はプロアクティブ(積極的)な先行指標の使用への転換が強く推奨されています。
社会認知理論に基づく概念モデル
この要請に応えるため、建設安全文化を客観的に分析し、向上させることを目指した堅牢な概念モデルが提案されています。
このモデルは、バンデューラ(Bandura, 1986)の社会認知理論に由来する「相互決定論」の概念を反映しています。この理論では、以下の三要素が互いに影響し合い、安全行動が形成されるとされます。
- 個人(Person)
- 行動(Behavior)
- 環境/状況(Environment/Situation)
提案された建設安全文化モデルの特徴
提案された建設安全文化モデルは、安全風土(個人)、行動ベース安全(行動)、安全システム(環境/状況)という三つの構成要素間の相互作用関係を認識しています。
このモデルの主な特徴は以下の通りです。
三つの関連概念の統合
安全風土、行動ベース安全、安全システムを統合することで、建設安全文化の異なる側面を個別に、または組み合わせて測定することが可能です。
多様な測定ツールの活用
単一の測定ツールに依存せず、調査、監査、フォーカスグループ、文書分析など、様々なツールに対応します。
プロジェクト固有の条件への対応
環境/状況の構成要素は、組織の状況的側面だけでなく、プロジェクトの特定の条件にも焦点を当てています。
多レベル分析の可能性
三つの構成要素が互いに補完し合い、三角測量による測定方法を提供することで、建設安全文化の多レベル分析を可能にします。
清華大学での研究応用事例―理論の実践的検証
実際の適用方法
清華大学での研究プロジェクトでは、この概念モデルが建設安全文化の全体的で多面的な性質を探求するための統合的フレームワークとして実際に活用されました。
具体的な測定方法は以下の通りです。
- 安全関連行動の測定:行動チェックリストを使用
- 従業員の認識測定:安全風土認識調査を実施
- 安全管理システムの検証:安全監査とインタビューを定期的に実施
得られた成果
初期の結果は、このモデルが建設プロジェクトにおける安全文化の全体的な理解を向上させるのに成功したことを示しています。
具体的な改善効果
- 質問票調査:従業員の安全意識を高め、安全風土を改善
- 現場安全監査:現場の安全向上を促進
- BBSプログラム:安全行動の増加を観察
この三つの構成要素は、すべての従業員が安全を自分事として捉えるための有効な手段を提供しました。
まとめ―安全文化向上への実践的アプローチ
建設現場における安全文化を客観的に分析するための体系的なアプローチが不足している中で、この包括的な概念モデルは重要な一歩となります。
従業員の認識、安全行動、環境的または状況的特徴を、安全風土調査、ピア観察、システム監査/検査を通じて評価することで、組織全体の安全パフォーマンスを向上させるための具体的な指針を提供することができるでしょう。
あなたの現場でも、この「みる・はかる・ととのえる」のフレームワークを活用し、真の安全文化を築いていきませんか。
安全文化の向上は一朝一夕には実現しません。しかし、体系的なアプローチと継続的な取り組みにより、必ず成果を得ることができるのです。
参考文献
- 論文タイトル(日本題):建設現場の安全文化を深く理解する:包括的な概念モデルの提案
- 著者:Rafiq M. Choudhry, Dongping Fang, Sherif Mohamed
- 発行年:2007年