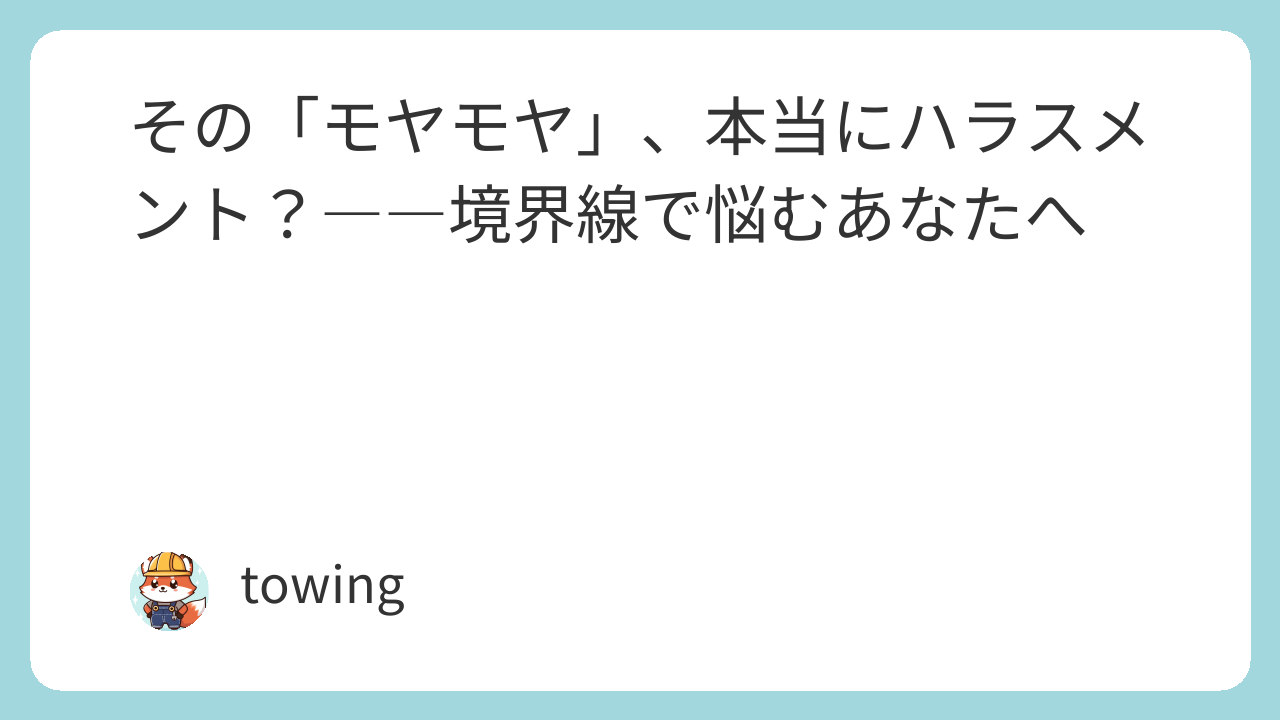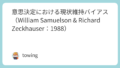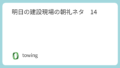はじめに:心の「モヤモヤ」に名前を与える前に
もし今このブログを読んでくださっているとしたら、きっとあなたの心の中には、言葉にしづらい「モヤモヤ」が渦巻いているのではないでしょうか。
- 「あの人の一言が、ずっと胸に引っかかっている」
- 「私の気にしすぎなのかもしれない…」
- 「不快に感じる自分は心が狭いのだろうか」
- 「誰も何も言わない。自分だけがおかしいのでは?」
そうやって自分を責めながら、一人で眠れない夜を過ごしてしまう。――これは、決して珍しいことではありません。
まず、はっきりお伝えしたいのは、その感情はあなたがおかしいからではないということ。そして、あなたは一人ではありません。
その胸の痛みや息苦しさは、心が「自分を守ってほしい」と送っている大切なサインです。無視せず、押し殺さず、きちんと耳を傾けてあげましょう。
「これはハラスメント?」と悩むときに大切な第一歩
私が相談を受けるとき、最も多いのは「これってハラスメントですか?」という質問です。
ただ、私はすぐに「はい/いいえ」と答えることはしません。なぜなら、本当に大切なのはラベルを貼ることよりも、あなたの感情を認めることだからです。
「嫌だ」「不快だ」「つらい」――それを感じた瞬間に「気のせいかも」「大げさかも」と打ち消す必要はありません。
その感情は、あなたにしかわからない「真実」です。
だからこそ第一歩は、社会のルールに当てはめて白黒をつけることではなく、自分の心に正直になることです。
「境界線」で悩む人が増えている背景
ここ数年、「ハラスメント」という言葉は世の中に広く浸透しました。それは人権意識の高まりを示す喜ばしい変化です。
しかし一方で、こんな声も増えています。
- 「部下に注意するのも怖い」
- 「どこまでがセーフで、どこからがアウトかわからない」
- 「不快と感じたら全部ハラスメントなの?」
なぜこれほど多くの人が「境界線」で悩むようになったのでしょうか。その背景には、現代社会の大きな変化が関係しています。
1. 働き方とコミュニケーションの変化
リモートワークの普及により、相手の表情や声色といった「非言語の情報」が失われました。メールやチャットの短いやり取りが、思いがけず冷たく、攻撃的に伝わってしまうこともあります。
2. 価値観の多様化
世代、性別、国籍、文化――バックグラウンドが異なる人々が同じ職場で働く時代です。ある人にとっては「励まし」が、別の人にとっては「パワハラ」と受け取られる。価値観のすれ違いは、今や避けられない現実です。
3. 「ハラスメント」という言葉の一人歩き
「〇〇ハラ」という言葉が乱立し、言葉だけが肥大化する一方で、本質を見失っている場面も見受けられます。「何でもハラスメントと言われてしまう」と萎縮する管理職もいれば、「少しでも不快ならハラスメントだ」と断罪する風潮もあります。
あなたが悩むのは「弱さ」ではなく「誠実さ」の証
こうした状況の中で、私たちは皆、手探りで適切な距離感を模索しています。
だからこそ、あなたが「境界線」で悩むのは、決して弱さでも神経質でもありません。むしろ、複雑な時代を真剣に生きている証拠なのです。