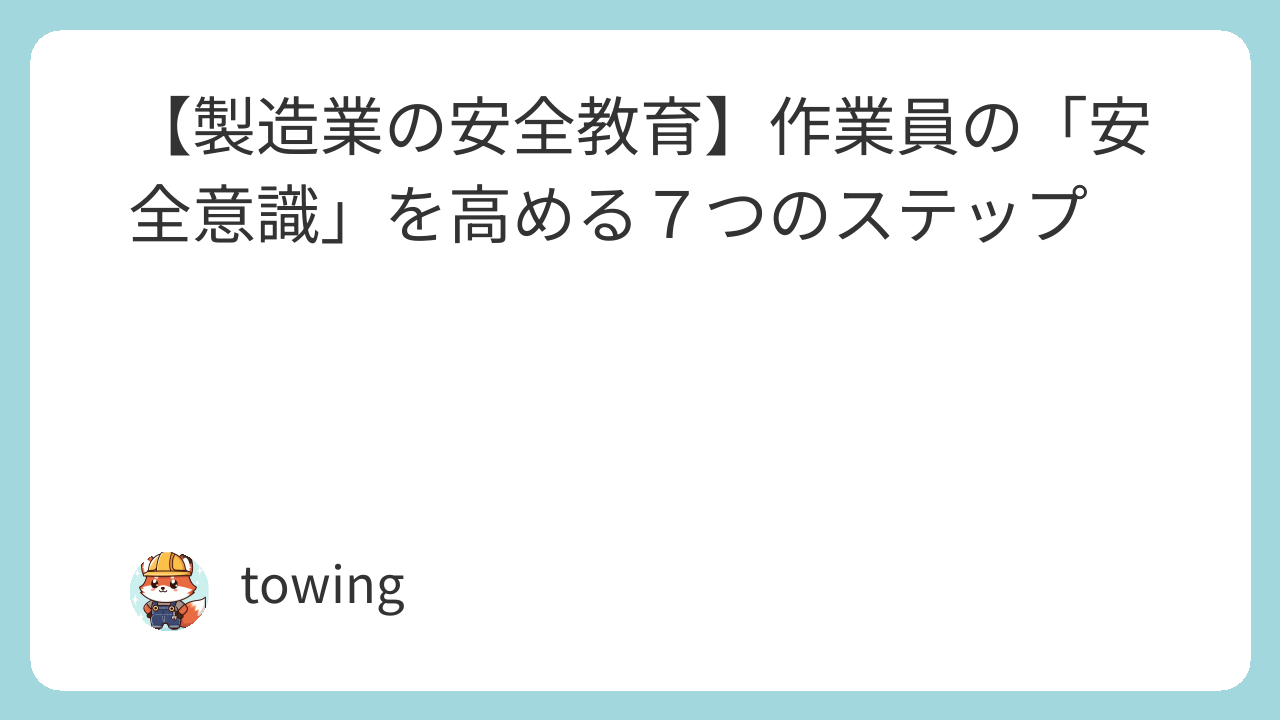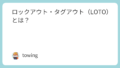──“やらせる”から“やりたくなる”へ、安全文化を育てる方法
現場で「気をつけろ」と何度言っても事故がなくならない。
注意喚起だけでは、人は動かないし、続きません。
ではどうするか──答えは「段階的に、安全意識を育てること」です。
今回は、製造業の現場で使える「安全意識を高める7つのステップ」をご紹介します。
ステップ① まず“見える化”──危険を「気づける」状態にする
現場で起こる事故の多くは、「気づかなかった」ことが原因です。
最初に取り組むべきは、危険を“見える化”すること。
- 危険箇所に目立つ標識や色分けをする
- ヒヤリハットの写真を掲示する
- 「ここが危ない!」を共有するパトロールを習慣にする
無意識のままでは、安全意識は育ちません。
ステップ② “話し合う”ことで気づきを自分ごとに
次に必要なのは、「自分のこととして」危険をとらえる仕掛けです。
朝礼やチームミーティングでの一言共有だけでも変わります。
- 「昨日のヒヤリ」を毎日ひとこと話す
- 作業前に全員でKY活動(危険予知)
- 安全に関する“つぶやき”を壁新聞にまとめる
他人のヒヤリは、自分の気づきになります。
ステップ③ 「知ってる」だけでなく「なぜ必要か」を伝える教育
教育は大切ですが、「知識だけ」では行動は変わりません。
特に若手には「納得」が必要です。
- 過去の災害事例を映像で見せる
- 実際の作業場所でリアルに体験させる
- 「守らないと、どうなるか」を当事者の視点で伝える
目的が伝われば、安全ルールは“やらされ感”から脱却します。
ステップ④ “やりたくなる”環境を設計する
安全行動が面倒だと、誰も続きません。
ならば、行動そのものを「やりやすく」してしまいましょう。
- 保護具は使いやすく、かっこよく
- チェック表は簡単で使いやすく
- 作業手順は図と色で一目でわかるように
安全は“根性論”ではなく“デザイン”です。
ステップ⑤ 続ける“しくみ”で習慣にする
一度変わった行動も、放っておけば元に戻ります。
だから、続ける“しくみ”が必要です。
- 毎週の安全ミーティングで、現場の声を拾う
- 持ち回りで安全リーダーを経験する
- 作業の前後で必ず安全チェックを行うペア活動
習慣になるまでが“勝負”です。
ステップ⑥ “褒める文化”をつくる
「怒られるからやる」のでは長続きしません。
「褒められるからやる」に変えましょう。
- 改善提案やヒヤリ報告にポイント制度
- 毎月の安全表彰をチーム単位で実施
- 安全ポスターや標語を現場から募集
人は、“見られている”ときに、一番がんばれます。
ステップ⑦ 組織として“文化”にする
最後に、安全を一時的なスローガンではなく、会社の文化に昇華させます。
- 安全衛生委員会を形式で終わらせず、全員に見えるようにする
- 外部の安全専門家による定期点検を導入
- 誰でも「作業を止められる」制度をつくる
“言える”風土が、事故を未然に防ぎます。
安全意識は、一朝一夕では育たない。
でも、正しい順番で、現場と一緒に進めれば、
必ず「安全が当たり前」の職場に近づいていきます。
「注意しろ」ではなく、「仕組みで変える」。
それが、OFFICE SAFE WORKの目指す“安全文化づくり”です。