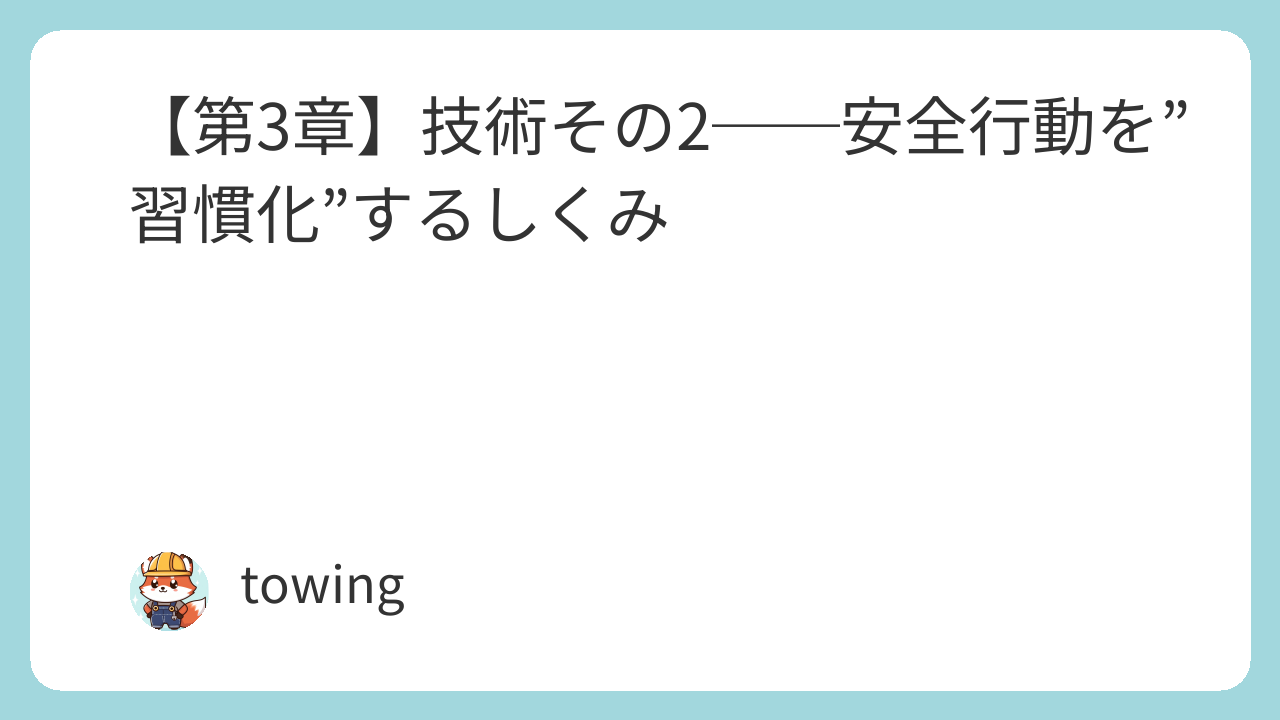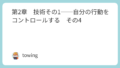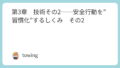なぜ、あなたの声は現場に届かないのか?
「動いている重機の後ろを歩くな。何度言ったらわかるんだ!」
「安全通路があるのに近道するな。転倒してケガしてからじゃ遅いんだぞ!」
皆さんの現場でも、このような光景を日常的に目にされているのではないでしょうか。指導する側は「なぜ、これほど当たり前のことができないのか」と苛立ちを覚える。一方で、指導される側も決して反発しているわけではありません。危険なことも、やるべきことも、頭では十分に理解しているのです。
では、なぜ理解しているはずのことが実行されないのでしょうか。
多くの現場では、この問題を個人の「意識」や「意志力」の欠如として片付けてしまいがちです。でも、それは根本的な原因ではありません。
答えは極めてシンプルです。
人間の意志力は、私たちが思っているほど万能ではない
からです。
意志力の限界を理解する
心理学には「自我消耗(Ego Depletion)」という概念があります。これは、人間の意志力や自制心がスマートフォンのバッテリーのように使うば使うほど消耗するという考え方です。
朝、満タンだった意志力のバッテリーも、一日中、様々な判断や集中、感情のコントロールを繰り返すうちに、夕方にはすっかり残量が少なくなってしまいます。
現場作業は、まさにこの意志力を絶え間なく消費する行為の連続です。段取りを考え、重い資材を運び、精密な作業に集中し、同僚とコミュニケーションをとる。夏の暑さや冬の寒さ、騒音や粉じんといった過酷な環境も、着実に私たちの意志力を削っていきます。
そのような状況で、「安全に気をつけろ」という漠然とした指示だけを頼りに、常に100%の注意力を維持し続けることは、人間にとっては至難の業です。意志力に頼る安全管理は、例えるならば穴の空いたバケツで水を運ぶようなものなのです。
最初は「よし、やるぞ」と意気込んでいた安全行動も、日々の業務の忙しさや疲労の中で、徐々に優先順位が下がり、ついには「面倒だ」「時間がない」という感情に負けてしまいます。
「やればできる」という精神論は、意志力が満タンの状態では通用するかもしれません。しかし、現場で本当に守るべきは、心身ともに疲労し、判断力が鈍った状態での安全です。
そのとき、私たちを守ってくれるのは、すり減った意志力ではありません。
無意識でも身体が勝手に動く「習慣」の力
なのです。
安全行動を歯磨きやシートベルトの着用と同じレベルの「当たり前の習慣」にまで落とし込むこと。それこそが、個人の意識に頼る不安定な安全から脱却し、誰もが安定して命を守れる現場をつくるための、もっとも確実な道筋となります。
本章では、そのための具体的な『しくみ』について考えていきましょう。