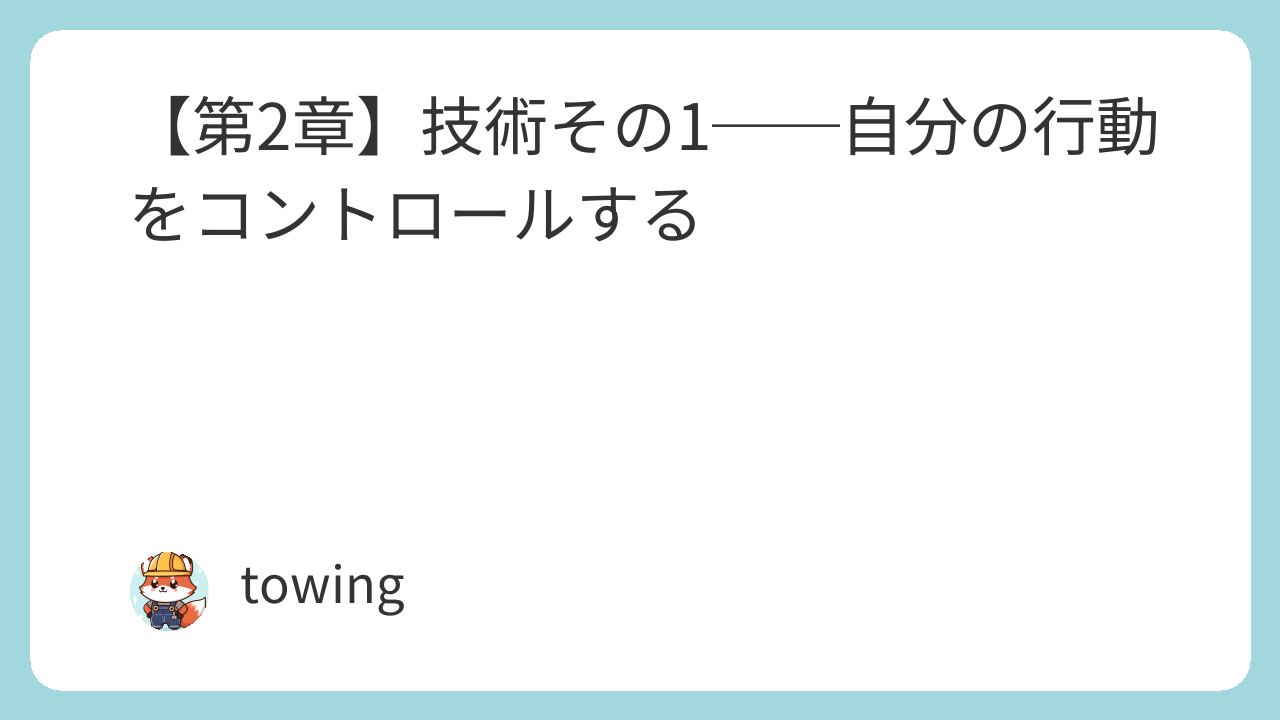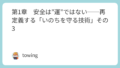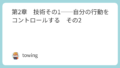ヒヤリの原因は「わかっていても、やらない」自分の中にある
「ヘルメットのあご紐、ちゃんと締めてくださいよ!」
「開口部の前で作業するときは、安全帯を使ってくださいって、あれほど言いましたよね!」
建設現場では、今日もどこかで、こうした注意の声が響いています。安全教育で繰り返し指導され、現場のルールとして明文化され、頭では「やらなければならない」と誰もが理解していること。それにもかかわらず、なぜ私たちは、時として安全行動を怠ってしまうのでしょうか。
この問いに向き合うため、私は数多くのヒヤリ・ハットや労働災害の報告書を読み解いてきました。そこで浮かび上がってきたのは、実に根深い事実でした。災害の原因の多くが「知らなかった」からではなく、
「知っていたが、実行しなかった」
からなのです。
このような経験はありませんか?
- 「ほんの数分だから、これくらい大丈夫だろう」と、安全帯のフックを掛けずに高所での作業を始めてしまう
- 「いつもやっているから、慣れている」という過信から、機械の安全装置を意図的に無効化してしまう
- 「とにかく急いでいるから、仕方ない」と、はしごをしっかりと固定せずに昇り降りしてしまう
- 「誰も見ていないから、いいだろう」という安易な気持ちで、定められた保護具を着用しない
これらは、決して未熟な誰かの話ではありません。経験豊富なベテランであっても、真面目で実直な若手であっても、ふとした瞬間に誰しもが陥ってしまう「心の隙」なのです。
そして私たちは、この「心の隙」を、あまりにも安易に「不注意」「気の緩み」「安全意識の欠如」といった個人の資質の問題として片付けてしまいがちです。
でも、本当にそうなのでしょうか。
「安全第一」とスローガンを唱え、個人の意識に訴えかけるだけでは、事故はなくなりません。なぜなら、人間の行動は、意志の力だけで決まるほど単純なものではないからです。はなくなりません。なぜなら、人間の行動は、意志の力だけで決まるほど単純なものではないからです。