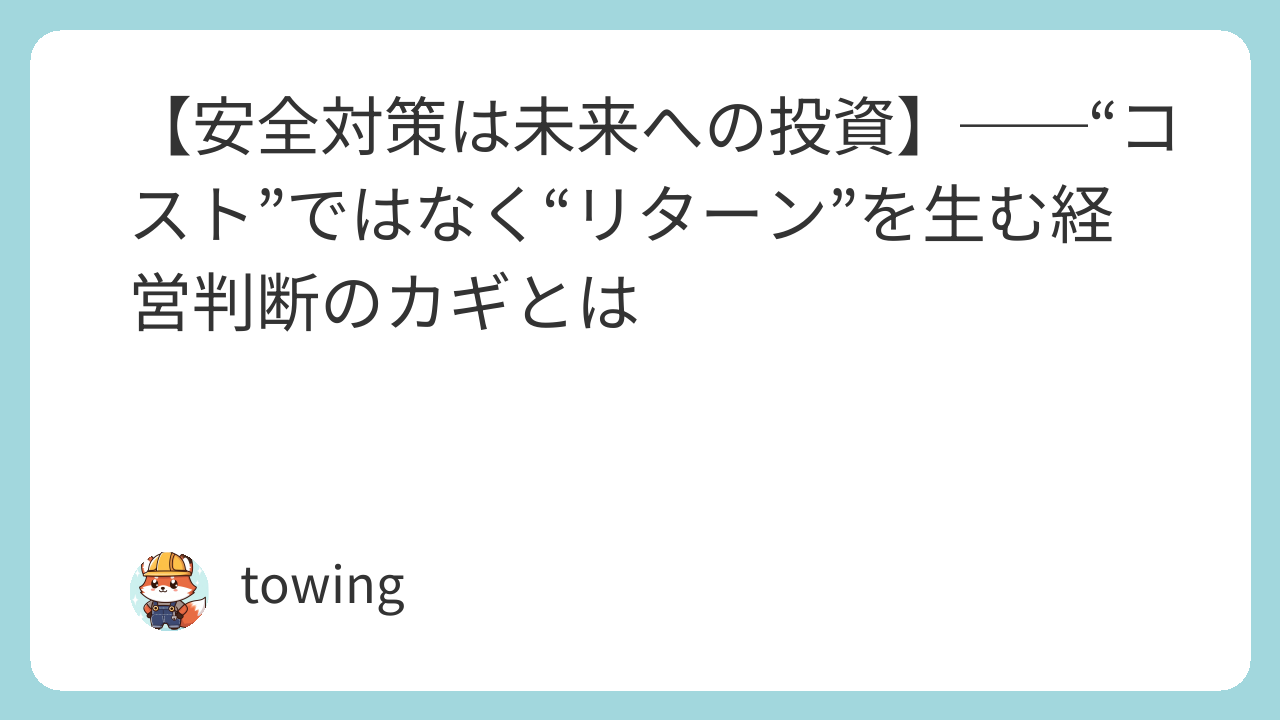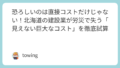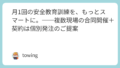はじめに
日々の安全活動、本当におつかれさまです。
現場でのヒヤリとした瞬間や、なんとか防げたあの一歩。
そんな毎日の努力が、誰かの命を守り、企業の信頼を守っています。
でも…
「安全対策はお金がかかるだけで、見返りがよくわからない」
そんな声が聞こえてくるのも事実です。
ところが最近、安全対策には“はっきりとした経済的効果がある”ことが、研究によって裏付けられました。
今回は、中央労働災害防止協会(中災防)と産業技術総合研究所が共同で行った調査研究をもとに、「安全対策の経済的評価」についてご紹介します。
安全対策は“見えない保険”ではない
安全対策にかかるお金は、「コスト」ではありません。
将来起こるかもしれない災害を防ぎ、損失を避けるための“投資”です。
今回紹介する評価手法は、いわゆる費用便益分析(CBA)です。
「この対策にいくらかかって、どれだけの損害を防げるのか?」
それを数字で“見える化”し、意思決定をサポートする仕組みです。
企業目線での分析に限定
・被災者本人や遺族の損害は含みません
・労災保険の給付など企業が負担しない費用は除外します
つまり、「企業として払った分と得られる効果」に焦点を絞ったシンプルで実践的な評価です。
経済的評価がもたらす4つのメリット
この手法を取り入れることで、経営にも安全にも、次のような効果が期待できます。
- 経営判断の合理化
安全投資の根拠が数値で示され、経営トップが動きやすくなります。 - “成果の見える化”でモチベーション向上
「何も起こらなかった」が最大の成果──この見えにくさを解消できます。 - 適正な安全対策費の算出
ムダなく、足りなくなく、ちょうどよい金額で継続可能な仕組みが作れます。 - 社会的信頼の獲得
社外に向けて、自社の安全活動の根拠と成果を示す“裏付け”になります。
実際、どう評価するのか?
この評価手法は、製造業の中小企業でも使いやすいように設計されています。
ここでは概要を簡単に紹介します。
1. 対象となる災害
- 主に死亡災害・重篤な災害(休業4日以上)
- 通勤災害や疾病は対象外
- 墜落、巻き込まれなど21種類の事故型と25種類の起因物をカバー
2. 費用の見積もり
- 初期費用(設備導入や教育訓練など)
- ランニングコスト(電気代、メンテ費用など)
- 廃棄費用(更新・除去にかかる将来コスト)
※すべて“割引現在価値”で評価
3. 効果の見積もり
- 災害がどれだけ減るかによって、回避される損害額を計算
- 「年千人率」を基礎に、全国平均と自社の安全レベルを比較
- 自社の安全レベルを5段階で選ぶだけで、頻度が自動設定されます
損害の中身も見える化できる
災害が起きたときに企業が被る損害は、多岐にわたります。
- 人的損害(治療費、補償、退職金の増額など)
- 物的損害(機械・材料の損失)
- 生産損失(操業停止、作業待機の人件費)
- 間接コスト(調査・報告、対外対応など)
- 労働損失による付加価値減少(被災者が稼げないことで失われる利益)
これらを「1災害あたり○円」と見積もることで、回避できる損害額が明確になります。
試算結果──たった50人規模でも最大3,000万円の効果
調査では、従業員50人の製造業が
「全国平均よりかなり危険」な状態から「かなり安全」に改善したケースで、
なんと最大3,000万円以上の損害回避効果があると試算されています。
特に注目すべきは、
「31日以上180日以下の休業災害」のリスクを下げた時の効果が大きい点。
頻度も損害も一定程度あるこのゾーンが、安全投資の“効果が高いところ”です。
とはいえ、課題もあります
- 評価に使う基礎データが製造業中心
- 安全レベル選択の目安がまだあいまい
- 間接的なメリット(離職率低下・企業イメージ向上など)は評価対象外
今後、評価ツールの改善や事例集の蓄積、第三次産業への展開が期待されます。
まとめ──「安全は数字で見える」
事故が起きないこと、それ自体が最大の成果。
でも、起きなかったからこそ“成果が見えない”というジレンマがありました。
経済的評価は、その壁を超えるツールです。
安全対策の本当の価値を、「費用」ではなく「効果」で語る時代へ。
中災防の評価ツールは、以下のリンクから無料でダウンロード可能です。
みなさまの安全投資が、働く人の命を守り、
そして会社の未来を支える確かな一歩になりますように。