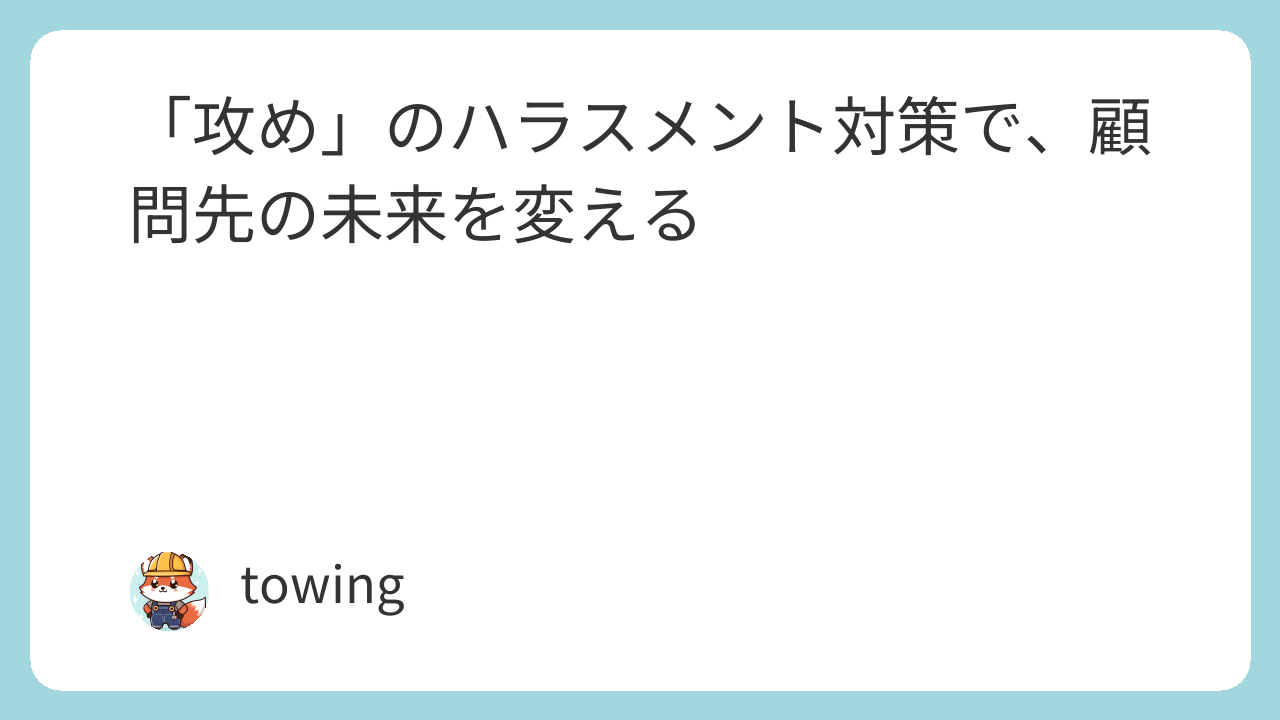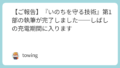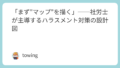はじめに
「ハラスメント」対策について、よくよく考えれば、個々の企業や人事担当者に働きかけることよりも、多くの顧問先を持つ社労士のネットワークへの働きかけが有効ではないでしょうか。
これからの時代、ハラスメント対策は単なる「守りの法対応」では終わりません。むしろ、企業の持続的成長を支える“攻めの経営戦略”として、社労士の出番が大きく広がる領域なのではないかと思います。
本記事は、これから社労士としてハラスメント対策に取り組むにあたって、本格的に考えるべきポイントを5つつに整理しました。
1. 「守り」から「攻め」へ──ハラスメント対策のパラダイムシフト
これまでのハラスメント対策といえば、トラブル発生後の対応、再発防止策、あるいは就業規則の見直し程度で済ませていた企業も多いのではないでしょうか。
しかし今、求められているのは問題が起きない職場そのものを、戦略的に設計していく力です。心理的安全性、従業員エンゲージメント、離職防止、業績向上──。これらをつなぎ合わせた提案が、これからの社労士に期待されています。
ここがポイント
- 顧問先への提案を「リスク回避」から「価値創造」へ
- 「心理的安全性」を業績に結びつける説明力を持つ
- 企業文化を変える介入策を、労務の枠を超えて考える
2. 法律対応は“最低限”──本質は社会的要請への応答
2022年4月、パワハラ防止法が中小企業にも全面適用されました。これで義務化対応は一段落──そう思っていませんか?
しかし、法改正の背景にあるのは単なるコンプライアンス強化ではなく、「安心して働ける職場」を社会全体で求めていこうという時代の空気そのものです。
Z世代を中心とする若年層の価値観も変化しています。「職場で嫌な思いをしたら辞める」が普通になった今、企業側も“選ばれる”努力が求められています。
ここがポイント
- 法令対応は“入口”であって“ゴール”ではない
- Z世代の心理に響く人事施策の再設計
- ESG・人的資本開示とハラスメント対策の接続
3. 効果を「見える化」──ROIで語る社労士になる
「うちはハラスメント研修をやってます」──この言葉だけで、経営者が納得する時代ではありません。今求められているのは、“この施策にどれだけの意味があったのか”を数値で示すことです。
例:対策の投資効果(ROI)
- 離職率の改善 → 一人当たりの退職コスト × 離職者数の減少
- 生産性の向上 → チームのパフォーマンススコア × 従業員満足度
- 企業イメージの改善 → 採用広報費の削減、口コミスコアの向上
ここがポイント
- 既存の顧問先のデータから、実効性のある指標を設計
- 数値化しやすいポイントを見つけて伝える
- 経営者と同じ“経営言語”で語る力を持つ
4. 「社労士にしかできない」ハラスメント支援とは?
社労士は他士業と違い、日常的に企業の「人」に関わり、現場のリアルを把握できる存在です。これは、他の専門職にはない圧倒的な強みです。
弁護士が担うのは主にトラブル後の法的対応、民間の研修会社は一時的な関与が中心。社労士は、予防から改善、そして組織風土の改革まで一貫して関われる立ち位置にあります。
ここがポイント
- 労務管理とハラスメント対策の連動ができる
- 現場に即した「実効性のある制度設計」が得意
- 継続的なフォローアップが自然にできる契約構造
5. 「新しい収益モデル」として考える
ハラスメント対策は、“手続き報酬”に依存しがちな社労士業務から脱却し、「プロジェクト型」や「継続支援型」の報酬体系を築くチャンスでもあります。
サービス展開のアイデア
- ハラスメント研修(動画+対面)
- 外部相談窓口の設置支援
- 組織風土診断・改善プログラムの提案
- ハラスメント対応フローの設計・運用支援
「社労士=相談役」という立場を活かし、現場と経営層の橋渡し役として機能するサービスが今、必要とされています。
今すぐできる3ステップ
Step1:現状把握
まずは、既存の顧問先におけるハラスメント対策の状況を“棚卸し”してみましょう。法対応の有無だけでなく、現場の声や離職理由など“温度”を感じる情報を集めてください。
Step2:提案の再設計
就業規則の見直しや相談体制の整備だけでなく、「心理的安全性を高めるためにどう制度と運用を設計するか」まで踏み込みましょう。
Step3:専門性を磨く
心理的安全性、エンゲージメント、ESG…新しいキーワードに対応できるよう、自身のアップデートも怠らずに。
まとめ──選ばれる社労士になるために
ハラスメント対策は、これからの社労士業務において確実に「成長市場」となっていきます。
まだ多くの社労士が十分に取り組めていない領域だからこそ、先行者としての専門性を確立するチャンスがあります。
手続きの“延長”ではなく、経営と人をつなぐ“戦略的パートナー”としての役割を担っていきましょう。