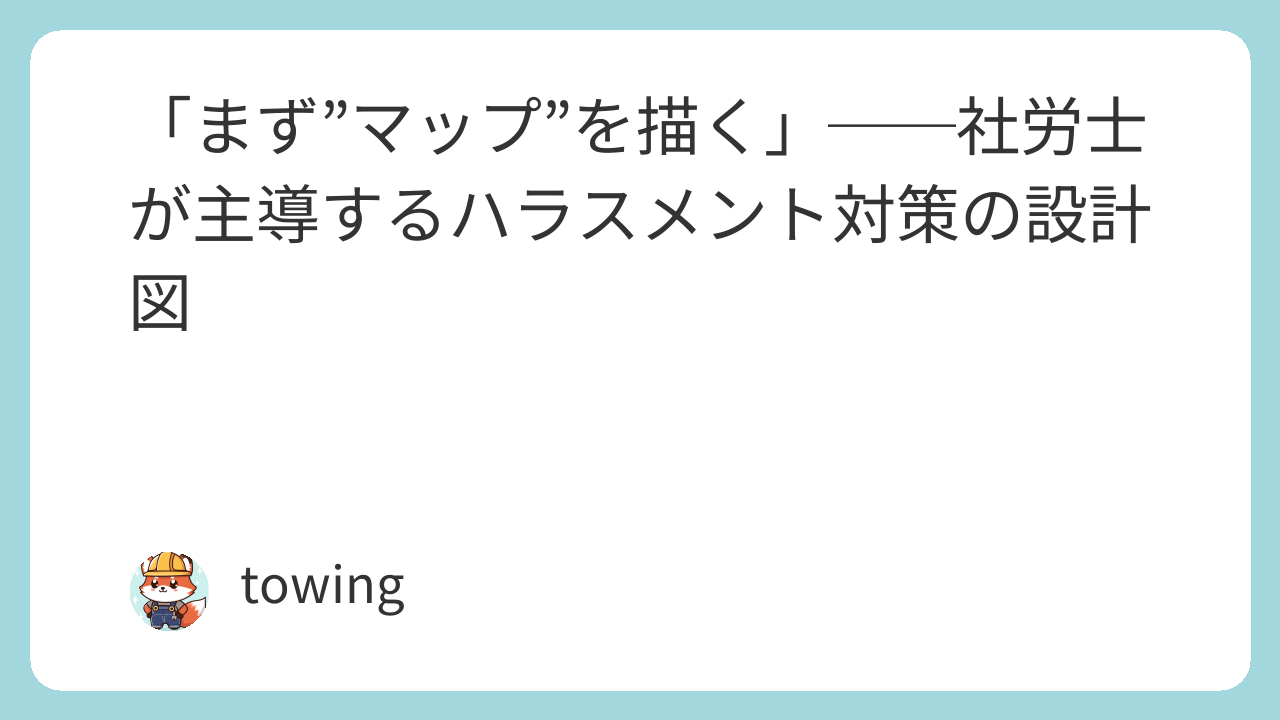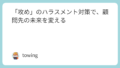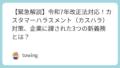はじめに
「先生、うちの会社、ハラスメント対策って何から手をつければいいんでしょうか?」
現場で最もよく投げかけられる質問のひとつだと思います。
「就業規則を直しましょう」「まず研修です」――確かに、どちらも欠かせない要素です。けれど、それ”だけ”では組織は動きません。なぜなら、経営者も管理職も、従業員も、皆が「で、結局何をどこまでやれば成功なのか?」という根本的な疑問を抱えたまま走り出そうとしているからです。
最初にやるべきことは、全体を俯瞰する”マップ(設計図)”を描き、社労士としての立ち位置と提供価値を明確にすることです。
私自身、北海道内の製造業から小売業まで、業種も規模も様々な企業を訪問し、ヒアリングと助言をしてきました。その中で痛感したのは、ハラスメント対策は「点(単発の施策)」ではなく、「線(連続したプロセス)」、さらに「面(組織文化の変容)」として捉えなければ成果が出ない、という事実でした。
そして、この全体設計こそが、プロフェッショナルである私たち社労士の真価が問われる領域です。
全体像を”点→線→面”で設計する
3層で考えると抜け漏れが見える
多くの企業が陥りがちなのは、目に見える「点」の施策だけに着手して、それで完了したと錯覚することです。しかし、本当に効果的なハラスメント対策は、以下の3層構造で設計する必要があります。
点(個別施策) 規程改訂、相談窓口の整備、研修の実施、再発防止策の作成など、いわゆる「やるべきこと」の一つひとつです。これらは確実に実行されなければならない基盤的要素ですが、バラバラに実施しても効果は限定的です。
線(プロセスの一貫性) 相談受付 → 調査 → 是正措置 → 再発防止 → 評価・見直し、までの手順を標準化して回すことです。つまり、点の施策を時系列で繋げ、一つのストーリーとして機能させることです。
例えば、ある食品加工会社では、相談窓口は設置したものの「相談が入った後、誰がいつまでに何をするのか」が曖昧で、結果的に相談者が放置される事態が発生しました。この会社では、相談受付から48時間以内の一次対応、2週間以内の調査開始、1か月以内の是正措置決定という「線」のルールを明文化することで、問題が解決しました。
面(文化・制度への埋め込み) 経営トップからの明確なメッセージ、管理職の行動基準化、評価制度との整合、心理的安全性の醸成など、組織全体の「当たり前」を変える取り組みです。これができて初めて、ハラスメント対策が組織の血肉となります。
社労士の価値は、「点」を「線」に束ね、「面」へと拡張させる”設計と運用”を主導できることにあります。 単なる規程の専門家ではなく、組織変革の設計者として機能することが、現代の社労士に求められている役割なのです。
まずゴールを設定する:「見えない目的地」では人も予算も動かない
「ゴールが見えない仕事は効率よく進めることが難しい」
これは、私が部下によく伝えていた言葉です。ハラスメント対策は長期戦です。法令遵守から文化変容まで、最低でも1年、本格的な定着には2〜3年を要します。だからこそ、序盤で”どこまで行けば成功と言えるのか”を労使で合意することが決定的に重要になります。
実務を振り返ると、うまくいった案件の共通点は”最初にゴールを言語化して共有できていた”ことでした。逆に頓挫した案件の多くは、ここが曖昧でした。
ある建設会社の事例では、最初の面談で「とにかくハラスメントをなくしたい」という漠然とした要望から始まりました。しかし、経営陣、人事部、現場管理職それぞれに「なくす」の定義を聞くと、全く異なる答えが返ってきました。経営陣は「訴訟リスクをゼロに」、人事部は「相談件数をゼロに」、管理職は「指導がしやすい環境を」。これでは方向性が定まりません。
そこで、1か月かけてゴールを言語化し、全員で合意を形成しました。その結果、プロジェクトは順調に進行し、1年後には目標とした成果を達成できました。
2-1. ゴールをこう書く(サンプル)
具体的なゴール設定の例を示します。重要なのは、“数値(KPI)×状態(定着・運用)”でゴールを定義することです。
【ゴール例】
・20XX年○月までに、法定措置義務(相談体制・周知・再発防止等)を完全実装し、実運用できている状態にする
・同期間中に管理職研修受講率100%を達成し、「初動対応」を標準化する
・匿名サーベイで「上司に相談しやすい」と回答する割合を○%以上へ改善
・相談受付から一次対応までの平均リードタイムを○営業日以内に短縮
・再発防止策の実行率、期限遵守率を○%以上に維持このように具体的な数値と期限を設定することで、プロジェクトの進捗が可視化され、関係者のモチベーション維持にもつながります。