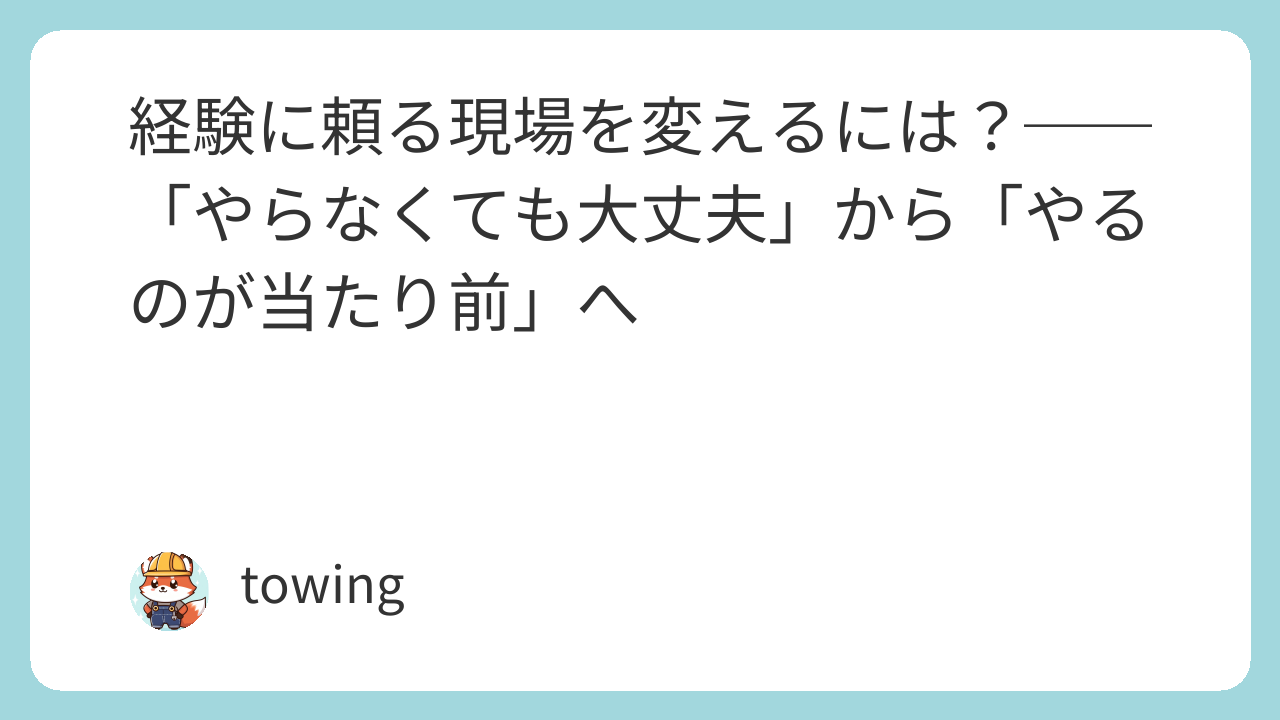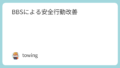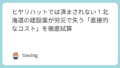「安全帯をかけるのは面倒」──そう言われて始まった試行錯誤
ある現場でこんな一言が聞こえてきました。
「そんな高いところじゃないし、安全帯はいいよ。時間かかるしさ。」
確かに、法律上の規制や社内ルールに違反しているわけではありません。けれど、「やらなくても大丈夫だった」経験が積み重なることで、不安全行動が“当たり前”になっていく。
これは小さな現場だけの話ではなく、どんな職場でも起こり得る人間の心理です。そこで、Behavior-Based Safety(行動ベースの安全)を使って改善を考えてみます。
なぜ人は「安全より効率」を選ぶのか?
まず、現場のベテラン作業者は次のように思っているのではないでしょうか。
- 「何十年やってきたけど、一度も落ちたことがない」
- 「安全対策してたら、作業が全然進まない」
- 「誰かに見られてなきゃ、やらなくていいって思っちゃうよな」
これは、行動心理の典型的なパターンです。
人間の行動は、「行動の直後にどんな結果があるか」で強化されていきます。
| 行動 | 直後の結果 | 心理的強化 |
|---|---|---|
| 安全帯を使わない | すぐ作業できる、楽 | → 不安全行動が強化される |
| 安全帯を使う | 手間・面倒・時間かかる | → 安全行動が敬遠される |
このメカニズムを逆転させなければ、現場は変わらない。そう考え、行動を変える仕掛けを考えなければなりません。
小さな工夫からのスタート──見える化と声かけ
まず着手すべきは、「何が望ましい行動なのか」を見える形にすることです。
- 作業手順書に「昇降設備の設置→作業開始」の明記
- 安全帯使用エリアの写真付きポスター掲示
- 朝礼でのルール再確認
しかし、正直なところすぐには変わらないでしょう。
「はいはい、わかってるよ」と軽く流されてしまい、ポスターの前を素通りする姿が目に浮かびます。
成功へのカギは「観察とフィードバック」
まずは、取組に行動観察を取り入れます。
- 作業中に、安全担当者がこっそり観察
- 安全行動をしていた人に「良かったですね」と直接声かけ
- 逆に不安全行動にはその場で丁寧に理由を聞く
この取組を続けていくと、次第に安全行動が増加し、不安全行動が減少していくことになります。そしてどこかで現場の当たり前が変化し、若手の作業員が昇降設備のセットに手間取っているときに、ベテランが声をかけたりします。
「お前、それちゃんとやってて偉いな。前は俺も面倒だったけど、最近は慣れたら逆に仕事の効率があがるぞ」
取組に対するポジティブな同調が現場で確認されると、現場の空気が一気に安全側に変化します。
「安全にやることが、かっこいい」に変わった
それからは、次のような変化が起こってきます。
- 安全に関する新たな取組みが現場で話題になり、改善案の声もあがるようになる
- 若手がベテランに「昇降設備まだです。ちょっと待ってください」などと気軽に声をかけるようになる
- ヒヤリハット報告が倍増(=意識の向上)
これらは決してルール強化や処分の強化ではない、「行動のポジティブな強化」から生まれてきます。
まとめ:経験に頼らず、習慣で守る
最初は「面倒だ」「時間がかかる」と敬遠されていた安全行動も、環境を整え、行動を観察し、良い行動を強化することで「自然にできる」ように変わっていきます。
行動を変えるには、「意識」よりも「仕組み」が先。
経験や感覚ではなく、行動科学を活用した改善こそが、職場の安全文化を育てるカギになります。
おまけ:現場でつかえる「安全強化の仕掛け」アイデア
- ✔ ポスターではなく、現場写真に手書きメッセージ
- ✔ 朝礼で「昨日の安全行動MVP」を発表
- ✔ 安全チェックを「やらされ感」から「チェックしてあげる役割」へ
経験を過信せず、やるべきことを自然にやる現場をつくる。
そのための試行錯誤を続けています。