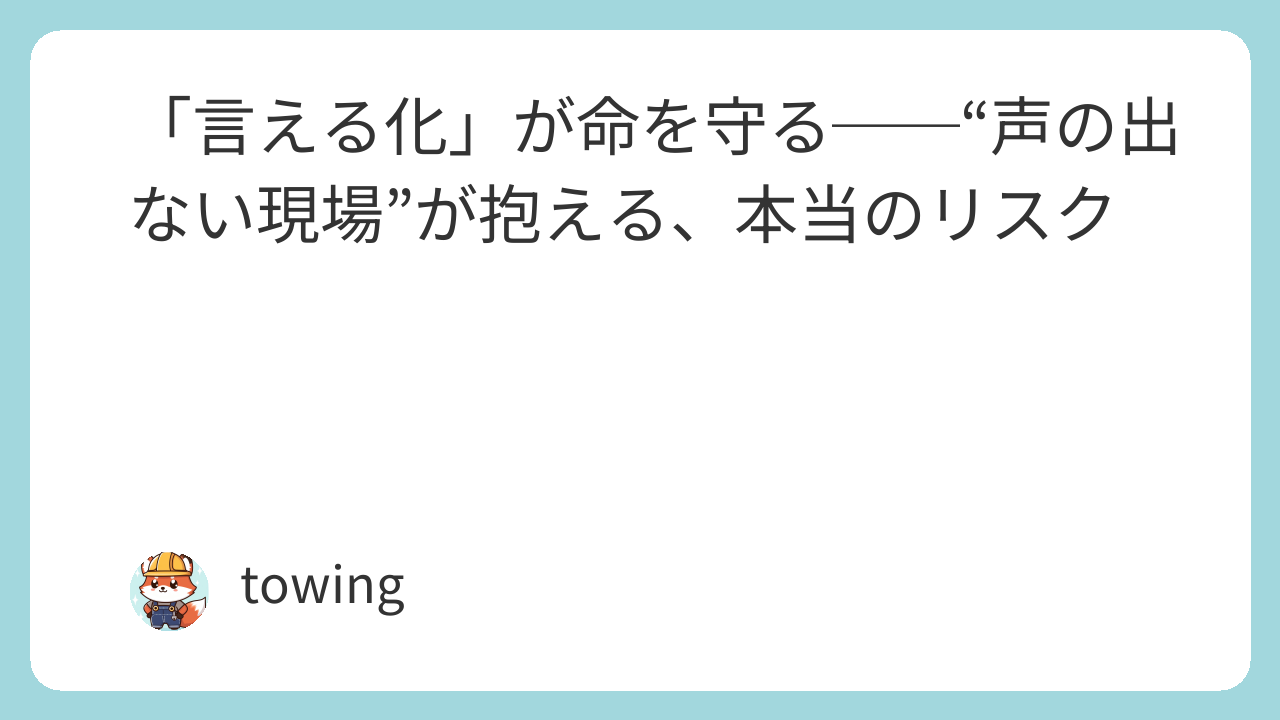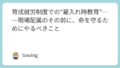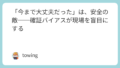はじめに
「あれ?」と感じた違和感を、口にできるか。
それが、労災を防げるかどうかの分かれ道です。
安全とは、マニュアルや設備の問題だけではありません。
“声の出る職場かどうか”が、すべての土台です。
言いたいことが言えない現場に、安全は育たない
危険の芽は、いつも最初はささいな“違和感”として現れます。
「なんかおかしい」「ちょっと怖い」──
その感覚が、周囲に伝わる前に押し込められてしまえば、ヒヤリは重大災害に形を変えます。
「言える化」とは何か?
言える化とは、現場で感じた不安・危険・疑問を、誰もがためらいなく言える状態を整えること。
それは声の大きい誰かに頼る仕組みではありません。
どんな立場の人でも、「おかしい」と思った瞬間に声を上げられる空気を職場全体でつくること──
それが「言える化」です。
小中高校生が教えてくれる“沈黙の始まり”
厚生労働省「平成26年度 全国家庭児童調査」によれば──
クラスで誰かが他の子をいじめているのを見たとき、「先生に知らせた」と回答した割合は
小学校高学年で49.4%、中学生で35.0%、高校生になると19.3%まで減少。
年齢が上がるほど、「声を上げない選択」が増えていきます。
見て見ぬふりが当たり前になっていく。
“言ってはいけない”環境は、学校生活の中ですでに育ち始めているのです。
そして社会人になっても、“言えない”は続いていく
厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査」では──
- パワハラを受けた人のうち「何もしなかった」人が36.9%
- 「上司に相談した」人は17.9%
- 「社内の相談窓口に相談した」人はわずか4.5%
さらに深刻なのは、その後の対応です。
勤務先の対応について、「特に何もしなかった」が53.2%に上ります。
つまり、“言ってもムダ”“言えば不利”という感覚が、職場に根強く残っているのです。
声が出ない職場が抱える“見えない危険”
声が出ない現場では、ヒヤリが共有されず、危険が常態化していきます。
たとえば──
- 「ここ、足場ちょっとグラついてます」
- 「この作業、安全対策いらないんですか?」
- 「昨日から少しやり方が変わってますけど…」
こうした声が出なかったせいで事故につながった現場は、数えきれません。
誰かが見ていても、“言えなければ、何も変わらない”。
沈黙は“性格”ではなく、“構造”の問題
「もっと声をだす勇気を出せ」
「気づいたなら言うべきだ」
──そうした声は、現場の沈黙を解消するどころか、むしろ深めてしまいます。
問題なのは、“黙らざるを得ない”環境を組織が放置していること。
「言いづらい」人が悪いのではなく、
「言いやすくしていない」職場が課題なのです。
言える化が進む職場に共通する3つの特徴
① 指摘が歓迎される
ヒヤリハット報告やちょっとした疑問にも、まずは「ありがとう」の一言。
面倒がられる空気がないことが、報告を継続させます。
② 声が変化を生む
報告されたことが改善され、現場ミーティングで共有される。
「言ってよかった」と感じられる体験が積み重なります。
③ トップが「声の価値」を発信する
上位者が明確に「言うことはリスク管理」だと語る。
“黙って働く人”ではなく、“声を上げた人”が評価される文化をつくる。
言える化が、命を守る
事故のあとに「気づいてた」という声が出てくることは、決して珍しくありません。
でも、事故の前には出てこなかった。
「声」がなかったのではなく、
「声が届く場所」がなかった──それが最大の問題です。
最後に──安全は“環境”で決まる
労災ゼロを本気で目指すなら、
ルールの厳格化より先に、「声が出る環境」を育ててください。
言える化は、制度や研修ではなく、“職場の文化”そのもの。
そしてそれは、意識して育てなければ絶対に根づきません。
あなたの現場では、声が出ていますか?
それとも、まだ沈黙が当たり前になっていませんか?