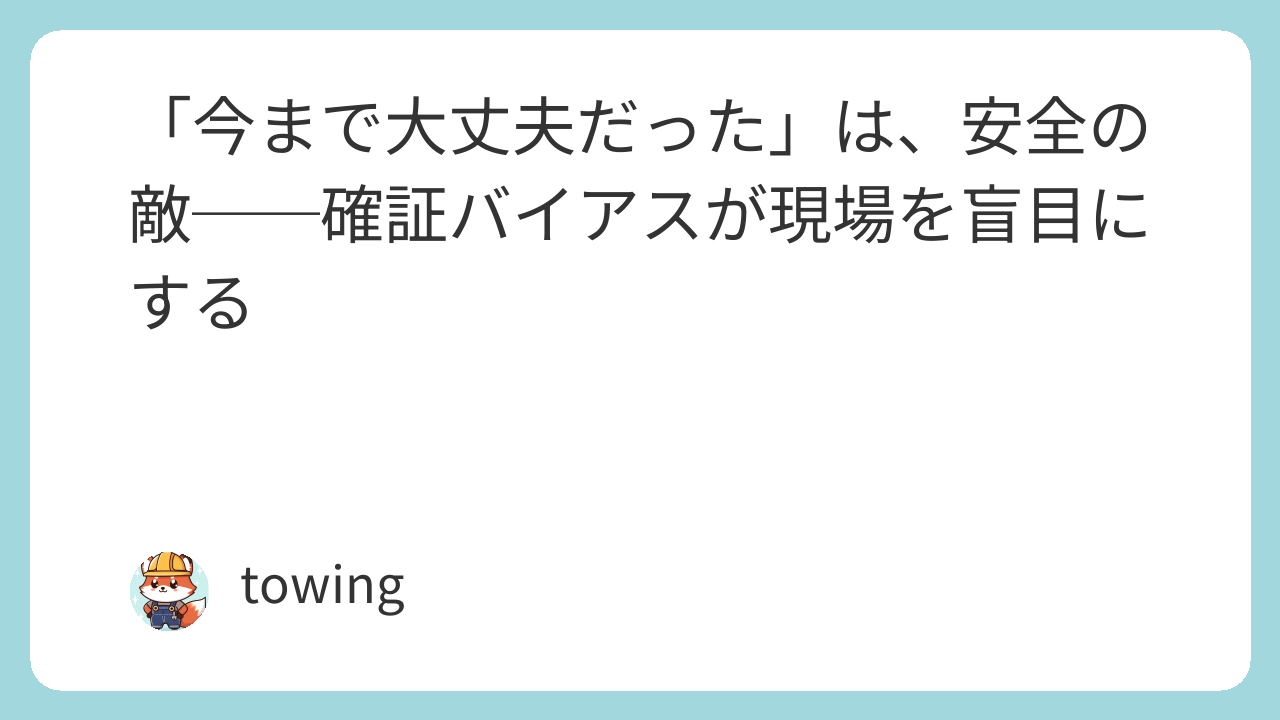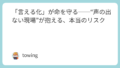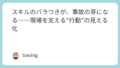はじめに
「いつも通り」「慣れたやり方」「うちは大丈夫」。
この言葉の裏にある心理、それが確証バイアスです。
確証バイアスとは、「自分の信じていることに都合のいい情報ばかりを集め、反する情報を無視してしまう心理的なクセ」のこと。
このバイアスが職場に根づくと、重大な災害が起きるまで危険が“見えないまま”になります。
「過去に事故がない=安全」ではない
「この作業、10年やってて一度も事故なんか起きてないよ」
この言葉、どの現場でも聞いたことがあるのではないでしょうか。
確証バイアスに支配されると、過去の“無事故”を“安全”の証拠として使ってしまうようになります。
しかし、事故は“たまたま”起きなかっただけかもしれません。
リスクが存在していても、運が良ければ災害は起きません。でも、それが安全ではないことは明らかです。
危険の“声”が封じられる
「そんなに気にしなくても大丈夫だろう」
「心配性すぎるって」
「言っても何も変わらないよ」
こうした反応は、危険への違和感を口にした人の“声”を潰してしまいます。
確証バイアスによって「安全である前提」が固まっていると、それに反する意見や指摘は“異常”扱いされ、結果として現場の沈黙を生み出します。
リスクアセスメントが形だけになる
確証バイアスは、「形式的な安全活動」を生み出します。
リスクアセスメントも、危険予知(KY)活動も、「いつもの通り」で進めてしまえば、「本日も問題なし」という安心が得られるからです。
しかし、現場は常に変化しています。
人も作業も環境も、少しずつズレています。
「いつもと同じ」に安心せず、常に“今の状況を疑う目”が必要です。
「慣れ」もまた、バイアスである
不安全な状態に慣れてしまう。
これは、現場に多い“麻痺”の一種です。
- 通路が資材でふさがれている
- 作業手順を守っていない
- 保護具が使われていない
これらが「いつもの風景」になってしまうと、もはや誰も疑問に思わなくなります。
確証バイアスは、“異常”を”正常”に見せかけるフィルターのように働きます。
確証バイアスにどう立ち向かうか
バイアスは無意識のうちに働くものです。だからこそ、意識的な対策が必要です。
第三者の視点を入れる
外部の安全パトロールや監査は、バイアスのない目で現場を見てくれます。
データで現場を見る
「感覚」ではなく、「数字と傾向」で安全を評価しましょう。ヒヤリハット、作業時間、教育実施率など、見える化された情報がバイアスに揺さぶりをかけます。
「なぜ?」を問い続ける
「なぜこれで安全なのか?」「なぜその手順なのか?」──答えが曖昧なら、それはバイアスの兆候です。
おわりに
労働災害は、往々にして「見えていたはずの危険」によって起こります。
しかし、確証バイアスがその“視界”を曇らせてしまう。
「今まで大丈夫だったから」ではなく、
「これからも本当に大丈夫か?」と問い直す習慣こそ、安全の出発点です。